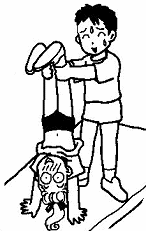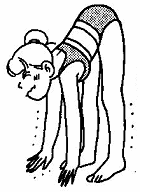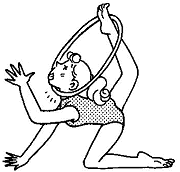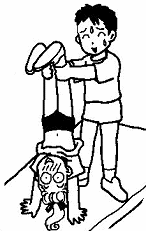
運動療法の効果 勉強会 平成18年10月20日
橋本泰嘉
今回は、運動療法の効果に限ってお話します。具体的なメニューについては、医師や運動療法士と相談しながら決めることをお勧めします。ある患者さんを例にして、解説します。
「運動療法の手引き」(糖尿病治療研究会編 医歯薬出版)からの例
糖尿病治療研究会が作成した本に、運動療法の効果を説明する良い例がありましたので、ここで紹介します。(一部改編)
昭和63年2月、検診にて尿糖陽性を指摘された。同年3月にブドウ糖負荷試験を実施され、糖尿病と診断されて4月初旬に入院した。入院の15年前より、心肥大、高血圧の治療をしていた。入院時のヘモグロビンA1cは9.3%だったが、空腹時血糖は143、食後血糖値も200以下と、血糖コントロールは意外に悪くなかった。コレステロール、中性脂肪も正常、肝機能にも異常を認めなかった。身長は152センチ、体重は73キロ、肥満の指数(BMI)は31.5(通常は22)と肥満があり、食事療法単独1200キロカロリー、薬なしで治療を開始した。
入院1週間後に運動療法の指示が出されたが、変形性膝関節症のため思うような運動ができず、ストレッチングを中心に実施。減量が進むにしたがい、筋力トレーニングや自転車運動なども行うようになった。何事にも熱心であり、後で聞いた話であるが、夜間に膝の痛みを我慢して病院内を歩いていたとのことである。1ヶ月の入院で体重は66キロに減少、空腹時血糖は83、ヘモグロビンA1cは7.6%となる。ブドウ糖負荷試験も高インスリン分泌を認めるものの、耐糖能は正常化した。
退院後も毎日のように運動指導室に通院し、現在まで12年間にわたり運動療法を継続している。ヘモグロビンA1cは5.8%以下と正常範囲を保ち、体重も60キロを維持している。平成4年からは2才年上の夫も運動に参加するようになった。現在も変形性膝関節症のために正座ができず、長時間の歩行も困難である。しかし、ストレッチングやあまり下肢を動かさないレクレーションスポーツを楽しみながら実施している。
余談になるが、夫が外来診察を経て初めて運動療法室に来院されたとき、まっすぐ歩行することも困難なくらいふらつきがあった。また、運動負荷テストでは不整脈が頻発し、循環器科へ紹介となった。このような理由で運動療法が開始されるまでに約2ヵ月を要し、半年間はストレッチングと軽い自転車運動のみで運動療法を実施した。現在も79歳と77歳の夫婦がいっしょに、自分達ができる運動を楽しんでいる。その姿は、「もう年だから運動できない」と言い訳する方々の口を閉ざしてしまい、「私にもできそうだ」という希望を与えている。元気で長生きするために運動が重要であることを教えてくれる症例である。
(注意点) 膝の痛みを我慢して運動するのが良いと言っているのではありません。膝が痛くても運動療法のやり方があり、効果があるということを強調している文章です。
体重と膝の関係
例に挙げた患者さんは、膝の痛みのために運動がやりにくい状態でした。歩く時には体重の2〜6倍の重さが瞬間的に膝に加わると聞かれたことがあると思います。仮に5キロ重くなると、膝の負担は10〜30キロ増えることになります。
ある先生が、30〜60歳の男女にアンケートをとったところ5〜6割の人が膝の痛みを持っておられたそうですが、その中で高度肥満の方は痛む割合がやせた方の1.7倍は高かったそうですので、おそらく体重が悪さをしているだろうと思われます。減量すれば、当然ながら膝への負担も相当軽くなり、痛みにも良い効果が期待できます。
膝が痛いときの運動の原則
この患者さんは、ストレッチを中心とした運動をされていました。膝が痛い場合には、いすに座った状態で足を伸ばし、太ももの前内側の筋肉を鍛え、関節の曲がる範囲を保つことを意識したほうがよいそうです。これは、日本人ではO脚の人が多く、腿の内側の力を使うことで膝の重みのかかり具合をかえることが期待できるからのようです。ただし、これは一つの意見にすぎませんので、そのような運動ばかりやるのはお勧めしません。
重みをかけて膝を伸ばそうとしても、膝が完全に伸びない運動では必ずしも思うような効果はないそうですので、重さを重くしすぎずに、膝関節が伸ばせる程度の負荷でやって下さい。膝の状況によって重さや回数を変える必要はあると思います。調子が良いからと、一気に負荷を強めると具合が悪くなるかも知れません。
あるスポーツドクターによれば、運動後には冷やしても暖めても、それを交互にやっても良いそうです。それによって血流の改善や、炎症の予防が期待できるそうです。ただし、これも科学的に実証されたものではありませんので、その後の反応を見て、冷やした方がよさそうなら冷やすようにされてはいかがでしょうか。少なくとも、冷やさなければならない、暖めなければならないという決まりはないようです。
膝が痛むときに、どのように運動すれば痛くなりにくいか、または痛みを強くしないで代謝面に効果的な運動は何かを科学的に実証した研究はありません。大規模な研究がしにくいからです。どの病院も、あまり根拠なしでやっています。明らかに良くないことは私にも説明できますので、こまごまと相談しながら試していくことをお勧めします。
運動が体重に及ぼす効果
この患者さんは体重がかなり減っています(73キロから60キロへ)が、運動をされていらしても意外に体重が減らないことを感じておられる方も多いと思います。統計でもそのように結果が出ています。運動選手のようなすごい量の運動をしないかぎり、なかなかやせません。普通はせいぜい数キロやせるかな?という程度です。脂肪が減っても筋肉が増えることや、そもそも運動で使うカロリーは何千カロリーに達することは望めないので、脂肪の何割を減らすというのは難しいからです。それでも効果があることが統計的に証明されています。したがって、体重が減らないから運動に意味がないとは考えないで下さい。
運動が血糖値に及ぼす効果
この患者さんは、ずいぶん血糖値が下がり、しかも安定しています。運動中に低血糖を起こされた経験をお持ちの方は、「運動は血糖を下げるなあ」という実感をお持ちだと思います。食事療法をしないで運動だけをした場合にどれくらいの効果があるのかは、どの病院でも必ず食事療法を指導されるために簡単に判定できない問題ですが、学者達が統計学を使って検討した結果、平均で週3日、約1時間の運動を約半年間続ければ、ヘモグロビンA1cは、0.6%下がるらしいと分りました。(コクラン データベース オブ システマチック レビューズ 2006;3:CD002968)
もちろん食事療法をするなと言っているわけではありません。運動療法に効果があると申し上げているのです。
運動が血圧に及ぼす効果
運動にも色々あります。例えば息をこらえて重量挙げをする時は、おそらく相当に血圧は上がると思いますが、呼吸を止めずにストレッチ体操などをやれば、それほど変化がないことが多いと思います。運動中の瞬間的な血圧の変化については、私を実験台にした時は、ヒーヒー言うほど動いたのに血圧は140〜150くらいまでしか上がっていませんでした。でも、ある実験結果を読むと、少なくとも最初の数十分は血圧がどんどん上がり、激しい運動の場合は健康な人でも200近くに上がることがあるそうですので、運動のやり方、負荷のかけ方に何の注意もいらないわけではなさそうです。
しかし、「運動療法中に事故が多いので運動療法をしないほうが寿命が長かった」という結果を出した研究はないようですし、血圧が高い時には出血予防のために運動を中止しなければならないという明確な研究結果もないようです。
逆に、運動療法を続けることで長期的には血圧が下がることが統計で証明されています。したがって、一定の血圧の治療をしながらならば、運動の制限はあまり考えすぎないほうが良いかもしれません。体調が悪い時は別です。
運動がコレステロールに及ぼす効果
症例のコレステロールについては何も書いてありませんでした、運動はコレステロールにも影響があるようです。個人差もありますが、通常は善玉コレステロールが増えて、悪玉コレステロールが下がる効果が出ることが多いようです。したがって、総コレステロールは意外に変化しなかったり、逆にやや増えることもありますが、だから良くないとは言えません。善玉の部分が増えることは、動脈硬化の防止のためには良いことだからです。