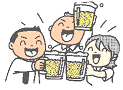気のせいか、飲酒した夜は体が熱を持って暑苦しく、睡眠も浅くなるように思います。アルコールは熱を発生させますから、当然でしょう。寝酒がないと眠れないと思って飲酒しても、かえって睡眠の質を落とすかも知れません。
睡眠中の状態を自分で評価するのは難しいので、アルコールの影響を自覚するのは無理かも知れませんが、せめて深酒は避けたほうが良いと思います。
トランス脂肪酸の制限
(トランス脂肪酸)トランス脂肪酸は合成した油だけではなく、乳製品など自然の食品にも存在しますが、含有量の多さを考えると、日本ではマーガリンやファストフード食品に含まれていることが問題になります。水素を添加して油を処理する際に、副産物として発生するそうです。
アメリカの政府機関FDAは、トランス脂肪酸を含む水素添加油脂の工業的生産を禁止するよう提言したようです(A Notice by the FDA on06/17/2015)。少量なら安全というデータがないので、全面禁止にすべきという理屈です。
工業的生産の禁止という意味は、おそらくマーガリンなどを製品として作る場合に、付随して発生するトランス脂肪酸を排除せよといった意味ではないかと思いますが、具体的にどうするのかは知りません。日本の場合は、マーガリンやショートニング以外にも、例えば植物性の食用油にも含まれているそうですが、米国では既に除去された製品が大半だそうですので、なんらかの方法はあるはずです。
(トランス脂肪酸の害)トランス脂肪酸の害としては、悪玉コレステロールを増やし、心筋梗塞などの疾患を増やすことが知られています。ただし、摂取することで実際にどの程度死亡率が増えるのかは分かりません。影響の程度が曖昧です。
以前は、飽和脂肪酸が良くないから不飽和脂肪酸が多い植物性油脂が推奨され、それに含まれるトランス脂肪酸は無視して良いのでは?といった、やや適当な理屈が幅を利かせていたように思います。そのレベルから進歩して、トランス脂肪酸も無視できないという意見が主流になりつつあるようです。
各々の食品に含まれる含有量について調べてみましたが、信頼できそうな統計は探せませんでした。欧州の推奨は含有量1%未満だそうですが、日本のマーガリンは10%以上の含有量があると書かれた文章を見たことがあります。でも、それが正確に計測された値かどうかは分かりません。記載すると消費者から敬遠されると考えているのでしょうか?
消費者としては、害が疑われるなら禁止してみては?と単純に思いますが、味や軟らかい感触を維持するために、食品業界は利用の継続を希望しているようです。
トランス脂肪酸は油を固めたり、臭いを除去する過程で発生するそうで、製造方法を変えると今より臭くなったり、酸化を受けて保存に支障が出たりして、商品の評価に問題が生じる可能性はあります。全面的に禁止すると、売り上げに影響することが会社にとっては心配でしょう。でも今後、米国で心筋梗塞が減ったら、さすがに日本も追随して規制するだろうと思います。
(当面の推奨)とりあえず固形の油脂類、お菓子、ファストフード類は、なるべく避けられたほうが良さそうです。マーガリンが良くないならバターを使おうか、あるいはパンに直接オリーブ油を塗ろうかといった考え方は、おそらく正しくありません。
一般に脂質には適量が決まっていて、脂溶性ビタミンや必須脂肪酸の摂取に必要な量、内容を確保できたら、ある程度は制限する方向で考えたほうが良いと思います。日本人の2−3割に脂質の過剰摂取があり、その割合は現在さらに増えつつあるそうです。脂質の過剰摂取は肥満、高血糖、心臓病、皮膚病の一部に影響することは間違いないと思います。油脂製品を適量まで減らすことを考えるべきです。
やがて日本のメーカーも工夫して、なんらかの方法でトランス脂肪酸フリーを宣伝文句にした製品を作ってくると思います。そうなれば、消費者の意識が高まって一気に市場の様相が変わるでしょう。
診療所便り 平成27年8月分より・・・(2015.08.31up)