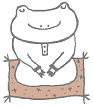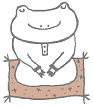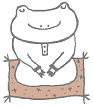脂肪と糖質のバランス
血糖値をコントロールしたい時に、糖分と脂肪分のいずれを制限すべきか、長い間の論争になっています。全く糖質を摂らないほうが良いという説を提唱し、本を書かれた方もおられます。
外来に来られる患者さんでも、主食を制限しない限り著しく高い血糖値が続く方がおられますので、糖質の制限にはそれなりの意味があると思いますが、患者さん全員に制限を勧めると、今度は低血糖やカロリーのバランスが狂うなどの問題が懸念されます。日本人の1型糖尿病患者を集めて、カロリーや糖分、脂肪分のバランスが血糖値に与える影響を調べた研究が発表されました(糖尿病55(1):6-11.2012)。
この論文では脂肪分が増えると血糖値は上がり、糖分では影響が少ないという結論でした。意外にも糖分を制限しても血糖値が改善しない場合があるということです。ただし、その内容を見ると歴然とした差ではなく、個人個人でかなりのバラツキがあるようです。
食べる物の全体の量やカロリー、野菜の量や消化吸収の早さ、栄養素の代謝の能力、体力や筋肉の量、運動量などには個人差がありますから、ばらついて当然だと思います。さらに考えれば、ある人では脂肪分が多いことで動脈硬化などの悪影響を及ぼす、ある人では糖分が多いことで血糖値をコントロールできずに糖尿病の合併症が進行する、そのような差もあるでしょう。
また、代謝に関わることは直ぐに結果が解らない点にも注意する必要があります。例えば発癌性ですが、脂肪分の割合が増えることで癌の発生が増えることは予想されます。昔よりも大腸癌が増えている原因は、タバコや乳製品とともに脂肪分が関係していることが疑われています。“腸内環境の変化”と言われる疑念です。糖質制限によって癌は増えたという結果も考えられます。
さらに、糖質制限によって一種の飢餓的状態が生じますから、飢餓によって誘発される“ケトーシス”のため、急死する可能性もあります。長期的な安全性、効果に関しては、ただ体重や血糖値を見ただけでは解るはずがありません。今回の研究は”1型”糖尿病患者を対象としていましたが、2型糖尿病ではどうか、膵臓の病気による糖尿病ではどうかなど、おそらく一概に言えるものではないでしょう。
自分で上手くいったから他の人にも勧めたいという気持ちは判りますが、個人差のせいで他の人で害が出た場合、責任を取れるかは疑問です。発表するのは客観的な検証を経た結果に限定するのが、真摯な態度です。読む人がどのように影響されるかも考えるべきでしょう。
血糖値を上げるのは糖分、それを制限すれば良いという考え方は、間違いではないでしょうが、単純すぎるようです。まだ解明されていない点も多いので、主治医や栄養士と色々な面から検討し、試行錯誤で答えを探すのが正しいやり方だと思います。
平成24年4月診療所便りより(2012.05.31up)