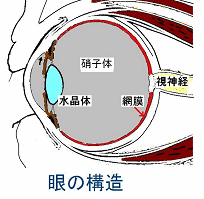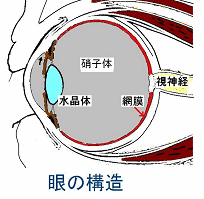
目の手術と糖尿病の関係 勉強会 平成21年6月18日
糖尿病では、さまざまな目の病気が出やすいため手術を受ける機会も多い傾向があります。手術の前には詳しく説明されると思いますが、基礎知識がないと話を理解するのは難しいものです。今回の勉強会では代表的な目の手術について、特に糖尿病がらみの危険性について説明します。
既にお気づきかと思いますが、眼科は検査の多さが目立つ傾向はあります。断言はできませんが診療報酬の制度の面で眼科の検査が収入を得やすい関係かもしれません。いっぽうで、きちんとした検査をしないと危険を伴いますし、検査や手術の件数が少ない病院は技術に不安も感じます。手術の必要性の判断、病院選びの判断は簡単ではありません。
眼の手術の前後には、手術を成功させたいからと急に真面目に糖尿病の治療をする人が多いのですが、血糖値が急激に改善すると眼に悪影響が出ることもありますので、医者とよく相談してください。
目の構造
目の手術を受ける時には、まず目の構造を知っていないと説明を理解できません。目は縦断面で見ると、右のような構造になっています。角膜や水晶体を経て眼に入った光は、奥にある網膜に焦点が合うように集められて初めて物の形として感じることができます。途中の角膜や網膜が濁っていたら光が散乱してしまい、光を正確に感じ取ることができません。
①白内障手術
糖尿病では白内障が起こりやすくなることが知られていますが、理由ははっきりしません。白内障は水晶体がにごる病気です。したがって、手術では濁った部分を入れ替えるのを基本とします。水晶体はレンズとして働いていますので、代わりに人工のレンズを入れるのです。
手術すべきかどうかは、眼科の先生と相談してください。眼科の病院によって考え方が違うことはありますので、一箇所の病院で手術が必要と言われても絶対に必要とは限りません。二箇所くらいは受診してみたほうがいいと思います。日常の生活で不便に思う点が増えたら手術を考える、例え白内障があっても日常で困ることが少なければ手術しないというのが一般的な方針だと思います。
ただし、以下のような場合には手術を念頭に入れて考える必要があると言われています。
非常に高度の白内障(白内障以外の眼病を引き起こすため)
糖尿病性網膜症の治療が必要な場合(レーザー治療の邪魔)
逆に手術成績が良くない、もしくは危険度が高いので手術を遅らせる方向で考えたほうが良いのは以下のような場合です。
糖尿病性網膜症が進行中(網膜症の悪化を招く)
目に入る血管に動脈硬化がある(炎症などが長引きやすい)
過去に目の手術で角膜内皮に問題がある(角膜に障害をきたす)
片目だけが白内障で、手術後に視力の左右差が予想される
前立腺肥大の薬を内服中で、これを中止できない
(タムスロシンという薬は手術成績を悪くします)
手術の合併症
公表されている手術成績は以下のようなものです。手術中に最大5%くらいは合併症があると覚悟すべきです。(ほとんどは何らかの対処が可能です)
後のう破損 1~2%
チン小体断裂 1~2%
網膜はく離 0.2%
緑内障 0.2%
その他 (感染性眼内炎、レンズの度数が合わない、再手術など)
視力の回復具合
公表されている国内各地の病院の手術成績では、7~8割の人が視力1.0以上になり、1割の人は0.6以下にとどまるようです。病院によっても多少の差はあると思いますが、かなりの人は視力が改善するので、事故を心配しすぎて見えないのを我慢するのは正しい考え方とは言えません。
手術自体は単純な作業ですので、ベルトコンベヤーに乗せられるかのように数十分で終了します。入院せず日帰りでできる施設も増えていますが、目薬をたくさん差さないといけませんので、管理に自信がない人は入院されたほうが安心です。
②緑内障手術
緑内障は眼の中の圧が高くなって、視神経が障害を受ける病気です。症状は進行して初めて出ることが多いそうですが、視野が狭くなり最終的には失明してしまいます。途中の段階では何の症状も感じていない人がおられますから、症状がないのに手術が必要なんて本当か?と信じられない場合も起こりえます。眼の中の圧が正常であるにもかかわらず緑内障と同じような症状、所見が出る場合もあります。
緑内障の原因は、眼の中の炎症などが引き金となって眼の中を循環している液の流れが滞ることによると思いますが、はっきりした原因が分からないことの方が多いそうです。
糖尿病における原因としては、糖尿病性網膜症が進行して病的な血管が新しく発生(新生血管)した場合が挙げられます。眼の中の液体が通る部分は眼の前のほうにありますが、ここに新生血管ができると液の調節が効かなくなります。網膜症で大きな出血があった後などは緑内障が起こる人も多いように経験していますが、血液が眼の中の液体の流れを滞らせる結果かも知れません。
慢性の緑内障は症状がはっきりしない病気ですので、手術を受けても効果を実感しにくいかもしれません。手術の目的は眼の中の液体の流れを良くし、病気が進行して失明しないようにすることですので、つまり予防の意味合いが大きく、手術を受けて視力が良くなるという実感は必ずしも期待できません。眼圧(眼の中の圧)が改善するかどうかで判断することしかできません。
目薬で眼圧を下げることができる場合は目薬の治療、目薬が無効なら手術が必要になります。手術には様々な方法があります。通りが悪くなった場所が分かっている場合は、針でそこに穴を開けることができます。レーザー光線で穴を開ける場合もあります。神経ブロックの応用によって眼の血流を上げる治療をすることもあるそうです。白内障の手術といっしょに手術する場合もあります(どうせ眼にメスを入れるから、いっしょにやれる)。
レーザー光線での治療の場合は入院の必要がないことが多いようですが、その代わりやや成績が悪くて、結局メスを入れる必要が出てくる可能性もあります。その他の場合も手術自体は短時間で済みますが、その後に再び穴が詰まることもあるため、通常は入院して眼の圧を管理しなければなりません。
③硝子体手術
眼の奥の硝子体内に出血、網膜が剥離して眼の外からの治療に反応しない場合などは、眼の中(白内障で扱う水晶体よりも奥)に針状の器具を入れて手術をすることがあります。これを硝子体手術と言います。
硝子体手術は年々技術が進歩し、視力を回復する人が増えてはいますが、もとの視力まで回復する人は多くありません。でも軽い病状の人で9割、重症の方の場合は6割近くは有効だそうです。昔と比べると成績は断然良くなっています。
糖尿病患者さん全部の中で、網膜症で失明の危険がある人の割合は2割くらいだという統計があります。網膜症の初期の段階では、仮に網膜に出血があってもレーザー光線で網膜を焼いて固める「光凝固」治療が有効です。早い時期なら8割、遅い時期でも4-5割の人に、それなりの効果が得られますので、いきなり硝子体手術をする必要はありません。でも眼の外からの光凝固で充分なコントロールができなければ、硝子体手術が必要になります。他に手がないからです。
硝子体手術は本格的な手術ですので、硝子体手術の成績が良い病院は本格的な眼科だと考えて間違いありません。白内障手術は、これに対してやや商売の色合いがありますので、手術をたくさんしているから本格的とは必ずしも言えないように思います。ただし、これは個人的印象で根拠はありません。
④レーシック手術
角膜をレーザー光線で削り、光の屈折率を変えることにより近視を矯正する治療法。9割以上の人が、裸眼(メガネ、コンタクト無し)で視力1.0以上になると言われています。数種類の削り方があるようです。
健康保険は使えませんので、10~20万円前後の費用がかかります。また、日本では2000年頃からの歴史しかありませんので、数十年後にどのような後遺症が出るのかは分っていません。角膜を削りますので、角膜が薄い人などは危険を伴います。まれに感染症によって、視力が悪化する場合があります。(最近、銀座の病院での集団感染が報道されました。)
糖尿病とレーシック手術の成績に何の関連があるかは分りませんが、病院側からは糖尿病を問題視されるかも知れません。感染症自体が非常に稀なので、特に糖尿病だから感染の確率が高くて手術が危険とは言えないと考えますが、網膜症などのために思ったよりも効果を実感できない場合はあるかもしれません。また、糖尿病性神経障害のために角膜の知覚が落ちている患者さんもいるので、角膜の異常に気づくのが遅れる可能性はあるかも知れません。
費用が安い病院が危ないかどうか、宣伝で目に付く病院が良いのかどうか、症例数が多い病院が本格的なのかどうか、眼科医の先生でも分からないのが現状ですが、数十年後にははっきりしてくると思います。
平成21年6月 勉強会資料より