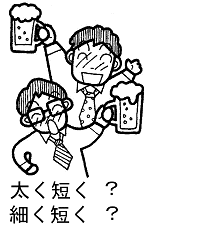食育のススメ
医学研究のテーマの中心は癌や移植です。技術も日々進歩しています。しかし健康を考えるうえで最も重要なのは、代謝の管理だと考えます。
意義について
例えば大腸ポリープを取る技術は進みましたが、取っても寿命が延びるとは限りません。まったく意味がないとは言えませんが、延命効果や医学的な意義を証明されてはいないのです。なんとなく病気を治療したような気になっているだけかも知れません。
また、例えば心臓手術の第一人者がいたとします。心臓の移植が必要になったら、その先生に頼まないといけません。でも、その先生が優秀だから長生きさせてくれるかと言えば、それは必ずしも期待できません。
動脈硬化で血管が詰まったら手術してつなげばいい、動きが悪くなった心臓や腎臓は取り替えればいい、予防を必要としない最先端の医療を受けたい、説教臭いのはイヤだ。我々は誰でも、そんな認識を多少は持っています。でも実際の治療は単純にいかないこともあります。手術すると、かえって成績が良くないというケースも少なくないのです。
代謝がうまく機能していない状態では、細胞の中ではいろんなことが起こります。不必要な物質が産生される、コレステロールが変性する、ホルモンの分泌が変るなど様々ですが、その結果は多方面に及びますから、ちょいと手術で解決とはいきません。目に見えにくくて解りにくいのですが、動脈硬化、老化、癌化などの他に、金銭面、精神面にも影響します。代謝の管理に派手さはありませんが、意義は非常にあります。
スーパードクター宣言
私は学生時代に、手術よりも代謝の管理が重要だと考え専門を選びました。収入を考えると眼科や耳鼻科を選ぶほうが利口ですが、意義を優先したいと思ったのです。どんなに手術手技が上手くて充実感があり、高い収入を得たとしても、病気になった結果の掃除にすぎない仕事は空しいと感じたのです。青臭い考え方ですが。
研修医時代は、まだ自分の専攻に自信を持てませんでした。医者の中で心臓外科や脳外科は花形です。手術が必要になると自分が無力に思えます。心臓外科は格好いい、自分はショボイ(格好悪い)と思いました。でも今は自信を持っています。健康を維持し、生活の質を落とさず、寿命を長くすることができたなら、やはり最高の医療です。
もちろん証拠があるわけではないのですが、世界一の脳外科医や心臓外科医がいるとしても、人の20年後、30年後にまで有効な医療を提供したい場合には私のような考え方しかないはずで、私と同じように治療するはずです。テレビで紹介されるスーパードクターがどれだけ手術が上手くても、寿命を延ばすことに関しては私に敵わないように思います。見かけ上どんなに私がショボくても関係ありません。実は私はスーパードクターより凄いのです(そうは見えないと言われます。外見は確かにパッとしません)。
養生訓
さて、ご存知かもしれませんが、健康に関する古書に貝原益軒の「養生訓」があります。江戸時代の学者の書いた本で健康の秘訣が書いてありますが、例を挙げると、うどん(ファーストフード)ばかり食べると早死にする傾向がある、それに早食いはするな等と書いてあります。今でも通用しそうです。
テレビや新聞などで食育が話題にのぼることは多いのですが、残念ながら昔の知恵が現代には引き継がれていないと思います。なぜ引き継がれないかを考えてみましたが、理由のひとつは生活環境が変るからでしょう。
生活の状況が変化すると、当然指導の内容も変ります。栄養が不足する時代が続いたら滋養をめざすことが先決ですし、飽食の時代にはダイエットが重要になります。この辺の変化に我々の感覚が対応しきれていないのでしょう。親の常識が子供に通用しなくなるのは世の常ですが、食事に関してもそうです。食品も随分変ります。
他の理由としては、生き方の問題があります。食事に関する考え方は生き方に通じます。正しい食生活をしていない人は、たとえバリバリ仕事をこなしていても自分の能力や健康を過信している点から考えて、何かしら判断に問題があることが多いようです。今の自分が問題ないと感じる食事が、過去の知恵からは異常かもしれない、害があるかも知れないと推測できる能力がないと、おそらく仕事や家庭生活の対応能力にも問題があります。
太く短く
生き方が絡んでいますので、説明して納得を得るのは容易なことではありません。冗談めかしてですが、よく患者さんから「自分は太く短く生きるから、ほっといてくれ!」と言われます。口に出しては言われませんが、表情も「細かいことばかりぬかしやがって、何が楽しいんだ。」と言いたげです。私も自分が病院にかかった時はそんな感じです。
でも実際に太く短く生きてコロッと死ねる人は稀で、動脈硬化でボロボロ状態になって苦しむことがほとんどです。その点を説明しても納得してもらえません。まだ目に見えない将来のことだからでしょうか。食育のセンスがない人に理屈を話しても、理解していただくのは難しいようです。手遅れにならないように、子供の頃から食事習慣のセンスを養わせることをお勧めします。
平成21年8月