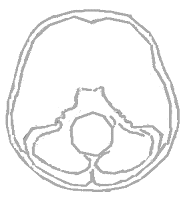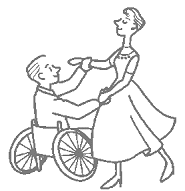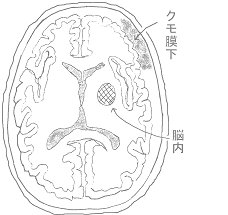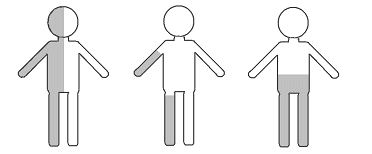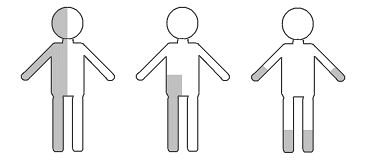������@�����P�W�N�U���P�T�� �@
���{��
���A�a�Ɣ]����
�@���A�a�͔]�������N�����₷������ƌ����Ă��܂��B�]�����̓}�q�Ȃǂ̕|�����ǂ��������a�C�ł��B�g�߂ȕ��̒��ɂ��A���̕a�C�ɂȂ�ꂽ����������Ǝv���܂��B���̕���̖ړI�͈ȉ��̂Q�ł��B
�@�P�@�\�h��ڎw������
�@�Q�@���������A�Ώ������Ȃ����Ɓ@�@�@�@
�p�ꂪ����ɂ����b�͏ȗ����܂��B�����܂��ɔ]�����̈Ӗ���Ǐ�𗝉����A�\�h�ɂ��Ă̍l�������w�т܂��傤�B
�]�����Ƃ́H
�@�]�����͉p���stroke��Abrain attack�ɑ������܂��B�]�̋}���̔���Ƃ����悤�ȈӖ��̌��t�ł��B��������]��ᇁA�]�̊O���Ƃ͈Ⴂ�܂��B�]�₻�̎��ӂɉh�{�𑗂��Ă��錌�ǂ��j��ďo�����邩�A���ǂ��܂��Ă��܂��i�[�ǁj�a�C���Ӗ����܂��B�܂茌�ǂɊW����a�C�ł��B�a���Ō����A�N�������o���A�]�o���A�]�[�ǂ��A���̑�\�ł��B
�@�N�����Ƃ����ƕ���ɂ����ł����A�N�������͐}�ł�
�]�̊O���̐F��h���������������܂��B�@�ΐ��̕�����
�]�o�����悭�N����ꏊ�ł��B�@�]�[�ǂ́A�]�Ɍ��t��
�����Ă��錌�ǂ��l�܂鎞�ɋN����܂��B�ꏊ�͔]�̂�
���ɂł����肦�܂��B
�]�����̉e���́H
�@�i�����Ɋւ��āA�Љ�I�A�o�ϓI�����A���_�I���S�j
�@�]�����̎Љ�I�ȈӖ��́A�܂����Ɋւ��a�C�ł��邱�Ƃł��B���{�l�̎����̓��v�����N�̂悤�ɔ��\����Ă��܂����A���ɑ������炢�̎��S�Ґ�������Ă��܂��B����������Ɣ]�����̍����ǂł���]���ǐ��̔F�m�ǁA��Ⴢɂ���ċN���鍜�܁A�Q������ɂȂ������߂̊����ǂȂǂ��܂߂�ƁA���܂��Ɏ����̑��ʂ�������܂���B
�@�]�����̎Љ�I�Ӗ��̑��́A�Ƒ���Љ�ɂ��܂��܂ȕ��S�������Ă��܂����Ƃł��B�����̌��ǂ��c�����ꍇ�ɂ́A���N�Ȏ��̎d�������Ȃ��͓̂���Ȃ�܂��̂ŁA��������g�̉��̕��B�ɂ���������܂����A�N���ɉ�삳��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂ͐��b������l�̕��S�͑�ςȂ��̂ł��B
�@�o�ϓI�ɂ�����������܂��B���܂܂ł̎d�����ł��Ȃ��Ȃ�ƁA���R�Ȃ�����������邱�Ƃ������A���@��O���ʉ@�̔�p�A�����˗�����ꍇ�͂��̔�p�B������Ƃ����O�o�ɂ���ʎ�i�̈Ⴂ����o����������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���_�I���S�������܂��B�܂��u�ǂ����Ď����͕a�C��
�Ȃ����̂��낤�B�v�u���̎��������Ă���Εa�C�ɂȂ�
���ɂ��̂ł́H�v�u�܂��Ĕ�������ǂ����悤�B�v
�Ȃǖ{�l�̔Y�݂����邱�Ƃ͂���܂��A�Ƒ���
���l�̔Y�݂��������ăC���C�����܂��̂ŁA���܂�����
�����ł��B
�]�����̌o�߂́H
�@�]�����̌o�߂��ȒP�ɂ܂Ƃ߂�A�ȉ��̊��Ԃɕ������܂��B
�@�@�P�@����̑O�G��A�����Ǐ�
�@�@�Q�@�Ǐ�̕s�����
�@�@�R�@�Ǐ�̈���
�@�@�S�@�@�@�@
�@��������Ɍ������K�v�ł��B�@�O�Ԃ�̒i�K�Ŕ����ł�������̂ł����A�ꎞ�I�ȃ}�q�̂悤�ȓ����I�Ȃ��̂��o�邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B�Ǐ����Ă��A�قƂ�ǂ̏ꍇ�͕��ׂȂǂƋ�ʂł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@�����ɂ͏Ǐ�͈��肵�Ă��܂���B�y����Ⴢ������̂Ɏ���ɐi�s���邱�Ƃ�t�Ɋ��S�ɓ����Ȃ������葫�������o�����Ƃ�����܂��B��Ⴢ��o��̂͐_�o�̍זE���@�\���~���邩��ł����A����̏����Ȃ�זE���@�\���Ȃ��Ȃ�̂�h�����Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�l�܂������ǂ��ēx�J�ʂ���A��i�Ő_�o�זE�ɏ��Q��^���镨���̔�����j�Q����A�������Ă�����̂�����Έ����������A���ł��B
�@��Ⴢ��c���Ă��A���n�r���œw�͂��Ē����������
���������܂��B�K�^�ƁA���������w�Ö@�ƁA�w�͂Ƃ���
�낦�Ή\�ł��B
�]�����̍����ǂɂ���
�@�@�x���A�ݒ�ᇇB������C�A�H�����ǁi�N�����j�D�������E�q�f�F�E���G�������H���܇I�F�m�ǁi�s���j�J�S�s�S�@�@�@�ȂǗl�X�Ȃ��̂��N����₷���Ȃ�܂��B�]����A�]�̃w���j���������ǂƌ����邩������܂���B
���������]�����ɗ^����e���́H
�@�@�@���A�a�͔]�����̔��������Q�`�U�{���߂�
�@�A�@���A�a���t�ǂ̈���
�@�B�@���A�a���Ԗ��ǂ̈���
�@�C�@�o���𑝂₷
�@ �D �@�x���̈���
�@�������H��ɍ����ƁA���ꂾ���œ����̕ǂ������Ȃ�Ƃ����������ʂ�����܂��B�Z���Ԍ��������������ł��ӊO�Ɉ����e���������Ĕ]�����ɂ����炩�̉e��������̂����m��܂���B
�@�����I�Ɍ���A���A�a���҂���ɂ͒ʏ�̂Q�`�U�{�̔������i���ʂ�n��ő����ȍ�������܂��j�Ŕ]������������ƌ����Ă��܂��̂ŁA���炩�Ɉ��e��������ƍl�����܂��B��ɓ����d����i�߂邽�߂ł��傤���A�������������ƂŃR���X�e���[���⌌�t�̃T���T����Ȃǂ̗l�X�Ȗʂɉe��������悤�ł��B�ȒP�Ɍ����ƁA�u���t�͌ł܂�₷���Ȃ�v�@�u���ǂ͔j��₷���Ȃ�v�@�悤�Ȋ����ł��B
�@���A�a�̍����ǂ����łɐi�s���Ă���ꍇ�͘b�����G�ɂȂ�܂��B
�Ⴆ�Γ��A�a���t�ǂŐt�@�\���������Ă��鎞�ɔ]�������N�����ƁA�]�ւ̖t���֗^���鈫�e�����\�z�����ꍇ�́A�[���ȗʂ��g���܂���B
�@�]�[�ǂ̏ꍇ�ɁA���t���T���T���ɂ��悤�Ƃ���Ɗ��o�����N�����ĖԖ��ǂ���C�Ɉ������Ă��܂����Ƃ����肦�܂��B�}�q�͌y���Ȃ������ǎ��������̂ł́A���Â��ėǂ������̂�����Ȃ��Ȃ�܂��B���A�a���҂���͖Ԗ��Ɍ��炸�o�����N�����₷���X��������܂�����A���̈�ۂƂ��Ă͂�����u���t���T���T���ɂ���v�n���̖�́A��ʂ̐l�����T�d�Ɏg�������������Ǝv���܂��B�ł��A���̖ʂɊւ��Ă͏[���Ɍ�������Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ��̈�Ë@�ւł��g���Ă݂Ĕ���������Ƃ����̂�����ł��B
�@�܂��A�]�����̔����͂悭�x�����N�����܂����A���A�a�̃R���g���[���������Ɣx���̎��Ð��т������Ȃ�X��������܂��B
�ԈႢ�₷���Ǐ�ɂ���
�@����̕���͗\�h�Ƒ����Ώ���ڕW�Ƃ��Ă��܂��̂ŁA���Ⴂ���₷���Ǐ��������܂��B�]�����ɂ͂��܂��܂ȏǏ���܂����A���ɂƖ�ჁA�ӎ���Q�ƃV�r���A�}�ɂ��т��������Ĉӎ����Ȃ��A�Ƃ����悤�ɏǏd�Ȃ�ΒN�ł��������^���܂����A�Ⴆ�u����ɂ���Ȃ�����]�����ł͂Ȃ��v�A�u�ӎ���������������]�������v�Ƃ͌����܂���B
�@�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ȏǏ�ɂ��ẮA�����̉\�����l���đΉ�����悤�ɂ��ĉ������B
�@ �ӎ��ɂ���
�@�@�@�K���ӎ������������Ȃ�킯�ł͂Ȃ�
�@�@�@���i�Ƃ̗l�q�̈Ⴂ�Ŕ��f���ׂ����Ƃ�����
�@�@�@���������ɒ���
�@�����͈̔͂��L���ꍇ�ɂ́A���悻���炩�̈ӎ��̏�Q���o�邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�ł��A���\�傫�Ȕ]�o���ł��ӎ����͂����肵�Ă��邱�Ƃ͒���������܂���B�������N�������]�̏ꏊ�Əo���̗ʂȂǂ̏����ɂ��܂��B�ӎ����͂����肵�Ă��邩��}�q�͂��肻�������Ǘl�q���݂悤�Ƃ͍l���Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B
�@���ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��A�u���������̐l��A��čs���܂��B�v�ƌ����āA�ǂ������������̂Ō���������]�o���������Ƃ����P�[�X�ł��B���i�Ɨl�q�������ŁA���Ƒ������������Ă���Ƃ���v���Ă����Ƃ������Ƃ����Ȃ��炸����܂��B�܂��A�\��Č������ł��Ȃ��悤�ȕ��̏ꍇ�́A�f�f���x��Ă��܂����Ƃ�����܂��B�@�������������Ă���Ƒ����̎��Ɍ��������܂���A���̈Ӗ��ł����܂Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B
�A �����ɂ���
�@�@�@�}�ɋN���������ɂ͑������^����
�@�@�@���ɂ̒��x�͌y�����Ƃ�����
�@�@�@���i�Ƃ̗l�q�̈Ⴂ�Ŕ��f���ׂ����Ƃ�����
�@�@�@�]�[�ǂł͓��ɂ��Ȃ����Ƃ�����
�@���������ɂ��}�ɏo����A�N�������o����]�o�����^��Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŒP�Ȃ铪�ɂ������ƕ��邱�Ƃ��قƂ�ǂł����A�}�ɋN�������ꍇ�͊m�F���]�܂�܂��B�������ӎ���Q��}�q���Ƃ��Ȃ��Ă���A���Ћ~�}�Ԃ��ĂԂׂ��ł��B
�@�o���̏ꍇ�ɂ͓��ɂ��o�邱�Ƃ������悤�ł����A��ł͂���܂���B���������ɂ���͂��̃N�������o���̊��҂���ł����ɂ�i���Ȃ��l�������܂��B�w�����ɂ��ƌ����Ă���ꂽ����A�������K�N�K�N���邾���Ƃ������҂�����o���������Ƃ�����܂��B�]�o���̏ꍇ�ɂ́A�����d���A���ׂ��H���炢�̒��x�ł��邱�Ƃ͏��Ȃ�����܂���B���̏ꍇ�A��Ⴢ��Ȃ���Α����ɔ������邽�߂ɂ͊�F�����������A�Ȃ�ƂȂ��l�q�������ƈႤ�Ƃ��������ɗ��邵���Ȃ����Ƃ�����܂��B
�@�܂��]�[�ǁi���ǂ��l�܂�ق��̑����j�ł́A���ɂ�i���Ȃ����Ƃ����ʂł��̂ŁA���ɂ��Ȃ����疃Ⴢ������Ă��~�}�Ԃ͌ĂȂ��Ă������낤�Ɗ��Ⴂ���Ȃ��ʼn������B�d���x�͌��������ł͂킩��܂���B


�i���j�Â������d�ǂ̔]�[�ǁ@�@�@�@�@�@�i�E�j���������ꎞ�I�ȓ���
�B ��Ⴢɂ���
�@�@�@���E�ǂ��炩�Е��̃}�q�͑����̃p�^�[��
�@�@�@�ŏ��͌y�����Ƃ�����
�@�}�q�i���Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�Ɓj�́A�]�̂ǂ̕���������邩�ł��悻�͈̔͂����܂�܂����A���E�ǂ��炩�Е��̃}�q�̏ꍇ�́A�]�������܂��l���Ȃ��Ƃ����܂���B����̏����Ɍy�������̂ɂ����Ȃ邩�A�t�ɂ����̂悤�ɏ����邱�Ƃ�����܂��B
�@��Ⴢ��}�ɏo�Ĉӎ��������낤�Ƃ��Ă���A���ɂ��������Ƃ����悤�ɏd�Ȃ�ΒN�ł��~�}�Ԃ��ĂԂł��傤���A�����Ȗ�Ⴢœ��ɂȂǂ̑��̏Ǐ��Ȃ����͐f�f�ɋ�J���邱�Ƃ�����܂��B
�@��Ⴢ̃p�^�[����
����������܂��̂�
�}�Ɏ����܂��B
�}�q���}�̍�����^��
�̂悤�Ȃ�A�����ɑ���
�p�^�[���ł��B�ł�����
�ɏo�����瑲���łȂ���
�͌����܂���B
�@��̋ؓ��̃}�q�������Ǐ�ł��B�ڂ��J���ɂ����Ȃ�A�O���Е�����������A������������ƐO�̕Е����琅���R���Ȃǂ���A�����ڂŋC�����܂����瑲���ł͂Ȃ����Ƌ^����l�������̂ł����A�ʏ�͊炾���̃}�q�̎��͒P���Ȑ_�o�̃}�q�ł��邱�Ƃ������悤�ł��B�������A�a�@�ƘA�������͂����ق�������ł��B
�C ���}�C�ɂ���
�@�@�@�͂��߂Ẵ��}�C����͌�����
�@�@�@�����ƈႤ����̂Ƃ���������
�@�@�@�ʐ^�̋@�B��B����ɂ��������K�v
�@�͂��߂ă��}�C�̔�����N�������Ƃ��́A�O�̂��ߔ]�̌����������ق��������Ǝv���܂��B���}�C�͂قƂ�ǂ̏ꍇ�͌����s���ŁA�����ŕ��鑲�����ᇂȂǂ̂悤�Ȉُ�͂܂�ł��B
�@�]�����Ń��}�C���o�邱�Ƃ́A����قǑ����͂���܂��A�]�̉��̂ق��ɏ����ȑ������N�������ꍇ�́A���}�C�����ǏȂ����Ƃ�����܂��B���ɏ����ȑ����̏ꍇ�ɂ́A�Ȃ��Ȃ��ʐ^�ł�����܂���B���a�@�ɓ��@����Ăǂꂾ�����ׂĂ�����Ȃ������̂ɁA������Ǝv���Ĕ]�̎ʐ^���B��@�B��ウ����]�[�ǂƕ��������Ƃ�����܂��B�����������̐f�f�Ɋւ��ẮA�ǂ���҂��ǂ��@�B�̂ق�������ɂȂ邩������܂���B
�@�b�s���B���Ă��炤�ꍇ�́A�ʏ���u�X���C�X�v�Ƃ����ݒ�����������Ă��炤�Ƃ͂����肷�邱�Ƃ�����܂��B���}�C�ɊW����ꏊ�͍��Ɉ͂܂�Ă���̂ŁA�ʏ�̃X���C�X�ł͎ʂ�ɂ����̂ł��B���}�C�Ɋւ��ẮA�\�Ȃ�l�q�h�ŁA��������\�̗ǂ��@�B�ŎB���Ă�������ق���������������܂���B
�@�@�@�i�E�j�@���W���̐}
�@���}�C�ɊW����̂͐}�̐^���牺�̂�����ŁA
���̌`�ɉe������ĉ摜�����ɂ����A�����ȍ[�ǂ͎�
��Ȃ����Ƃ�����܂��B
�D����ׂ�ɂ����A���ݍ��݂���������
�@�@�@�}�ɏo�����t�̏�Q�͑������^����
�@�@�@���t�ƈ��ݍ��݂͓����Ɉ������₷��
�@�@�@�뚋�ɒ���
�@�̂ǂ�A��A���̓�������Ⴢɂ���Ĕ��������ɂ����Ȃ�ꍇ�ƁA���t�̂����ԈႢ�������Ȃ�A�Ӗ��̂킩��Ȃ����Ƃ�����ׂ�ȂǁA�]�̏ꏊ�ɂ���ĈႢ������܂����A�]�����Řb���ɂ����Ȃ邱�Ƃ͂悭����܂��B�܂��A���̂悤�ȏꍇ�͂��̂����ݍ��ޓ���ɂ���Q���łĂ��邱�Ƃ������悤�ł��B���̂��߂ɐH�ו����C���̂ق��ɋz������ł��܂��Ĕx�����N�������Ƃ�����܂��B
�E�ڂ̌���������������
�@�@�@��̓����Ɉُ킪����A�]���_�o�ُ̈�̂��Ƃ�����
�@�@�@������Ĕ��f
�@�@�@�����Ɉُ킪�Ȃ���A�����͊�̒��ُ̈�
�@�ڂ̌������́A���͂��������̂��A�ڂ̓������������������Ȃ����̂��ɂ���āA���悻�̌���������ł��܂����A�Ǐ�����t�ŕ\�����ɂ������ɂ͐f�f�ɍ��邱�Ƃ�����܂��B
�@�����ȊO�̗��R�A�Ⴆ�Γ��A�a���_�o��Q�Ŗڂ����ؓ��̖�Ⴢ��N����A������d�Ɍ�����悤�ɂȂ銳�҂���͑����̂ł����A�ߋ��ɔ]�������N���������Ƃ�����ꍇ�ɂ́A�]�����ɂ��̂��_�o��Q�ɂ��̂�����ʂ��ɂ������ƂɂȂ�܂��B�������Ƒ��̕����u�}�ɕ�����d�Ɍ����o�����B�v�ƌ����āA�ڂ̓����������牺�̐}�̂悤�ɂȂ��Ă����ꍇ�͖ڂ̋ؓ��Ƀ}�q�����邱�ƂɂȂ�܂��B���Ƃ��ƎΎ��̌X����������̏ꍇ�́A�ڂ����ۂɓ������Ă����Ȃ��ƕ���܂���B
�@�@�@�@�@�u�E�����ĉ������B�v�@�@�@�@�@�u�������ĉ������B�v
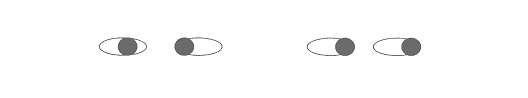
�@�@�@�@�@�����������������ƂɋC�Â���܂����H
�@��̂悤�Ȗ��炩�Ȗڂ̓����ُ̈킪�Ȃ��Ă��A���͔����ȓ����̏�Q�����邱�Ƃ�����܂��B�ł��A�Ꭹ�ُ̂̈�œ�d�Ɍ����邱�Ƃ̂ق��������悤�ł��B�Ⴆ�ΖԖ��͂�����Ԗ��̂ނ��݂Ȃǂł��B���������đ����̏ꍇ�́A�����Ɉُ킪�Ȃ������Ȏ��͊�Ȃ̖��A���������炩�ɂ���������Γ��Ȃ�]�O�Ȃ̖�肩�H�ƍl���đ��k���ׂ��ł��B�i���߂Ă�����Ȃ��ق�������ł����B�j
�@�����̏ꏊ�ɂ���ẮA����i������͈́j�������Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���삪�����Ȃ��Ă��A���̌�����ς���Ό����Ȃ��킯�ł͂���܂���B���ɂ͓��̌����߂���̂Ɋ���Ă��܂��āA�{�l�͎���̏�Q�ɋC�Â��Ă��Ȃ��l�������܂��B�Ǐ}�ɋN����C�����Ǝv���܂����A�������i�K�I�ɐi�s����ꍇ������悤�ł��B
�@���A�a���Ԗ��ǂŌ����Ȃ��Ȃ����Ƃ���v���Ă�����A�����������ƕ��邱�Ƃ����肦�܂��B�����ƖԖ��ǂƗ����������Ă���ꍇ�ɂ́A�{���ɐf�f������Ȃ�܂��B
�F���т�A���o�ُ̈�
�@�@�@�Е��̃V�r���͑����̃p�^�[��
�@�@�@����A�����̐�͐_�o��Q�̃p�^�[��
�@�V�r���ɂ͂��낢�날��܂��B�r���r������A���o������Ȃ��A�t�ɉߕq�ɂȂ��Ă���A�܂��͓����Ȃ��Ȃǂ͂��ׂăV�r���ƕ\������܂�����A�ǂ������Ǐ�Ȃ̂����͂�����`���Ȃ���Έ�҂ɂ͈Ӗ����`���܂���B�����̏ꏊ�ɂ���āA�V�r�����ꏊ���ς�܂��B�����ő����͉̂��̐}�̍��̂悤�ɕЕ��̎葫�ɂł�p�^�[���ł��B
�@���A�a���_�o��Q�ł����o���ɂԂ��Ȃ�����A�ɂ��Ȃ����肵�܂����A�T�^�I�ȏꍇ�͐}�̉E���̂悤�Ɏ��A����ɋN����܂��̂ŁA��قǂ̏ꏊ�ƈႤ���Ƃ������肢��������Ǝv���܂��B
�G�������
�@������]�����ŋN���邱�Ƃ�����܂��B�������͑��̕a�C�ł��N����܂�����A�}�ɋN�������ꍇ�́A���������ł͉������������f�ł��܂���B�����������̌�́A�ʏ�ł��ӎ������ǂ�̂Ɏ��Ԃ�������܂�����A�����ɂ��ӎ���Q�Ȃ̂�����ɂ������Ƃ�����܂��B
�@�������]�̕\�ʂɋ߂������ɋN����ƁA���������N�����₷���ƌo���㌾���Ă��܂��B�������̌����͒��ׂɂ����A���g�����ɋ�����ჂƂ��������̂ő����ɈႢ�Ȃ��Ǝv�������҂��A��̃P�K�̌��ǂ��x��ďo�����������������Ƃ������Ƃ�����܂����B
�@������ɂ���A���������N��������~�}�Ԃ��Ă�ʼn������B
��ʓI�Ȕ]�����̎��Ö@
�@�]�����ً͋}��v����a�C�ł��B����̑����ɔ����ł����ꍇ�ɂ͐��Ƃ̂���a�@�ɍs�����Ƃ������߂��܂��B���܂������}�q���y���čςމ\�������邩��ł��B�������A�a�@�ɂ���Ă͉ߌ��Ȏ��Â̂��߂Ɏ��S�����������č������Ƃ�����܂��̂ŁA�����������̖ʂ͂���܂��B�a�@�̎��Ð��тɂ��Ď厡��Ɋm�F�����ق���������������܂���B
�@�o���̎��ɂ́A��p�ʼn��P�������߂�Ȃ�Ύ�p�������ɂȂ�܂��B�ǂ�ȏo���ł���p�Ŏ�����킯�ł͂���܂���B�o���̏ꏊ�ƗʂŐ��т��\�z����܂��̂ŁA�Ⴆ�Ύ�p���Ă��a�������邱�Ƃ��\�z�����ꍇ�ɂ́A�o�����̂ɂ͓��Ɏ��Â����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���ǂ��l�܂鑲���i�[�ǁj�Ȃ�A��ł̎��Â������ɂȂ�܂��B
�@���n�r���͔M�ӂƌo���̂��闝�w�Ö@�m������Ƃ���ŁA����̑������疈������������邱�Ƃ��K�v�ł��B�Ǐ��肵����A���x�͕��@���w�����Ă�����āA����ő����邱�Ƃ��厖�ł��B�F�{���͔M�ӂ̂���搶�B�̓w�͂ŁA���̖ʂ̘A�g�����܂���������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�������炸�A�V�����@�E�B�@�_���X�v
�]�����̗\�h�͉\��
�@�\�h�͉\�ł��B�]�����͉��炩�̌��ǂ��c���a�C�ł�����A������N�����A�ǂ�ȗǂ��a�@�ɍs���Ă����ÂɌ��E������܂��B�\�Ȍ���\�h���ׂ����Ǝv���܂��B�ŋ߂͗\�h�Ɋւ��鎎���������Ȍ`�ł���Ă��܂��B��������R���g���[������قnj��ʂ�����悤�ł��B
�@�R���X�e���[���̎��Â̊�ɏ]���R���g���[������
�@�R���X�e���[���������l�́A���A�a�̕��Ɠ����悤�ɔ]�������N�����m���������̂ł����A�R���X�e���[���̎��ÂŔ�������Ȃ茸�炷���Ƃ��ł��܂��B��ɏ]���A���悻�Q�`�R���͔�������点�邾�낤�ƌ����Ă��܂��B���t���̃R���X�e���[����������ƁA���ǂ̕ǂ̒��ł��낭�ė₷�����������肷��ƌ����Ă��܂��̂ŁA�ȒP�Ɍ����u���u���ɂȂ������ǂ���v�ɂ���Ƃ����悤�ȈӖ��Ō��ʂ�����̂ł��傤�B
�A�g���`�P����ڈ��Ɍ����l���R���g���[��
�@�����̃R���g���[���Ŕ]�������ǂꂭ�炢���点�邩�ɂ��Ă����v���łĂ��܂��B�C�M���X�̌����ł͂g���`�P�����P�������������ŁA�]�����͂P�����炢���邾�낤�Ƃ������ʂł����B���̌����́A���{�̂悤�ɓO��I�Ȏ��Â����Ȃ��ł̌��ʂł����̂ŁA�O�ꂷ������ƌ��ʂ����邩������܂���B
�B �����̎��Â̊�ɏ]���Č������R���g���[��
�@�����̎��Â����ʂ�����܂��B�Ⴆ�A�g���������i���̌����j���T�����邾���ŁA�����̊댯�x���R������Ƃ������v������܂��B�܂��A��قǂ̃C�M���X�̌����ł͎��k�������i��̌����j���P�O������ƁA�]�����͂Q������Ƃ������ʂł����B������Ή�����قǗǂ��Ƃ͌����܂��A���ɓ��A�a�������Ă�����������ɂƂ��āA�����͏d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@��̎�ނɂ���Ă���̌��ʂ̈Ⴂ������悤�ł����A�����邱�Ƃ��ł��厖���Ǝv���܂��B�������A��C�ɉ�����Ɛ��т��ǂ��Ȃ��悤�ł��B
�C �얞�����邱��
�D �^�o�R���z��Ȃ�����
�E ���������͂ɍT���邱��
�@�S�g�I�ȉe�����l����ƁA�ی��w������҂��������Ƃ͂��ׂė\�h���ʂ�����A�����Ă������ق����ǂ��Ǝv���܂��B���Ƀ^�o�R���z���ƁA�����̎��Ì��ʂ�ł��������炢���͂Ɍ��ǂ����߂܂��̂ŁA�։�����ɕK�v�ł��B
�F���ǂ̌�������
�@��]�ɓ����Ă������ǂ̑����⌌�ǂ̕ǂ̌����́A�G�R�[�Ƃ����@�B�ŊȒP�ɕ���܂��B�������ɍׂ��������������ꍇ�́A�������Ă��镔�����g����A���ǂ̃o�C�p�X�����Ȃǂ̎��Â��������Ƃ�����܂��B�@�]�h�b�N�Ŕ]���ǂɓ���ᎂ����������ꍇ���j���h�~�ł��邩������܂���B����ᎂɋl�ߕ����߂���A�N���b�v���͂��肷�邱�Ƃɂ���ăN�������o�����\�h�ł��܂��B�@�����͓���Ȏ��Âł�����A���̕���Ɋ��ꂽ�]�O�ȂƑ��k���Ȃ��Ƃ����܂���B
�]�����̗\�h��ɂ���
�@�]�o����\�h�����́A�ʏ�͎~���܂ł͂���܂���B�~�����ʂ̂����܂͂���܂����A�]�o���Ɋւ��Ă͗\�h���ʂ��͂����肵�Ă��Ȃ��悤�ł��B���������āA������R���X�e���[���A�����̎��Â����i�ɂ��Ċώ@���邱�Ƃ��o���̗\�h�ɂȂ�܂��B
�@����ɑ��āA���ǂ��l�܂�̂�h����́A�]�[�ǂ�\�h������ʂ����Ȃ肠��܂��B������l�ƈ��܂Ȃ������l���ׂ����v�������āA���l�̂ق��������̔��ǂ����Ȃ��X��������܂��B
�@�����t�@�����i���i�����[�t�@�����A�A���t�@�����Ȃǁj�A�`�N���s�W���i���i���\�[�p�[�A�p�i���W���A�`�N�s�����A�p�`���i�Ȃǁj�A�V���X�^�]�[���i���i���v���^�[���A�V���X�e�[�g�Ȃǁj�A�A�X�s�����i���i���o�C�A�X�s�����A�j�`�A�X�s�����A�o�t�@�����Ȃǁj�N���s�h�O�����i���i���v���r�b�N�X�j�ȂǁA��������̎�ނ�����A�e�X�̓K�������悻���܂��Ă��܂��B
�@�������A��̕���p�łǂ����ɏo��������A�̑�����������l�����܂��B�Ԗ��ǂ̏�Ԃ������l�Ȃǂ́A���o�����N�����Ȃ�����p�ɂɌ������Ȃ���łȂ��ƊȒP�ɂ͎g���܂���B���t������������Ȃǂ��A���̊��҂�����p�ɂɂ��ׂ���������܂���B�܂��A�����̖�Ŕ]�����̂��ׂĂ�\�h�ł���킯�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̗\�h��͂Ȃ�
�@�Ԗ��ǂ̂��߂Ɏ~���܂��g���Ă���l���]�[�ǂɂȂ������ɍĔ��\�h���ǂ����ׂ����ɂ��Ă͓��v���͂�����łĂ��܂���̂ŁA���Ƃł����m�ɓ�������l�����܂���B���ʂ̗\�h�����������̂���ʓI�ł����A�Ԗ��ǂ��������邱�Ƃ͂���܂��B��ȂƑ��k���Ȃ���A�ʏ���T�d�ɂ��ׂ����ƍl���Ă��܂��B
�@���N�H�i�ŗ\�h���ʂ�������̂͂ǂꂩ�A�c�O�Ȃ��璲�ׂ邱�Ƃ��ł��܂���B�����Ђ͐�`�����ɍI���ł��̂ŁA�m�荇���Ɋ��߂�ꂽ����Ƃ����ĊȒP�ɐM�����܂��A�厡��Ƒ��k���Ȃ��猈�߂��ق��������Ǝv���܂��B