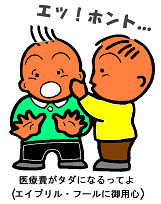新年度が始まりました。
4月から病院で支払う薬代や診察料が少し変わります。大きな変化はないと思いますが、支払額が減る人もいるかもしれません。 診療代、薬代は国が決めています。景気が悪いのに薬の値段だけ高くても仕方ないので、価格を激安セールなみに下げて欲しいと思いますが、製薬業界の力のせいでしょうか、そのような改定はされないようです。
診療代が少し下がっても、健康保険料や介護保険料が高くなるので、実質の支出は残念ながら減りそうにありません。
オンライン診療報酬請求
レセプトのことを解説します。通信に関する専門知識がない私は、実際に通信して怖く感じます。不安に思う理由を述べます。
この文章は、事故が起こらないかぎり患者さんには関係のない話ですが、事故が起こると実害が生じる可能性があるので、知っておくべきと思います。
レセプト
「レセプト」は、診療内容の報告書です。
病院が診療内容を報告する際、健康保険事務所にレセプトを提出します。レセプトには患者さんの保険証の情報、病名、処方内容、処置内容などが記入されています。
以前は書類で提出する病院が多かったのですが、国の命令でコンピューターを使うようになっています。文書や表を電算化して、暗号のような内容に変えています。
オンライン請求
「オンライン請求」は、電話線や光ケーブルを使ってインターネットを介してレセプトを報告することです。既に大きな病院にはオンライン請求が義務化されています。
IT技術の利用は効率化を生みます。いちいち人間が点検していては人件費がかかりますし、点検の間違いも覚悟しないといけません。文書をコンピューターに入れれば、自動的に判定できますので、費用や時間の節約につながります。
無駄な治療内容を指摘することも可能になります。実際にオンラインで報告すると、瞬時に間違いを指摘してくれます。
電算化
作業効率を上げ、人件費を減らすために、情報の電子化は必要と思います。
ただし、コンピューターの業者に数百万〜数千万円の支払いが必要になるのに、それを医療機関に払わせるのは無茶です。国が規則を変えるたびに業者が管理料を得る仕組みなので、役人と業者に不透明な関係ができやすく、患者さんの利益にならないことに保険料が使われる傾向が生じます。
予算を節約するためには、システムごと国が提供したほうが簡単です。膨大な予算を使って事業を展開し、特定の業者を優遇し、国民を欺く手法と言われても仕方ありません。
業者の利益を損なう心配より、社会全体の利益を重視し、効率化を目指して欲しいと思います。
情報管理の責任
病院は患者さんの住所、年齢や病気の内容などの個人情報を守る責任がありますが、大勢の患者さんの情報を守りきるのは簡単ではありません。
通信の際には専用の通信回線を使いますが、専門知識を持っていれば盲点をついて情報を盗むことは可能です。もしも健康食品やサプリメント業者、生命保険業者に情報が漏れたら大きな利益を生みますので、情報の売り買いが発生するかも知れません。
通信を受ける側の保険事務所の管理体制は相当しっかりできているはずですが、人がやることですから完璧とは思えません。罰則の程度は知れていますので、内部に情報を売る人がいてもおかしくありません。
病院側も万全ということはありえません。 病院職員はコンピューターに関しては素人同然ですから、こっそり機器や通信ケーブルに仕掛けをされても、おそらく気づきません。業者が細工をした場合は、まず発見できないでしょう。
システムの脆弱性、技術的問題
実際にオンライン請求をしてみると、回線の点検の都合か通信が混雑する時期があるためか、通信できないまま時間切れになることがあります。
空港や銀行のような極めて綿密に作られたシステムでも時々不具合を起こしますが、便利なシステムには同時に脆弱な面もありますので、通信に技術的問題が何もないとは言えません。
公的な事業に携わる業者には、本来なら一度でも障害を起こしたならば撤退、廃業を念頭に入れるくらいの厳しさが望まれます。その意味で、既に現在の業者(本来なら支払い基金自身も)は事業に携わる資格がないとも思えますが、他の業者が事実上参入できないことや、そもそも民間の管理業者の参入を要すること自体が問題なのかも知れません。
ハッカーの脅威
グーグルという会社や、アメリカ政府のサイトに中国政府のハッカーが侵入した事件がありましたので、管理がしっかりしているはずのサイトにさえ侵入は可能だということが判ります。
その気になれば中国企業が日本人の健康状態を把握し、商品を売りつけることも可能でしょう。もしくは特殊な情報(ウイルス)を混入させて、データを改変することも可能です。
外国企業を日本の法律で処罰することは難しいので、ハッカー行為がないと考えるほうが無理かも知れません。
不正に情報を入手、変換するハッカーが存在する限り、情報管理に関しては何ごとも杞憂ということはありません。想像もできない手段で盗む人がいると考えておくべきです。
当院の情報保護
このような状況では、情報伝達の際は可能な限り通信ケーブルを使わず、外部と物理的に遮断しておくのが原則です。
現在、当院はコンピューターを使う中では最も安全と思える方法を採っています。ハッカー相手に完璧ということはありえませんが、少なくとも通信回線からの侵入はできません。
業者を介していませんので、管理業者が情報を売る心配もありません。大きな病院は、ほとんどが業者によってコンピューターが管理されていますので、その社員が全て高いモラルを持っていなければ情報漏れは防げません。
これらの面で、当院は大きな病院よりは安全です。国の方針には従わざるをえませんが、今の方針のままでは患者さんの情報管理、保護に関して危うい面もあることを皆さんも知っておくべきと思います。
平成22年4月30日 診療所便りより 橋本泰嘉