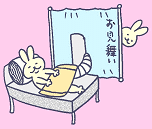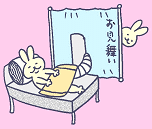脳梗塞の治療成績
脳卒中の発作を起こされたら、救急車で脳卒中センターに行くのが原則です。テレビCMで「サッカーと同じでスピードが大事。」と言っているように、卒中の中の「脳血栓」と言われる病気の場合に、うまくいくと血管を再開通させることができるからです。
ただし血管の再開通は遅れると効果を期待できませんし、副作用のために出血して亡くなる可能性もあります。専門的治療の成績を調べた統計が発表されました[JAMA.2011;305(4)373-380]。
統計は外国のものです。治療成績は専門施設のほうが一般病院より良い傾向はありましたが、大きな差はないという意外な結果でした。死亡率は専門施設10.1%、一般病院12.5%と記載されています。
この数字は随分高いので、日本で統計をとれば結果が違うかも知れません。施設による2.4%の差をどう考えるべきかも解りません。熊本県では一般に麻痺の程度に関しては専門施設、特にリハビリが得意な病院のほうが断然軽くて済む印象を受けます。
脳梗塞
脳梗塞は脳の血管が詰まる病気です。例えば心臓にできた血液の塊りが脳の血管に流れ込んで血管を詰まらせた場合は、脳塞栓という言い方をします。これに対して、動脈硬化した脳の血管の一部がその場所で詰まる場合を脳血栓と言います。 血栓溶解治療で回復が望めるようになったのは、この脳血栓のほうです。
私は脳血栓で患者さんを無くした経験はほとんどありません。それは詰まる血管が細めで、障害が少なくて済むからです。脳のよほど大事な場所に血栓を起こさないかぎり、命に別状はないと言えるほどです。
対して脳塞栓では大きな血管が詰まって脳の半分くらいが一気に障害を受けることもありますので、脳浮腫、心不全、肺炎、胃潰瘍などが合併して生存率が下がります。それでも死亡率はせいぜい5~7%程度、治療薬が少なかった研修医時代を除けば脳塞栓でも患者さんが亡くなることは少なく、救急車で来る脳梗塞患者全体の死亡率は2%程度、「もはや脳梗塞は命に関わる病気ではない」という印象さえ持てるほどでした。
発表にある10%も亡くなるような成績は、人種の違いによるものか、腎不全などの基礎疾患、治療法の違いのせいかも知れません。外国では軽い麻痺の場合は病院に行かない人も多いはずなので、対象者の重症度が違うのかも知れません。でも、もし治療法の問題なら、救命率の高い治療法にするのが道義的と考えます。
治療方針の違い
脳塞栓は重大な後遺症を残し、助かっても寝たきりという事態も珍しくありません。 私は死亡率を低くできたものの、結果として後遺症の強い患者さんを多数残すことになり、患者さんや家族に負担をかけた点を反省せざるをえません。
いっぽう、脳血栓の場合、命さえ助かれば麻痺が重くていいとも言えません。少しでも後遺症が軽いほうが良いと考えるのが自然で、血栓溶解治療が試みられるのはそのためです。 治療には施設によって微妙な方針の違いがあります。その違いは主に再開通を試みるか否かの判断と、代謝や循環の管理方法によるものです。以前は独断が過ぎる傾向があったので、血栓溶解剤の使用には基準が設けられるようになりました。 各施設で治療成績を公表し、患者や家族に選択させるべきと思います。
もしかすると、血栓塞栓という病態の違いより、病巣の位置とサイズに従って治療法を選ぶべきかもしれないと私は考えます。少なくとも生命予後はそれによって改善します。 血栓と塞栓の鑑別が微妙な例も多いので、得られる治療効果が非常に大きくなければ鑑別する意味がありません。 治療成績に従うべきだと思います。 ただし、これは個人的な考えで、一般的な意見ではありません。様々な考え方がありますから、理屈にこだわらず実際の成績で判断すべきと思うだけです。
血栓溶解は劇的に症状が改善する治療法です。しかし、①患者本人の意志を確認しづらい、②家族の同意だけで治療することの道義的問題、③100%出血しない保証は不可能、④出血すれば医原性に症状を悪化させたことに他ならない、⑤脳血栓では本来死ぬことは稀であり、一か八かの治療をする必然性はない、このような問題を含みます。
極端な例で言うと、意識が戻った患者さんが、 「あなたは本来なら麻痺で済んだのに、治療によって出血し、寝たきりになった。これは家族と相談した結果だから仕方ない。」と、医者に言われて本当に納得できるかということですが、これはやはり治療成績で考えるべきでしょう。血栓溶解療法で死亡率も麻痺も半分になるといった圧倒的な成績が証明されれば、治療に道義的な裏づけができます。 日本から好成績を発表して欲しいと期待しています。
脳梗塞の予防
この研究結果の解釈の仕方は色々あります。高い死亡率を考えると検討に値しないのかもしれませんし、やはり大きな病院のほうが少し良いとも言えますし、発作を起こせば同じで予防が大事とも言えます。少なくとも病院による大きな差はなさそうですから、専門施設に行けば絶対に大丈夫、予防は面倒だからする必要はないという理解はしないほうが良いでしょう。
実際の予防法は、血液をサラサラにする薬を飲むこと、コレステロールや血圧の治療をすることなどですが、様々な困難を伴います。抗凝固剤、抗血小板剤と言われる薬は使っていても再発する場合があり、逆に効きすぎて吐血されることもあります。近年、クロピドグレルやダビガトランといった薬が開発されましたが、副作用なしに100%予防できる薬はありません。
血圧やコレステロールの治療薬を処方しても、塩分の制限をできずコントロールが悪い人、薬を止める人が少なくありません。さしせまった危機感がないと予防薬を飲むこと、食事療法運動療法の意義を感じて努力を続けることは難しくなるようです。
外科的な卒中予防
MRIなどで血管を写した結果、首や脳の血管に細い部分や動脈瘤が見つかることがあります。高齢者の場合は、異常がないことが少ないくらいです。 動脈瘤があっても治療できればクモ膜下出血を予防できます。血管の細い部分を削ったり、別な血管からバイパスを持って来れば脳血栓の予防ができます。もちろん外科的な治療は必ず成功するとは限りませんから、慎重に方法を選ばないといけません。
心房細動という不整脈は脳塞栓を起こしやすい病気ですが、外科的な治療や電極を使って発生を止められる可能性もあります。薬もありますから外科的治療が必須とは言えませんが、適応を選べば効果的な治療です。
麻痺が出てからでは遅いと思います。確かにサッカーも卒中もスピードが大事ですが、発症してからのスピードを重視するより、やはり発症しないことのほうが大事です。
平成23年4月 診療所便りより (2011.04.30up)