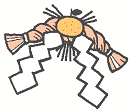認知症対策の難しさ
(認知症対策の根拠)
認知症に関する対策の報道をよく目にします。高齢化が進むと認知症の方も増えるはずなので当然です。既に政府が専門家を呼んで検討会を開いたり、施策を発表したりしています。雑誌やテレビでも最新の研究結果が紹介されます。見ていると、認知症など直ぐ克服されそうな気になります。
でも、実際に何をやればどれくらい有効なのかは曖昧です。欧米の対策を評価した発表があります(Ann Intern Med.22 Oct2013 Review)。
その結論では、
①認知症の評価は簡単、
②薬やリハビリなどに大きな効果があるとは言い難い、
③認知訓練の効果も限られている、といった残念な現状でした。
認知症は簡単な施策では対処できず、手ごわいということでしょう。研究には期待しますが、今の技術では治療より介護を中心に考えるべきと、個人的には思います。
(効果の判定法)
認知症に関しては、効果をどのように判定するかが簡単ではありません。風邪のように治癒する病気ではないからです。論文で‘効果がない’と判定しても、実は少し進行を遅らせる効果があり、その意味を見逃した可能性はあります。
評価の仕方が難しいので、効果有り無しと明快に分けることは難しいはずです。この論文の結果も、鵜呑みにはできません。
高齢者の中で認知症の方の割合が減る、もしくは軽度に留まる、寿命が延びる、一人あたりの医療費や介護費用が減少するなど、明確な指標でないと効果を評価できませんが、改善を証明した信頼できる統計はないと思います。おそらく誰も、何も解っていないのが現状ではないでしょうか。
(認知症の薬)
現在の認知症の薬は進行の抑制効果を狙っていますから、効いている人でも徐々に病状が進行し、多くのケースで5年くらい経つと使う使わないの差がなくなります。したがって、5年を経て続ける場合には、誰でも納得できる充分な根拠が必要なはずです。 治験結果(開発時のデータ)に従うなら、本来は初期のアルツハイマー型認知症に対象を絞るべきですが、乱用に近い形で処方される傾向を感じます。‘初期’の基準が曖昧ですし、効果判定も恣意性を排除できていません。
アルツハイマー型認知症の薬は非常に値段が高く、処方が増えれば保険財政に負担をかけます。処方の根拠には敏感であることが望まれます。いったん処方された場合、処方の意味が不明な方について中止を進言しても、家族の了解を得ることはほとんどありません。多くの家族は薬に意味があろうとなかろうと、放置はしたくないといった心情的理由で処方を希望されます。同じような心情もしくは誤解は、医者の側にも存在するかもしれません。薬の中止は、イメージ的には患者を見捨てる行為に近いからです。
薬の投与期間については、適正な処方を促す目的で一定の記載が望ましいと思います。長期的効果が明らかな新薬が出れば話は別ですが、現在の薬で効果を証明するのは困難と思います。
(画像診断)
認知症の診断で困るのが、頭部MRIやCTなどの画像診断の仕方です。全く検査しないと水頭症などの病気を見逃しますが、意味なく検査を繰り返しても保険財政の面で問題です。
現状の画像診断で初期の認知症を確実に診断することは難しいので、様々な新しい検査法が研究されています。多くは放射性物質を注入して、脳の機能を評価する方法になります。でも放射線を浴びる問題もあり、画像診断への過剰な期待、偏重には注意が必要です。治癒を目指せる薬が開発されていない段階で、放射性物質を体内に注射して診断する意義があるのか微妙かも知れません。
この点についても、今後治療の効果が証明されてくれば話は変ります。早期診断の意味がある治療法が出てくれば、費用的に許されるなら積極的に検査すべきとなるでしょう。
(施策と効果)
もし、この論文の通り診断評価が簡単で、薬剤や訓練の効果が限られているのなら、言い方は悪いですが、現在の日本の方針では効果を期待できないという疑念が生じます。
日本では大まかに言うと、拠点病院の専門家の指示で地域の診療所などが治療する方針で進みつつありますが、予算を使う施策ですから根拠は必要です。施策によって何がどの程度改善したかを明らかにすべきです。
一般に専門家は、自分たちによる管理の必要性を強調する傾向があります。原発や外交、防衛といった大きな問題から買い物に至るまでそうです。でも専門家がミスリード~間違うのは珍しくありません。その方針の必要性、効果が実証されるなら実施すべきですが、施策が無効で無駄に終わる可能性も考えつつ、効果を実証しながら方針を選ぶべきと思います。
診療所便り 平成26年1月分より(2014.01.31up)