���A�a���_�o��Q�Œm���Ă����������� �@���{�@��
�@�_�o��Q�̌����╪�ނɂ��Ă̊w��I�Șb�́A���X�̖{����q�ɍڂ��Ă��܂��̂ŁA�����ŕ����Ă�������(�����Ȃ�܂����j�B�����ł́A�w��I�ȏ��Ԃ��痣��āA�Ǐ玄�B���ǂ̂悤�ɍl����ׂ������܂Ƃ߂܂��B�@
�P�D�葫�̂��т�
�Q�D�ڂ̓����ُ̈�
�R�D�����Ȃǂُ̈�
�S�D�ؓ��ُ̈�
�T�D����
�P�D�葫�̂��т�i���тꂪ�o����ǂ̂悤�ɐf�f���Ă��邩�j
�u���т�v����ǂ̂悤�ɓ��A�a���_�o��Q��f�f���Ă��邩��������܂��B���������ǂ̂悤�ɐf�f���Ă��邩�́A���҂���ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��������Ƃ���Ȃ����Ǝv���邩������܂��A�a�C�𗝉����邽�߂ƁA��f�△�ʂȌ�������g����邽�߂ɂ͑厖�ł��B
�@���A�a���҂���̎葫�����т��A�܂��͒ɂ��Ƃ����Ǐ��i����ꂽ���ɂ́A���A�a�������_�o�̏�Q�ł͂Ȃ����ƍl���܂��B���̏ꍇ�A�����_�o�Ƃ͎葫�Ȃǔ]���痣�ꂽ�����̐_�o���Ӗ����܂��B���̕a�C�̊��҂���͂ƂĂ��������܂��B�������A�f�f�͊ȒP�ɂ͂����܂���B����ƈ�ʈ�̈Ⴂ�́A���M�������ĊԈ���Ă��邩�s�����ɊԈ���Ă��邩�̈Ⴂ�����������肵�܂��B�������́A�܂��Ǐ�̓��������Ă��邩�����������܂��B
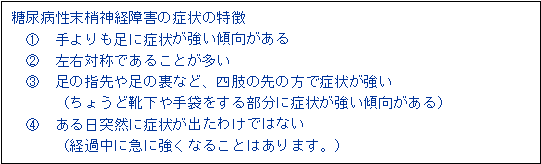
�ȉ��̂悤�ȕʂȕa�C�ł��A���т��ɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B�����̕a�C�ɂ͂���Ȃ�̓���������܂��̂ŁA��ʂ����ŎQ�l�ɂȂ�܂��B
�_�o�̈����ɂ��ꍇ�̏Ǐ�̓���
�@�@���E����ꏊ�̕肪����
�A�@����∳���ŕω�����
��̂��т�́u�荪�Ǐnj�Q�v�Ƃ����a�C����N���邱�Ƃ�����܂��B���̕a�C�͎��̕t�߂Ő_�o�Ɉ��������邽�߂ɋN����a�C�ł����A���w�𒆐S�ɕЎ�ɂ��т��ɂ݂��o�邱�Ƃ������ł��B���ɂ͎����z���āA�r�̂�����܂ŏd�����o��ɂ݂������邱�Ƃ�����A�܂����E�����ɋN���邱�Ƃ����肦�܂�����A�Ǐ��ŋ�ʂł��Ȃ����Ƃ�����܂��B�����������Ԃ�������˂���悤�ȓ���������Ƃ��ɒɂ݂��ω�����悤�Ȃ�A�����������W�����ǏȂƋ^�����Ƃ��ł��܂��B
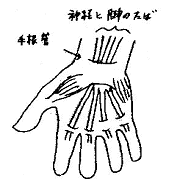
��@�荪�ǂ̐}�@
�@�@�荪�ǂƂ����ꏊ�́A���ɂ����F��_�o�����ɂȂ��Ă��܂��B
�Ғ��Nj���ǁi�������イ���傤�������傤�j��Ғł̕ό`���ߏǁA�z�Ō�c�x�э����ǁi�������イ�������������傤�j�Ƃ����a�C���悭����a�C�ł��B��Ɏ�⍘�̂�����Ŕw����x�сA�ŊԔ��_�o�̂ǂ������������Ă��܂��a�C�ł��B�ʏ�̓V�r������ɂ݂��A���E�ǂ��炩�ɋ����o�邱�Ƃ������̂ł����A���E�Ώ̂ɏo��ꍇ������܂��̂ŁA���̎��͐f�f������Ȃ�܂��B�Ғł̒ŊԔw���j�A�̏ꍇ�������ł��B��������⑫����L������X�����肷��e�X�g���������l�Ă���Ă��܂��āA�����ʼn����Ǐ�̕ω����������ꍇ�͈����ɂ��Ǐ���^�������ɂȂ�܂��B�O�����݂ɂȂ邾���ŏǏy���Ȃ�l�����܂��B��̎w�̐e�w���ɕ���Ⴢꂪ�o�邱�Ƃ�����܂��B��̍��̈ꕔ�Ɉ���������ꍇ�������ŁA�f�f�����ŎQ�l�ɂȂ�܂��B
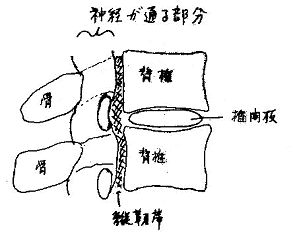
�}�͔w���������猩���Ƃ���ł��B�Ґ��͐}�Ɏ����Ғō��̌��Ԃ�ʂ��Ă��܂��B���A�ŊԔA�x�т̂����ꂩ���ό`����A�Ґ���Ґ�����}�����ꂵ���_�o���������Ă��܂��܂��B
���ǂ̕a�C�ɂ��ɂ݂�V�r���̓���
�畆�̐F�������Ȃ邱�Ƃ�����
�Е��̑����₽���Ȃ邱�Ƃ�����
���������ɒɂ��Ȃ�
���ǂ��ׂ��Ȃ��Č��t�̗��ꂪ�s���������́A�ɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B�y���ꍇ�́A���邢�����₵�т��Ɗ�����ꍇ������܂��B���A�a���҂���́A���łɓ����d���������Č��ǂ��ׂ��Ȃ��Ă���\���������̂ŁA���̂悤�ȕa�C�ɂ����邱�Ƃ������Ȃ�܂��B�Ђǂ��ꍇ�́A���̐F�������Ȃ葫���₽���Ȃ��āA���E�̑��̐F�≷�x���Ⴄ���Ƃ�A���s�ɂȂ��Ă���f�f�����ꍇ������܂��B
�T�^��͕��������ɑ����ɂ��Ȃ��āA�x�߂ΏǏ���Ƃ����u�Ԍ����͂����v�Ƃ����Ǐo�܂��B�܂��ɂ݂͋ؓ��ɂɋ߂��炵���\�ʂ�G���Ă��Ǐω����ɂ����X��������悤�Ɏv���܂��B
�]��������̂��т�̓���
���̏Ǐ���Ƃ��Ȃ����Ƃ�����
�}�ɋN���邱�Ƃ�����
�Б��ɋN���邱�Ƃ�����
�傫�Ȕ]�����ł͒ʏ�Ȃ甼�g�ɖ�Ⴢ��o����A�ӎ��������낤�Ƃ����肵�܂����A�������ďꏊ�������Ă���ꍇ�͊��o�ُ̈킾�����Ǐ�ł��邱�Ƃ�����܂��B����ł������������āA���N������}�ɏǏo�Ă����Ƃ������悤�ɋ}�ɋN����X�������邱�ƁA�ʏ�͗����̎葫�ɂ�����ɏǏo�Ȃ����ƁA�����ł��ؗ͂̒ቺ�����т�Ɠ��������ɏo�邱�Ƃ��������ƁA����ׂ�ɂ����A���݂��݂����ɂ����Ȃǂ̑��̏Ǐ���������Ƃ�����Ȃǂł��B�����̓���������Γ��A�a����̏Ǐ�ł͂Ȃ��\���������Ȃ�܂��B
����
�@�]�̂b�s�A�A�]�̂l�q�h�A�B�Ғł̃����g�Q���A�C�Ґ��̂l�q�h�A
�D�@�_�o�`�����x�A�E�@�U���o�A�F�@���ǃG�R�[�@�G���t�����Ȃ�
�]�������^���鎞�ɂ͑��₩�ɔ]�̎ʐ^���B��ׂ��ł��B�_�o���Ȃ̐���ł��f�@�����ł͌��\��f���܂�����A������҂�肢���@�B��T�����ق��������ꍇ������܂��B���A�a���҂ł̓����g�Q���ɂ��CT�����A�ŏ�����MRI�����������ق����ǂ�����ꍇ�������Ɗ����܂����A������͈����͂���܂���B
��⍘�Ő_�o���������Ă���\����������A�����g�Q���ō��̕ό`���m�F���ׂ��Ǝv���܂��B�_�o�̐f�@�Ŏg���e�X�g�Ə����������Ă���ΐf�f�����m���������Ȃ�܂��BMRI�������d�v�ł��B���ɍ��ɕs���R�ȍ��܂�A�j�ꂽ�悤�ȏ���������Ƃ��͊����������Ă��肷�邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ����Ƃ��m�F�����ق�������ł��B
�_�o�̓�������������u�_�o�`�����x�v�Ƃ��������ŁA������Ɍ������ُ킪�o�Ă�Ύ荪�Ǐnj�Q�̉\���������Ȃ�A���Ɏl���ɍ��E�����Ȃ��ُ킪�o�Ă���Γ��A�a�������_�o��Q�̉\���������Ȃ�܂��B
�����i�s�A�m�̒����ȂǂɎg���A�������Ɖ����łĐU��������j���g���āA�U���ɑ��銴�o�̋���������邱�Ƃ��d�v�ł��B�����̐U���ɑ��Ĕ��ɓ݂��Ȃ��Ă���Ζ����_�o�̏�Q������ƍl�����܂��B
���̍b�̕����Ō��ǂ������Ă��镔���Ɏ�ĂĂ݂āA�ǂ������G���悤�Ȃ瑽���͌������ǍD�ƍl���Ă����Ǝv���܂��B����ɂ����ꍇ�͑��Ǝ�̌����̍����ׂĂ݂邩�A���ڃG�R�[�Ō��ǂ̂܂����������邱�Ƃ��ł��܂��B���łɓ��A�a���_�o��Q��������Ɍ��ǂ̕ǂ��N���邱�Ƃ��悭����܂��B���̏ꍇ�͐f�@�����łǂ��炪�Ǐ�̒��S���Ă邱�Ƃ͓���̂ŁA�G�R�[�Ȃǂ̌������K�v�Ǝv���܂��B
�܂������ł͂���܂��A���A�a�Ɠ����悤�ɑS�g�̕a�C����N���邵�т�łȂ����Ƃ��m�F���Ȃ���Ȃ�܂���B�A���R�[�����̈ꕔ��A����̋����̒��łł������悤�ȏǏo�܂��B������b�̒��Ŋm�F���Ă��܂��B�n���̗L�����A�S�g�I�ȕa�C��T�邽�߂ɂ܂��K�v�Ǝv���܂��B
�Q. �ڂ̓����ُ̈�
�@���A�a���_�o��Q���ڂ����_�o�ɋN���邱�Ƃ��悭����܂��B�Ǐ�́A���̂����d�Ɍ�����A�܂Ԃ���������A�ڂ̉��������ɂނȂǂł��B�ˑR�N���邱�Ƃ������̂ŁA�F������ɐS�z����܂����A���R�Ɍy�����Ă������Ƃ��قƂ�ǂł��B�������]�[�ǂ⓮��ᎂȂǂ̕a�C�łȂ����Ƃ��m�F���邱�Ƃ͑厖�ł��B�������܂Ƃ߂܂��B
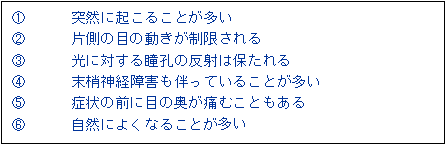
�}�@�ڂ̓����͋ؓ��Œ��߂��Ă���
�ڂ͋ؓ����������邱�ƂŌ�����ς��Ă��܂��B�ڂ̋ؓ��ɐL�т�_�o�ׂ͍��Ē������߂ɁA���̐_�o�ɐ�삯�ďǏo�₷����ۂ�����܂��B���ǂ⌌���̕s���A�����ł悭��Ⴢ��A��������ɖڂ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
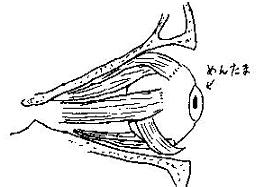
�R. �����Ȃǂُ̈�i�����_�o�j
�����߂���_�o�Ɉُ킪�N����ƁA�����オ�����Ƃ��Ɍ������グ�锽�����キ�Ȃ��āA��������݂������Ȃ邱�Ƃ�����܂��B�ɒ[�ȗ�ł́A�܂��������ĂȂ��Ȃ�l�������܂��B�����̒��߂����Ă���_�o�́A�����_�o�Ƃ����܂��B�l�X�ȏǏ�A�ُ킪����܂��̂ł܂Ƃ߂܂��B�قƂ�lj��ł�����Ƃ��������ł��B
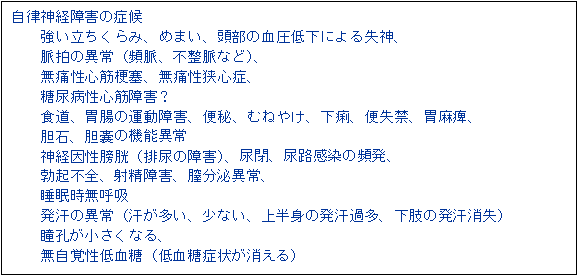
�S�D���A�a���؈ޏk��
�H�ȍ����ǂł����A���ǂ⌌���s���������Ƃ���ؓ��̏�Q���ł邱�Ƃ�����܂��B�Ǐ�͂P�`�Q�N�Ōy�����܂����A�Ԉ֎q���������炭�������Ƃ�����܂��B�����ł͓��������������܂��B
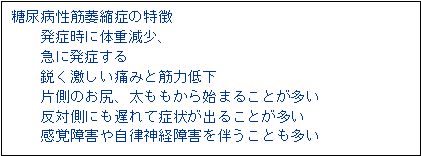
�T�D����
�@�����ł͖�̖��O���Љ�܂��B��͏Ǐo�����ɂ͗���ɂȂ�܂����A����p���܂������Ȃ��S���Ɋm���Ɍ������̂͂���܂���B�u��������߂Ίm���Ɉꔭ�ŗǂ��Ȃ�܂���B�v�ƌ���ꂽ��A�����������������Ă���Ǝv���ėǂ��ł��傤�B���ł悭�Ȃ�͂��͂Ȃ��A���{�I�ɂ͓��A�a�̎��Â�ʓ|���炸�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�ł��A�������R���g���[�����������Ŗ���g���A���Ɍ������Ƃ��m���ɂ���܂��B
����܂ŏǏȂ������l���}�ɑ��̒ɂ݂œ����Ȃ��Ȃ�A�ڂ���d�Ɍ�����Ȃǂ̏Ǐ�ɋ����A�Y�܂�܂����A���̂܂܂����ƍ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����Ă����Ǝv���܂��B���ǂ��c�邱�Ƃ�����܂����A�قƂ�ǂ͋C�ɂȂ�Ȃ����x�Ɏ��܂�܂��B�l�X�Ȗ���܂��B
�@�{���^�����@�@�@�@�Q�T�`�P�O�O�~���O����
�@���L�\�j���@�@�@�@�U�O�`�P�W�O�~���O����
�@���[�r�b�N�@�@�@�@�P�O�`�P�T�~���O����
�@�{���^��������@�P�Q�D�T�`�T�O�~���O����
�����͒ɂݎ~�߂ŁA��������̎�ނ�����܂��B���ʂ������ĕ֗��ł����A����p�Ƃ��Ĉݒ�ᇂȂǂ��N�������Ƃ�����̂����_�ł��B���ݖ�ȊO�ɍ���i���K���������j������܂��B���ݖ�ɔ�ׂ�A�݂ւ̕��S���y�����ʂ��m���ł����A���������Ȃ�₷���X���͂���܂��B
�@�e�O���g�[�� �Q�O�O�`�U�O�O�~���O����
�@�g���v�^�m�[�� �P�O�`�R�O�~���O����
�@���{�g���[�� �O�D�T�`�U�~���O����
�@���L�V�`�[�� �P�O�O�`�R�O�O�~���O����
�����̖�͐_�o�̓��������艻�������p������A���Ƀe�O���g�[���͒ɂ݂ɂ͗ǂ������܂��B�������A�n����s�����Ȃǂ̏d������p�����肦�܂��B�Ǐs�����₢�炢����Ă��鎞��A���̒u���ꂪ�Ȃ��Ƃ����Ǐ�̎��́A�g���v�^�m�[���A���{�g���[�����L���ł��B�Ǐy�����́A���L�V�`�[�������ʂ�����܂��B
�@�L�l�_�b�N�P�T�O�~��
�@���`�R�o�[���P�D�T�~���O����
�@�v���^�[���Q�O�O�~���O����
�@�I�p�������R�O�}�C�N���O����
���v���T�`�P�O�}�C�N���O����
�����͐_�o�זE�̒��Ɉُ�ȕ��������܂�̂�h����p��A�_�o�ւ̌��t�z�������邱�Ƃ��˂������ł��B���̑��ɂ���������̖���܂��B��������U�`�W���̊��҂���Ɍ��ʂ�����܂��B���тꓙ�͐��T�ԂŌy���Ȃ邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�A�̐F���ω������肵�܂����A�����o�����₷���X��������܂��B�l�i�����ɍ������̂����邱�Ƃ����_�ł��B
������������ꂽ��A��̖ړI�A�Ӗ������ׂāA����p�ɗp�S���Ȃ������ʼn������B���͖{������Ŗ�Ɋւ���{��ǂ�A�l�b�g���g���ďڂ������ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B