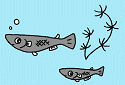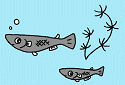心拍数と寿命の関係
脈拍が早い人は寿命が短いという話を聞きます。どなたかがテレビで言っているようです。動物を例に挙げ、一生の脈拍数は決まっているから、脈が遅いほうが長生きするという理屈です。寿命に関係する要因にはタバコや血圧、血糖などの個人差があるので一概には言えないような気がしますが、繰り返しテレビで言われると私もつい自分の脈を数えたくなります。脈拍と死亡率を検討したスウェーデンの論文が発表されました(JAMA.2011;306(239:2579-2587)。
長期間にわたって安静時の脈拍を記録した結果、脈拍数が年々増える傾向の人は、心臓病での死亡率が高いようです。この種の研究は以前から何度もされています。 狭心症や心不全などを有する人の場合、脈拍は多くないほうが良い傾向はあります。脈が速いと心臓に負荷をかけてしまう場合があるようです。
ただし健康な人でも脈拍を抑える必要があるとまでは言えないように思います。 脈拍を抑える薬は一般に心臓の力も抑えます。したがって心不全の人に使うと、病状を悪化させる危険性があります。カルベジロールという薬が代表的ですが、少ない量から徐々に増やす慎重さが必要です。心不全なら症状があるだろうから簡単に見分けが効くと思われるかもしれませんが、自覚症状が出るのは限られた場合だけです。したがって、安易な思い込みで使うと危険です。
脈拍が増えることは、もしかすると心不全の結果なのかも知れません。 衰えた心臓の機能を補充するために脈拍が増える反応が起こっているなら、頻脈が心臓病の原因ではなく、むしろ結果なのだということになります。 さらに、脈が速くなるホルモンが増えている場合も結構あります。バセドー病のように直ぐ測れるホルモンなら判定も容易ですが、微妙な試験を要するホルモン異常の場合は、原因の特定が難しい場合もあります。
健康人の脈拍と寿命に関しては、この論文や過去の研究結果からも、まだ結論には至っていないと思います。脈を抑えても、必ず寿命が延びる保障はありません。
現時点で非常に脈拍が早いことに気づいたら、心臓の機能に異常がないか、脈拍を早くするホルモンが出ていないかを確認されたほうが良いと思います。それには心臓エコーや血液検査が必要です。 心筋症など、脈拍の抑制が経過の改善を見込める病気があれば、コントロールすることも考えるべきです。 何も異常がなさそうな場合に、とりあえず脈拍を抑えるべきかどうか、その点についてはよく解りません。
診療所便り平成24年3月分より (2012.03.31up)