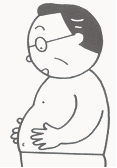メタボリックシンドローム
メタボリックシンドロームは、肥満、高血糖、高血圧、高脂血症などの異常をいくつか合併した状態を意味します。独立した病気ではありませんから、ちょっと分りにくいかもしれませんが、この状態が続くと各々は軽い異常でも動脈硬化が進むので、生活指導を受けて心臓病や血管の病気を予防して下さいという意味の病名です。曖昧な面があり、病気としての基準というべきものが明確ではありません。
いつの間にか企業健診、特定健診にもメタボリック症候群の基準が導入されるようになってきました。コレステロールの項目が総コレステロールからLDLコレステロールに変更されたので、検査値の正確さ(検査値が一定しにくい)や、以前のデータとの比較に多少の問題が出ています。健診のシステムにも様々な問題があります。
世界保健機構や内科学会が簡単な基準を作りましたが、まだ完成には時間がかかると思います。おなかの回り(およそへその高さでのウエスト)を測って内臓脂肪の具合を推定し、血圧や血糖の値を参考に、以前よりも軽い異常をとらえようと工夫されています。
診断基準を覚える必要はありません。大事なのは、肥満のうち特に内臓に脂肪がついた肥満では、軽い高血圧や高血糖、高脂血症が出やすいので、健康診断の判定で「生活に注意して経過観察」しか書かれていなくても、本当は生活態度の改善が必要であるということです。
高血圧、糖尿病、高脂血症は別個の病気ではありません。すべてホルモンなどで調節されて関係しあっています。各々の異常が軽い時でも動脈硬化のスピードは2倍にも3倍にもなり、やがては心臓病や血管の病気を起こしてしまいます。動脈硬化を進ませないためには、知恵と意欲が必要です。治療すれば病気を予防し、寿命を延ばすことができます。
15年位前に人間ドックを受けた人を調べたことがありますが、肥満や高血圧、高血糖、高脂血症などの結果が出ても、9割の人は治療を受けていませんでした。これではドックを受ける意味もありません。ドックを担当する医者に、もっと判定基準を見直し説明に力を入れて欲しいとお願いしましたが、その当時は医者たちも意味が分ってなかったので、私は変人扱いされてしまいました。
医者ですら専門を外れるとそうなのですから、まして一般の方に治療を勧めても理解してもらうのは難しかったわけです。今は自分が先進的な意見を持っていたのだと確信しています。お腹がぽっこり出た方、健診で血圧、血糖、高脂血症などに経過観察という項目があった方は、ぜひご相談下さい。
メタボリックシンドローム日本の基準
立位、軽く呼気の状態で、へその高さで腹囲を測定する
男性85センチ、女性90センチ以上が目安。
これに加えて、以下の3項目のうち2項目をみたす
中性脂肪 150以上またはHDLコレステロール40未満
血圧 収縮期130以上か 拡張期85以上
空腹時血糖 110以上
補足 診断基準は妥当か?
混乱されるかも知れませんが、診断基準は他にもあります。日本の基準は主として大阪大学の研究結果を根拠に作製されています。CTで測定した内臓脂肪面積100という数字が腹囲の基準に反映されています。
腹囲を測ろうという考えは、今までBMIを基準にして教育指導しても充分な効果があがらなかったことの反省に立っており、より簡単で具体的数字で患者さんに訴えかける意味があります。
でも実は当初から他の大学からは反論が出ています。数字の根拠になっている内臓脂肪面積100という数字は、統計で算出された推定値で、実際に患者さんの経過を追って確認した値ではありません。その値を基準にすることが正しいかについては異論があって当然です。
単純に考えても、本来内臓脂肪の影響を考えるなら脂肪の重量か体積から基準値を求めるべきで、面積で代用が可能だと多少は認められてはいますが、あくまで計算上の傾向のことで、そこからさらに基準を作るのは論理的に無理があります。基準は臨床的経過を直接調べて算出すべきです。
女性は皮下脂肪が多いことから男性よりも腹囲の数字が大きく設定されましたが、統計的に合わないかもしれないという指摘もあります。
本来とるべき方法は、腹囲を測って経過を追った統計をもとに死亡率や病気の発生率を求め、そこから基準を求めるやり方ですが、残念ながら推定した数字でさらに推定するという苦しい方法をとっています。腹囲を減らしたら寿命が伸びたという証拠がなければ、大掛かりな健診体制の変更は無意味になります。
私たちは細かい診断基準を気にする必要はありません。大事なことは、軽症の人に注意を促し病気を予防することと、統計を10年単位で取って本当の診断基準を確定することだと思います。
平成22年1月31日 診療所便りより