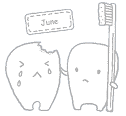蘇生処置の効果
病院外で人が倒れた時は、その場に居合わせた人が心臓マッサージをして助けるよう推奨されています。 蘇生の成功率、問題点を研究した日本の論文があります{JAMA.2013;309(3)257-266}}。
(蘇生の成功率)
後遺症なく蘇生が成功する率は、せいぜい数パーセントだそうです。低い数字ですが、現実を表していると思います。病院内での蘇生率は、原因や処置の担当者にもよりますが数十%に達しますから、処置の速さと正確さ、薬剤を使えるかどうかが重要であることが窺えます。
もし蘇生が成功したら、それ以上の人助けはありませんので、成功率が低いから蘇生の試みが無駄とは思えません。
(法的な問題点)
ただし蘇生行為には問題点もあります。例えば処置の手法に過ちがあり、処置によって状態が悪化したと疑われる場合は、せっかくの好意が仇となり犯罪者扱いされる危険性があります。
私は、心臓マッサージをしたことで患者さんを殺したと言われたことがあります。暴行事件で肋骨を骨折した瀕死の人を処置した結果で、検死官が状況を誤認したための無茶な話です。
救命を試みた人を保護する法律は未だにありませんので、もし訴訟になったら覚悟を決めないといけません。また、後遺症を残した場合も大きな問題です。重大な後遺症を残すと、本人と家族を非常に苦しめることになり、かえって迷惑という感情が生まれる可能性もあります。
(救命士による気道確保の問題)
統計では、救急隊が気管支にチューブを入れると救命率は下がるという結果も出ていました。予想通りの結果です。理由は多々あると思いますが、処置する間に搬送が遅れる影響が最も疑われます。
救急救命士法が始まって直ぐ、病院への到着が遅れることに気づきました。到着が遅れれば、本格的な蘇生手技の開始も遅れます。
気道確保の手技が上手いかどうかも関係します。気道確保は心臓マッサージをしながら数秒間で正確に施行しないと、止めを差すことに他なりません。マッサージによって揺れる患者さんを自分の胸や膝などで固定して処置しないといけないので、手技の習得も対象が動いていることを前提に考えないといけません。ところが、訓練は手術室などの安定した状況でされるので、実地に即していません。指導する麻酔科医も経験が充分でないことが多いはずです。
手技に熱中して、肝心のマッサージがおろそかになり搬送のタイミングが遅れれば、処置の成績は当然改善しません。懸命に救命を目指す隊員には気の毒ですが、努力が仇となった傾向は無視できません。
(救急救命士法)
搬送を急ぐように頼んでも、救急外来の医師の意見を無視して現場で気道確保されることがあります。法には「救命士は、医師の指示の下に気道を確保する。」という規定があるはずですが、この場合の医師は受け入れ病院の医師とは限定されていませんので、‘指導医’‘コントロール医’など他の医師の許可を取ることが許され、指示系統が曖昧になって実質は自由にやれます。
隊員にもプライドや使命感があるでしょうし、救急隊独自の内規があるのか解りませんが、人の命が絡むので規定も解釈も厳密にすべきです。
私が述べるまでもなく、病院への速やかな搬送は重要で、気道を確保しても血液循環が再開しなければ意味がありません。循環を再開させることを第一に考え、現場での処置に気をとられてマッサージを止めるような愚は絶対にしてはなりません。心臓マッサージしつつ搬送→状況に応じて気道確保という認識の徹底がなされていない現状がありました。
つまり救命士の認識の問題ではなく、法を策定した人間の規定能力が足りなかったことが現場の誤認を生じた理由かも知れません。隊員達は使命感を持って働いていましたので。
(搬送時間による違い)
わたし個人の意見で検証はされていませんが、救命の成功を目指す場合、現場と受け入れ病院との距離によって事情が違うと思います。
現場から病院まで数時間かかる場合は、搬送中に脳の低酸素状態が続きますので搬送を急ぐ理由が希薄になり、むしろ現場で処置すべき状況になります。
交通事情の良い市中の現場なら、渋滞の状況にもよりますが心臓マッサージを続けながら、簡易のマスクで呼吸の補助をしつつ搬送を急ぐほうが効果的であろうと思います。
低酸素状態がどれくらい続くと見込まれるか、隊員の手腕、患者さんの顎の形(顎が小さい人は、気道確保が難しい場合もあります)、推定される病気などによって、ある程度の対処法は決まるはずです。
最初から搬送時間によって規定を定めておけば、数万人の命が救えたのかもしれません。
(今後の方針)
戦場で指揮官が間違った戦法に固執する時、兵士はさぞ空しい心境だと想像します。救急外来も似たような状態でした。
隊員には気の毒な言い方ですが、救急隊から連絡を受けた段階で、「今の法律で、あの救急隊なら患者さんは助からないはずだ。」と‘敗戦’を予想できるような状況は改善を要します。隊員よりも患者さんに気の毒な現状の改善が優先されるからです。
法律を改正すれば救命率が数倍上がることも期待できますし、改正しなくとも救急隊と学会の取り決めで今回のデータを踏まえた行動規範を定めるだけでもいいかもしれません。
一般の人の認識の向上も有意義と思います。例えば、呼吸停止状態の人を見て、誰かを呼ぶ、心臓マッサージを開始するなどができるかできないかで救命率が変わってくるかも知れません。
今後の改善につなげうる統計が出たように思います。もし周りで人が倒れたら、心臓マッサージを続けること、病院への搬送を第一に考えることを覚えておいて下さい。
診療所便り 平成25年6月分より (2013.06.30up)