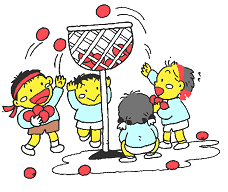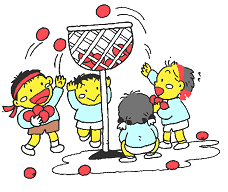電子タバコ
患者さんで電子タバコを購入された方がおられます。タバコのような煙(水蒸気)が発生し、良い匂いがするそうです。禁煙に有効かもしれません。 ただし外国製が多いようで、衛生検査が不十分なため発癌性物質を含む商品もあると報告されています(FDA News & Events Public Health focus 07/23/2009)。日本製もあるらしく、ニコチンを含むもの、含まないものなどがあり、禁煙効果が高いもの、危険性が低いものを選ぶこともできるかも知れません。
抗原と抗体価
「抗原、抗体」という言葉は、免疫学の用語です。
「免疫」・・・体を病原体やガンなどから守る防御機能
「抗原」・・・免疫の反応で退治されるもの
通常はウイルスなどの外敵
「抗体」・・・外敵である抗原にくっつく蛋白
「免疫グロブリン」という別名もある
抗体が抗原に反応すると、抗原が退治されやすくなると考えられています。
例えばインフルエンザワクチンは、ウイルスを処理して一部を取り出したものです。これを注射し、免疫細胞に反応させて「抗原」にしてもらおうと狙っているわけです。いわば擬似的な感染、弱い感染を起こしているとも言えます。
抗体ができれば、「免疫ができた」と言われる状態になりますが、抗体が少ないと外敵が生きのびることがあります。抗体の量や活性度を抗体価と表現し、充分な抗体価があれば感染への防御力があると考えていいことになります。
ワクチンを射てば必ず抗体価が上がるとは限りません。安全性を考えて副作用が出にくい量しか接種できませんので、人によっては充分な免疫反応が起こらず、抗体ができない場合もあります。そうすると感染の防御は難しくなります。また、同じウイルスでも型が変化する場合、抗体が抗原と微妙にしか反応しないのであれば、やはり感染してしまいます。
何度か接種すると反応が強まることもあります。3種混合ワクチンなどを2〜3回接種するのは、この理由によります。アジュバント(補助剤)を使うと、抗体ができやすい傾向はありますが、副作用が増える可能性もあります。抗体価は、繰り返しの免疫反応(つまり感染者との接触)があれば高いレベルを維持できますが、反応がないと徐々に低下していきます。
本当の感染があった場合は一般に免疫も強いけれど、ワクチンによる免疫はやや弱めで、抗体価もすぐ下がる傾向もあります。一般には「はしかに一度かかったら、二度とかからない。」と思われていました。でも、過去に感染した場合も、再度感染する例はあります。軽い風邪症状や部分的な発疹で済む場合もありますので、ご自分が二度目のはしかに罹ったことに気がつかない場合もあるかも知れません。不顕性感染という言い方をします。
症状が典型的でない場合は、血液中の抗体価が変化して初めて感染があったことが判る場合もあります。
ワクチンの効果と副作用
ワクチンの意味を考えていただくために、効果と副作用について簡単に述べます。ワクチンの専門家は効果しか述べない傾向があり、被害者団体は害しか述べません。日本のワクチン制度に不備があるはずですが、情報がなくて私にも全く理解できない部分があります。 面倒ですが接種の際には、各々の予防接種問診用紙の注意書きを確認して下さい。
ワクチンの性能 ワクチンを接種しても感染を100%防げないことは、既に皆さんご存知と思います。しかし、ワクチンが感染症の予防に有効な手段であることも事実で、害ばかりに注目して感染を蔓延させるのは愚かなことです。 対象とする病原体により、またワクチン製剤毎に性能の違いがあります。欧米の統計によれば、インフルエンザワクチンは感染率を数割減らすと思われますが、日本の信頼できるデータはないようです。周りにどれくらい感染者がいるか、直接ウイルスを浴びるかでも成績は違って来ます。国内にはワクチンを作る会社が数社あり、おそらく会社によっても微妙な性能の違いがあると思いますが、具体的な違いは判りません。
接種の仕方と効果 なかには「インフルエンザワクチンは全く無効だ。」と断言する人もいます。接種したのに感染したら、そう言いたくもなるでしょう。ましてや副作用が出た場合はなおさらです。1歳以下の子供に国内で使えるインフルエンザワクチンの量では有効性が証明されない(つまり効かない)という報告もあります。でもワクチンの注射量は国が決めており、医者の判断で調節することは許されていません。1歳以下へも、海外で推奨される量を使えば有効と考えられますが、それは違法行為になります。
効果の持続 はしかのワクチンは一般に効果が高いと評価されています。はしかだけに対するワクチンもありますが、子供の場合はMR(麻疹風疹)ワクチンで接種され、ある程度の年数は効果が残ります。ただし、感染予防率は100%ではありませんし、15年も過ぎると効果もなくなっていくでしょう。大学生くらいの年代では抗体価が低く、ワクチンの再接種が必要になる人も多くなります。有効と言われる麻疹ワクチンでさえそうですから、他のワクチンの多くは、もっと効果の持続期間が短い傾向があります。
国ごとの違い BCGの接種は全く必要ないという人もいます。接種しても大人の肺結核を予防できなかったという報告が海外であったからですが、衛生状態が違いますし外国と日本の製品は同じではないので、必ずしも外国のデータを信用できません。乳幼児の感染はかなり防ぐことができると言われていますが、もちろん100%ではありません。日本で使うのは独特の形の接種針(細かい針が並んだもの)ですが、あの器具も海外では少ないそうですので、微妙に効果に影響している可能性も否定できません。ほとんどのワクチンが、このように製品毎、国毎の違いやデータの信憑性の問題を抱えています。
ワクチンの副作用 副作用を強調すると、全くワクチンを受け付けない人も出てきます。栄養状態、衛生状態が常に良ければ感染症はかなり防げますが、常とは限りません。ワクチンの副作用に神経質になりすぎると、結局は感染症をコントロールできなくなります。
副作用にどのようなものがあるかご存知でしょうか? おたふく風邪のワクチンは毒性の弱いウイルスを感染させるタイプの製品ですから、やはり軽いおたふく風邪の症状が出る人もいます。弱毒型(生)のワクチンでは、一定の割合で原疾患の症状が出ます。その他は過敏症がほとんどですが、脳炎のような症状で後遺症を残すこともあります。頻度は非常に少ないのですが、命に関わる副作用もあり、その種類が多いので、とても口頭で説明するのは無理です。ぜひ、文書で確認すべきです。
MMRワクチン 国内のワクチンの失敗例として有名なのは、MMR(新三種混合)ワクチンです。開発中は期待の星のように説明されていましたが、やがて害が明らかになりました。 このワクチンは、何かの理由により三つの会社の製品を混ぜた形で作られました。この理由が科学的判断なのか製薬会社の希望が反映されたのかは不明です。 接種開始後に副作用の報告が相次いだため、製品を混ぜることを止め、やがて事実上の中止になりました。この間、少なくとも1800人以上の被害者が出たと報告されています。
副作用の予見 一般の人がワクチンの意味や危険性を理解するのは大変なことですが、医療機関でも害を公表されていない段階で予見するには相当な能力が必要になります。 当時MMRの害を予見して導入しなかった病院は判断能力を信頼できると考えますが、実際には接種した後に知った病院が多かったかも知れません。今後も新しいワクチンが開発されるでしょうが、効果と害の確認を怠ってはいけません。新型ワクチンをいかに急ぐと言っても、輸入したワクチンを検査無しで使うなど考えられません。
インフルエンザワクチンの準備 今回の2009年型インフルエンザの流行で始めて知ったことですが、ワクチンを国内でまかなう計画はなかったようです。輸入製品には多少の不安があります。ウイルスは世界中で流行するので、日本が輸入すれば不足する国が必ず出ます。危機管理の面からも、国内の生産ラインに余裕を持たせて増産が可能なように計画しておくべきではなかったかと思います。専門家や政府がどのように考えていたのか判りませんが、今回のウイルスへの対応を見る限り、強毒型のウイルスが出現したら、お手上げ状態になりそうです。
診療所便りより 平成21年9月30日 院長 橋本泰嘉