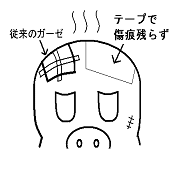外傷の治療法
最近は傷の治療法が変ってきました。怪我をして病院に行くと、治療法の変化に驚くかもしれません。 以前は消毒とガーゼ貼付が中心でしたが、今は消毒もガーゼも治癒を遅らせるという考え方が主流です。すり傷には、サランラップのようなテープをあてることもあります。バイキンの感染がなければテープで保護するほうが痕を残さないようです。
ただし、傷の状況にもよります。化膿する場合には昔ながらの治療をしないと危険です。傷の内部に病原体が溜まっている場合は、傷の中で菌が増えてしまいますので、体外に出すことが原則です。また、破傷風菌などの怖い菌がいる可能性が高い時には、菌に対する治療も忘れてはいけません。MRSAなどの耐性菌がいる場合は、患者さんの病態によっては傷を覆ってはいけないかも知れません。
感染をコントロールできる傷であることがテープを使う際の条件です。コントロールできるか解らない時には、とりあえず開放状態にして状態を把握するべきではないかと思います。
褥創がひとつの代表でしょう。最初は菌が溜まっていますから、洗うなどして菌を減らすことが必要です。いきなり覆ってしまうと感染をコントロールできず、傷が大きくなっていきます。消毒しても創は無菌状態にはできません。でも菌の勢いが落ちて感染がコントロールできたら、今度は肉が盛り上ってきますから、これを邪魔してはいけません。ガーゼの問題点は、交換する時に肉まで付いてしまうことです。
テープを当てる意味は、カサブタの代わりをさせて傷を保護し、内部で肉が盛り上ってくるのを邪魔しないようにしようというのが狙いです。専用のテープには目に見えない穴があるので、ある程度酸素を通しますし、ちょっと水がかかったくらいでは傷の中は汚れないように工夫されています。
ラップ治療が始まった頃、褥創の治療に使おうと提案したところ、「患者さんは食べ物ではありません!」「きっと家族から文句が出ますから止めて下さい。」と、婦長に怒られたことがあります。確かに、なじみのない治療法は反発を買いがちです。さすがに最近は皆が知るようになって来ましたので、文句を言う人は少ないと思いますが、旧来の治療法と織り交ぜながらやるべきだろうと考えています。
診療所便りより 平成19年10月 院長 橋本泰嘉