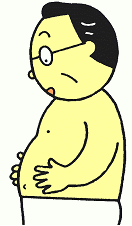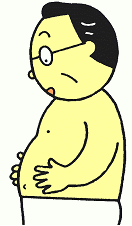
特定健診の問題点
院長 橋本泰嘉
平成20年4月から健康診断が変りました。市町村単位の「基本健診」はなくなり、40歳〜74歳の方については保険組合が特定健診という健康診断を管理します。
(目的) 生活習慣病を早期発見し、合併症を未然に防ぐ
(検査項目)コレステロール、血糖、中性脂肪、肝機能、
血圧、検尿、お腹周りの長さ等
(腎機能やレントゲンなどは検査項目から外され
ました。)
(対象) 40〜74歳の全員(国民健康保険)
(検査後) 異常があれば、保健指導を受けるように連絡
国民健康保険の加入者の方は市町村から、社会保険の加入者や家族の方は、会社の保険組合から葉書が来ます。検診の目標は、成人病(生活習慣病)、メタボリック症候群を放置させないことです。
したがって、検査の内容も今までの健診とは異なります。胸部レントゲンや心電図などは必ずしも検査されません。それらは別な健診を受ける必要があります。
今までの健康診断や人間ドックはひどいレベルでした。多額の予算をつぎ込めた時代の制度で、病気を予防する発想はなく、検査したものの、受ける人も検査する医者も意味が解らないままという有様でした。健診センターは商売に徹する傾向が強く、健診をしないほうが医療費を節約できた県の例があるなど、費用やモラルの面で多くの問題を抱えていました。
政府は生活習慣病を減らし、国民の健康を増進させ医療費を抑えようと考えているようです。病気になってから治療を始めても動脈硬化を予防できない、病気になってもらうと健康保険の財源が不足するという理屈です。
この健診には問題点もあります。
(問題点)
大きな予算を要する(保険財政を圧迫する)
強制的な姿勢
メタボリック症候群の疾患概念、基準の妥当性が不明確
治療中の検査として不向き
健診受診率、指導の受診率が不明
費用対効果の面で問題あり
癌検診については無視
健診事業が失敗した時の責任の所在が不明
データの秘密保持の責任が不明
予防の意図が制度に盛り込まれる点は評価すべきですが、強制的な姿勢や省が大きな影響力を維持しようという目論見も見えます.
また、判定基準や検査項目にも問題がありそうです。そもそもメタボリック症候群の判断基準が確立していませんので、将来基準が変った時に混乱するかもしれません。
例えば腹囲85センチが男性の判定基準項目ですが、基準を出した研究の対象は、まだ背が伸びていなかった時代の日本人でしたので、戦後の身長が伸びた世代では当然ながら数字が違ってきます。また、女性の基準の90センチも国際的な基準とは異なります。後で変えることが予想されるものを指標にするなど、戦略的に正しいとは思えません。
人間ドックや健診では、成人のおよそ4割の人が生活習慣病に相当しています。もうほとんど要医療の段階です。4割もいるなら、その対策こそが重要です。疾患概念や基準が不明確なメタボリック症候群を中心にするより、旧来の診断基準を使って指導方法のみシステム化し、腹囲などはその参考資料にするのが妥当な方針ではないかとも考えられます。
何かの病気を治療中の人が健診を受けた時もややこしくなります。副作用を見たい時は、貧血の有無や腎機能、CPKという蛋白を測定しないといけませんが、検査項目に入ってないので、嫌がる患者さんにもう一度血液検査を勧めないといけなくなります。尿蛋白陽性の人の腎機能とミネラルの値も重要ですが、これも検査項目に入っていませんので同様の問題が起こります。
また、予想されたことですが受診率が低いようです。検査に1000円出せと言われたら、私も受けたいと思うか分りません。そもそも通知を出したくらいでは人は動いてくれません。健診を受けなければ、病気になっても保険を使わせないくらいの強制力がないと動かない人もいます。でも強制は人道に反します。制度面の検討が不足していました。
この健診事業は予算をたくさん使った壮大な実験になり、データが集まれば、大きな論文が作られるでしょう。それを目標にしているのかも知れません。うまくいけば病気が減るはずですが、計画が単純で根拠が乏しく、昔の軍のエリートのような判断ミスを内在しているように思えます。既に財政が厳しい医療保険組合にとっては大きな費用負担になり、費用対効果の面では最初から結果は見えているような・・。
癌検診は別の機会に受けないといけなくなりますが、また別な予算が必要になり、手間も増えます。受診しない人も増えるのではないでしょうか?そうなると高血圧は減ったが癌の死亡者は増えたという結果になることもありえます。この点についての検討は不十分のように思います。
特定健診事業が保険財政を圧迫し、癌による死亡率を上げ、医療費の節約にも失敗した場合に、誰がどのように責任を取るのかも曖昧です。他の政策でもそうですが、責任の所在を明確にしないと、作りっぱなしの年金施設と同じく無駄のチェックが難しくなります。厚生省が責任を取るでしょうか?
データの管理には民間の業者が介入します。将来病気になりそうな人達の情報が簡単に集まります。罰則はたいしたものではありませんので情報の売り買いが行われたとしても、それについて皆さんが納得されているのでしょうか?
いろいろ問題点もありますが、意味もあります。当院も参加する予定です。
健診では腹の周りを測られます。恥ずかしいかも知れませんが、生活習慣病に対する意識がたかまり、病気を減らすきっかけになるかも知れません。
特定保健指導の問題点
健康診断で生活習慣に問題がある場合には、指導を受けるように規定されています。罰則めいた決まりも検討されていて、受診率が低い場合は補助金を減らされるようですので、保険料を上げられる口実となるかも知れません。
指導内容も、ある程度は決められています。厚生省が参考例として提示したパンフレットがありますので、それを参考に各施設が独自の資料を作って受診者に説明をします。指導時間をどの程度かけるべきかまで決められていますが、理解が早い人と遅い人では当然ながら差が生じてしまうかも知れません。
どのような指導が効果的か、実は明確ではありません。厚生省が今回の健診事業の根拠として挙げている成功例はあり、全国いろんな地域で試験的に健康教室などを開いて、その後も継続的に指導する研究がなされ、成果を挙げました。ただし、成功例は熱意のある保健婦さんなどが職務以上に頑張った地域ではないかと思います。「あの栄養士は、行かんと電話してうるさいから行こうかな。」、もしくは「行かないと区長が機嫌を悪くして、後で面倒だから行こう。」というような、社会的な強制力がはたらいたのではないかと想像します。事務的に「指導を受けること!」と言われても続かないはずです。
指導を受けた人の全員が自分の生き方や食事の仕方を分析し、対策を考えて実行に移せれば理想的ですが、頭で分っていても生き方は簡単に変らないのが現実です。「タバコは止めましょうね。」「毎日体操しましょうね。」と言われて従う人ばかりなら誰も苦労しません。仕事を制限して健康のために時間を割く余裕のない人もいるはずです。ある意味では無理に指導を受けに来てもらうことになりますので、義理人情の面からの圧力も必要でしょう。
今回の特定健診事業は、大きな予算を組んで導入される実験的なプロジェクトですが、医療費を抑制できるという根拠は乏しいものです。データ管理会社に役人が関与することなど、「特定業者のための特定健診」と言われかねない仕組みも見え隠れします。そうすると、ただ予算の規模を大きくしただけの結果で終わるとも予想されます。
当院では手紙での励ましを中心に、情報過多にも不足にもならないことと、気が緩まないようにしつこく、かといってイライラさせないよう努めます。目指すのは無病息災、もしくは一病あっても息災です。
診療所便り平成20年3月より(平成21年6月30日改定)