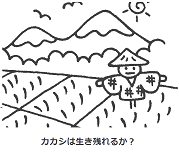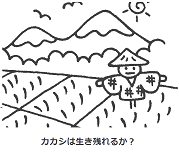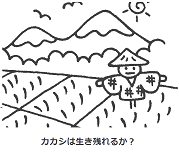今話題のTPPは、私にはよく理解できません。日本側は交渉に入ったばかりなので、もしかすると政府や学者も含め、誰も理解できていないのかも知れません。
TPPが実効し始めた場合、輸出関連企業の業績が良くなるいっぽうで、農業への悪影響と医療や保険の面で変化が予想されます。おそらくアメリカ側には郵便貯金などの資産管理をアメリカの金融会社に移行させる狙いがあるはずです。
健康保険にも米国の保険会社が参入を希望しているはずですから、社会保障システムごと米国流になるかもしれません。
何かの歯車が狂った場合に、広範囲に障害を及ぼすのはグローバル化が進んだ世界の特徴です。歯止めがあったほうが良いと思います。強欲の餌食にならないといいのですが・・・
携帯電話と脳腫瘍
携帯電話はかなりの電磁波を発生するそうです。それが脳腫瘍を発生させるのではないかという論文が過去に発表され、マスコミでも大きく取り上げられました。その後、“ケータイ”はさらに普及し、小学生や老人も持つようになっています。害はないのでしょうか?
デンマークで長いこと検討されている統計が発表されました(BMJ2011;343:bmj:d6387)。結論から言えば、現時点で脳腫瘍が増える明確な証拠は認められませんでした。短絡的に結論できませんが、使っている人からわざわざ逃げるほど怖がる必要はなかったようです。
最近の携帯電話は、電話というよりゲーム機、オーディオ機器、テレビのような性能を持っています。機能が増えたために面白みが増して、電話よりも長時間使う人が多くなったはずです。若い方は、暇さえあれば画面に見入って何か操作をしています。よく飽きないものだと感心するほどです。
使用時間が極端に長くなると、過去の統計は役に立たないかも知れません。1日数時間も若い頃から使い続けた影響は、もしかすると今後はっきりと統計でも証明されるかもしれません。耳に当てる電話機としての使い方ではなく、手に持つ場合の電磁波の浴び方は、また違うかも知れません。 それに今回のデンマークの統計も、子供達は対象に含まれていないようですので、子供に限定した場合は結果が違うかもしれません。
脳腫瘍以外の問題もありえます。 現在までの統計結果で解説することはできませんが、常識的に考えて小さな画面を数時間にわたって見つめ、動きもしないような生活が長く続いたら、健康的な状態とは言えないはずです。 精神面への影響や、視力が落ちる、学習時間が減る、運動が不足するなどの弊害が予想されます。携帯電話の使用時間と将来の生活習慣病、脳腫瘍以外の腫瘍や癌の発生、心臓病の罹患率などに、何か有意な所見が出てきても不思議ではありません。
とは申しても、子供達から携帯を取り上げようなどとしては、きっと大喧嘩になります。時間を制限するように言うだけでも、必ず一悶着あるでしょう。害が明らかになるまで、対処しようがないのかも知れません。
診療所便り平成23年12月分より (2011.12.30up)