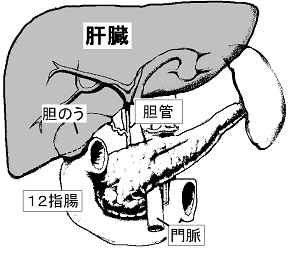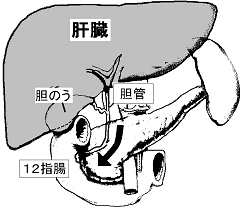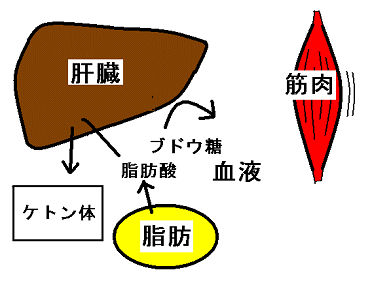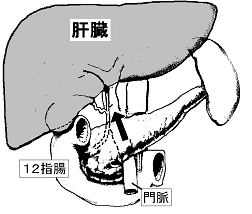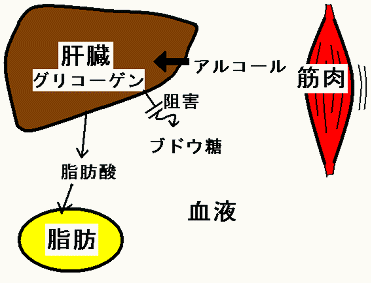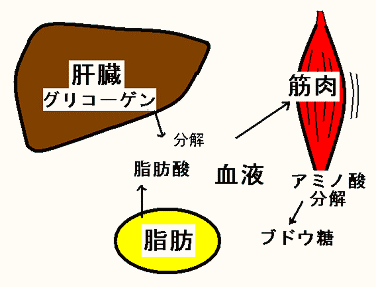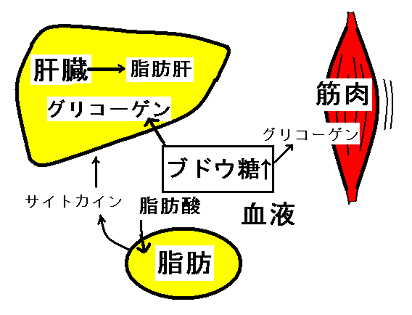�@�@�@�̑��Ɠ��A�a�̊W�@�@�@�@ �����Q�O�N�P�O���P�U��
���̕���ł͊̑��̓�����A�̑��a�����A�a�ɋy�ڂ��e��������܂��B�H���Ö@�Ɖ^���Ö@�́A���ǂ͊̑��Ƌؓ��̓����߂���̂��ڕW�ł��B
�P�E�̑��@
�̑��́A�������ł͂k���������AHepar�ȂǂƏ����܂��B�Ă������̃��o�[��o�h���͓����̊̑��ł��B�@�@
�̑��́A�ʏ�͉E���̂��獜�̓����Ɉʒu���Ă��܂��B�̑��̏�ɂ͎��b�≡�u�����ւ�����`�ɂȂ��Ă��܂��B�@�@
�̑��ɂ͕��ʂ̌��ǁi�̓����j����̌��t�ƕʂɁA�喬��������t���͂��܂��B���̖喬�𗬂�錌�t�͒�����̉h�{����A�X������̃C���X�����Ȃǂ��܂�ł��܂��B�h�{���ƃC���X�����Ȃǂ��̑��ɉ^��A�����ő�ӂ����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�̑�����͒_�`���o�Ă��܂��B�_�`�ɂ͒_�`�_�Ƃ��������ɖ𗧂t�ƁA�r�����r���Ƃ������F���F�f���܂܂�Ă��܂��B�r�����r���͌��t�����`������ł��镨���ł��B�_�`�͒_�X�ɗ��܂��āA�H���̎��ɒ_�ǂ�ʂ��ĂP�Q�w�����ɔr�o����܂��B�@�@
�_�`�������ǂ͒_�ǂƌ����܂��B�_�ǂ��≊�ǂȂǂő�ƁA�_�`�̒ʉߏ�Q���N�����ĉ��t���o�܂��B���t���o�Ȃ��Ă��A���t�����̊̋@�\�Ɉُ킪�o�邱�Ƃ�����܂��B�@
�Q�D�̑��̓����@
�̑��͑�ӂ̒��S�ƂȂ�厖�ȑ���ł��B�̑��̍u�`���Ă���Ɩ����Ȃ�قǕ��G�ȓ��������Ă��܂��B�����ł͎�ȓ����Ɍ����āA�T����������܂��̂ŁA����Ȃ��Ŋw�K���܂��傤�B�@�@�@
�`�D�����@�@�@
�z��������������͂�����܂��B�����ŕ��̏ꍇ�́u��Łv�A�̏ꍇ�́u��Ӂv�A�h�{���̏ꍇ�́u�E�E��Ӂv�Ȃǂƌ������͕ς�܂����A����������������Ƃł��B�@�@�@
�a�D�����@�@�@
�̑��́A�������邢���ۂ��ŁA���o�����������Ă��܂��B�̂����`���̑����ɂ͊̑����W���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@
�b�D����A�r���@�@�@�@
������_�`�́A�E�}�̖��i���j�̂悤�ɒ_�ǂƂ����ǂ�`���ďW�܂�A�_�X�ɗ��߂�ꂽ��ɁA�P�Q�w���ŐH�ו��ƍ������킳��܂��B�_�`�́A�����ɖ𗧂�p�ƁA�ŕ���r�������p�Əd�Ȃ��������������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�܂Ƃߕ���ς���ƈȉ��̂悤�Ȍ��������ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�P�D����@�@�@
�̂ɊQ�̂�����͉̂�����͂�����܂��B�v��Ȃ��Ȃ������̂͒_�`�Ȃǂƍ����Ĕr�����܂��B�@
�Q�D��̏����@�@�@
����������܂��B���̉�ō�p�ł��B��������ɗ���ł��A����������ƊQ���o�܂��B�Ⴆ�A�����~���܂����܂ł�������������A�ጌ���ɂȂ�܂��B���̑����Ŗ�����ď��߂Ė�Ƃ��Ďg���܂��B�@�@�@�@
�R�D�h�{���̏����@�@�@
������H�ׂĂ��A���̂܂܂ł͖��ɗ����܂���B�̑��́A���������ăG�l���M�[�����܂��B�`�����⎉�b�����l�ɏ����i��Ӂj���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�S�D�h�{�̒����^���N�@�@�@
�O���R�[�Q���͓������獇������A�������s���������ɕ�������܂��B����ɂ���āA���̗ʂ����ɕۂ���₷���Ƃ������ʂ�����܂��B�������A���b��`�������߂����悤�ɁA�̑��̒��ŕ������������āA���ꂼ�ꎉ�b��ؓ��̌`�Œ����܂��B�Q���Ԃɑς��邽�߂ɂ������͕K�v�ł��B�@�@�@�@�@
�T�D�`�������@�@�@
�̑��́A�Ⴆ�A���u�~�������܂��B�A���u�~�����Ȃ��ƁA���t�̔Z����ۂĂ܂���B��̕���݂��琅�������o���̂͌��t�ɔZ�������邩��ł��B�Z���ق��ɐ����������������p������܂��B���z���������A�A���u�~�����t���Ă��邩�猌�t�̒��ň��肵�ĉ^��܂��B�A���u�~�����Ȃ��ƌ��ǂ̕ǂɂ������Ă��܂��A�����Ȃ��ł��傤�B�@�@�@�@�@�@
�U�D�Z�x�����i�����A�����A�����̓����𑍍����āj�@�@�@�@
���t�̔Z���A���t�̒��x�A�����l�A�A�~�m�_�A���b�_�Z�x�̒��߁B�@�@�@�@�@�@�@�@
�����̋@�\�������Ȃ�����E�E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�����ł��Ȃ��ł��̂ɂ��܂��ĊQ���o�܂��B
�A���t���o�邱�Ƃ�����܂��B
�B�A���u�~���s���̊Q�i����݁A�����Ȃǁj���o�܂��B
�C�����l�̏㉺���������Ȃ�܂��B
�D��̕���p���o�₷���Ȃ�܂��B
�E�̑��̎���̌������������邱�Ƃ�����܂��i�̍d�ς̏ꍇ�j�B�F�Ɖu�̓����������܂��B
�G�ӎ����������Ƃ�����܂��B�@�@�@
�R�D��ӂ̊T�v�@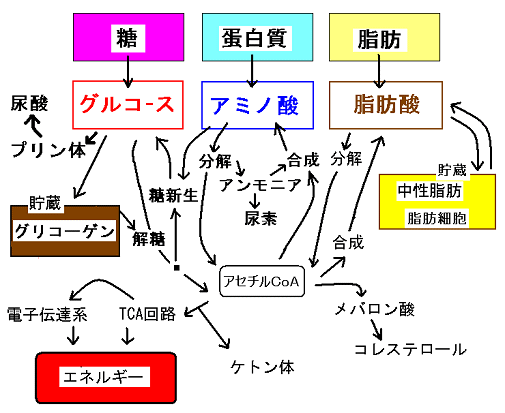
���ƒ`�����Ǝ��b�́A������x���݂��ɕϊ�����܂��B���������āA�u�A�^�V�A���Ȃ�ĐH�ׂȂ��̂ɁA�ǂ����đ���̂�����H�v�ƁA�s�v�c�Ɏv�����Ƃ͂���܂���B�]�����h�{���́A�O���R�[�Q���⎉�b�i�������b�j�̌`�Œ�������܂��B
�����悤�ɁA�ɕ��̂��ƂɂȂ�A�_��A�R���X�e���[�����̓��ō�������܂��B���̎�ȏꏊ�͊̑��ł��B
�S�D�̑��𒆐S�ɍl���铜���̗���@
�@�����̋z���i��O������܂��j�@�@�@�@
�����̓f���v���A�V�����A�����A���蓜�A�ʓ��Ȃǂ��܂݂܂��B�H�ׂ����̒��̓����́A�݂⒰��ʂ邤���ɏ����t�ɂ���ĕ�������A�u�h�E���ɂȂ����ꍇ�͏�������z������܂��B�@�@
�@�����̗A���A��荞�݁@�@�@�@
�z�����ꂽ�u�h�E���́A�E�}�̖��i���j�̂悤�ɖ喬��ʂ��Ċ̑��ɓ���܂��B�̑����o�đS�g�A���ɔ]�A�ؓ��⎉�b�זE�ɂ��^��܂��B������荞�܂�鎞�ɃC���X���������ʂ����܂��B�@
�@����Ӂ@�@�@�@
�̑��ł̓u�h�E������G�l���M�[�����o���A�]���������͒����܂��B������ۂɂ̓O���R�[�Q������_���̌`�����܂��B�����G�l���M�[�⌌�����s�������ꍇ�ɂ́A���������܂��B
�@�^�����@�@�@�@�@
�^�����n�߂Ă��炭����ƁA���t���̃u�h�E���͌͊����A�V�����b�_���ؓ��Ȃǂɉ^��ăG�l���M�[���ɂȂ�܂��B�O���R�[�Q�����̑���ؓ��ŕ�������܂��B�^�����I���ƃG�l���M�[�������n�܂�܂��B�^���̌��ʂ͂Q�����炢�c��A�����l�Ȃǂɂ��e��������܂��B
�@�Q���Ԃł́@�@�@�@
�l�Ԃ̑̂͋Q���Ԃɑς���悤�ɃO���R�[�X��ߖA�ʂȂ��̂��G�l���M�[���Ƃ��ė��p����A���邢�͕ʂȂ��̂���O���R�[�X�ݏo���d�g�݂������܂��B�@�@�@�@
�̑���ؓ��ɒ~�ς��ꂽ�O���R�[�Q�������ăO���R�[�X�����_�ɂ��A�ʏ�̃u�h�E���Ɠ����悤�G�l���M�[�����o���܂��B�P���̐�H�ŃO���R�[�Q���̂قƂ�ǂ͕�������邻���ł��B
�A�~�m�_�Ȃǂ���V���Ƀu�h�E�����������i���V���j�A������K�v�Ƃ���]�Ȃǂ̑���ɒ��܂��B
���t���̓����ɒ[�ɕs������ƒ`���⎉�b���������܂��B�ؓ����A�~�m�_�ɕ������ăG�l���M�[�̍ޗ��Ƃ��đ�ӂ����̂ŁA�ؓ����ׂ�܂��B�@
������������[�����ƁA���̔����͎~�܂�܂��B���������āA�Q���Ԃ̎��̓��̕�[�i�_�H�Ȃǁj�́A�ؓ����ׂ�̂�h�~����̂ɗL���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���b�����Ď��b�_�ɂ��A�ؓ��̃G�l���M�[���ɂ��܂��B�̑��ł̓P�g���̂��ł��܂��B����͔]�ɉ^���ƁA�G�l���M�[���Ƃ��Ďg���܂��B�̑��ł̓P�g���̂������ł��܂���B�ؓ���t���ő�ӂ���A�A�ɂ��r������܂��B�@�@�@�@�@�@
�@�C���X�����s����Ԃł́@�@�@�@
�C���X�����������Ȃ����͓����זE�Ɏ�荞�ޗ͂������܂��̂ŁA�����l�i�O���R�[�X�j���オ��܂��B�ʏ�̓��A�a�ł́A���Ԃ��o�ĂΓ����̑��Ɏ�荞�܂�Č����l��������܂��B�������A���������Ԃɍ����ǂ͐i��ł��܂��܂��B�@�@
�C���X�������قƂ�Ǔ����Ȃ���Ԃł́A�E�}�̂悤�Ɍ������זE�̒��ɂ͎�肱�߂Ȃ��̂ŁA�����͂�������̂ɗ��p�ł��Ȃ���ԂɂȂ�܂��B�@�@
���̎��́A�����̃G�l���M�[���Ƃ��āA���b�����锽�����N����܂��B���̍ۂɃP�g���̂�����܂��B���x���������ƃP�g���̂͑�ʂɔ������܂����A�̑��ł͏�������܂���B�t����ؓ��ł��������������Ȃ��ƁA�P�g���̂����܂��Č��t�̃o�����X��������A���A�a�������Ɋׂ�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�C���X�������ߏ�ɂ���ꍇ�́@
�C���X�����͌��t����זE�ɂǂ�ǂ�u�h�E������荞�݂܂��B�����l�������肷���āA�ጌ�����N�����܂��B�ጌ�������m���Ċ̑��ŃO���R�|�Q���Ȃǂ���u�h�E�����������锽�����N����܂����A���x��܂��̂ŁA�ጌ���̔���̏ꍇ�͑��₩�ɓ�����⋋���Ȃ��Ƃ����܂���B�@�@
�u�h�E�����h�{���ɂ��Ă���]�Ȃǂ��A�����̕s���ɂ���Ċ����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�ؓ��̂悤�ɑ��̉h�{�����ӂ̎�i�������Ă���g�D�͑��v�ł����A�]�͉e�����₷���悤�ł��B�@�@�@�@�ؓ��ɂ��O���R�[�Q��������܂����A�u�h�E���ɕω������Č��t���ɏo���\�͂͂Ȃ��̂ŁA�ጌ���Ɋւ��Ă͊̑�������ł��B�O���R�[�Q�������Ȃ���Ԃł́A�ጌ������̉ɂ���Q������܂��B�@
�T�D�̋@�\�����@
�̑��̋@�\�͌��t�����ł͂Ȃ��Ȃ�����܂���B�{���̋@�\�͑����I�ɔ��f���Ȃ��Ƃ����܂���B�@�@�@
|
GOT�iAST�j |
�̑��ɑ��݂���y�f�ł��B���t��ؓ��ɂ��܂܂�܂��B�̉��Ŋ̍זE�����鎞�A�ؓ������߂����A���t�זE����ꂽ���ɂ͐������オ��܂��B |
|
GPT�iALT�j |
�̑��ɑ��݂���y�f�ł��B���b�̂▝���̉��Ȃǂ̎��ɂ͐������オ��܂��B�ł��A�Ⴆ�Ί̍d�ς̎��ɂ͒ʏ�オ��܂���̂ŁA�̋@�\�������Ă�����l�̂��Ƃ�����܂��B |
|
�K���}GTP |
�̑���t���ɑ��݂���y�f�ł��B�A���R�[����ۂ�Əオ��X��������܂��B�_�`�̗���ɑ肪���鎞���オ��܂��B |
|
ALP |
�̑��ɑ��݂���y�f�ł��B����ٔՂɂ����݂��܂��B�_�`�̗��ꂪ��ƍ����Ȃ�X��������܂��B |
|
�A���u�~�� |
���t���̒`���̔������炢���߂Ă��܂��B���t�̔Z�������A�z�������Ȃǂ��^�Ԗ������ł��܂��B�̑��̒`�������\��������ƁA���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B |
|
�R�����G�X�e���[�[ |
�̑��ō��������y�f�ł��B�̋@�\�����������͐�����������X��������܂��B |
|
�r�����r�� |
���t�̂��ƂɂȂ镨���ł��B���t�����w���O���r���������܂��B�}���Ȋ̉���A�_���̕ǂɂ���ď㏸���܂��B |
|
������ |
��Ɋ̉����i���i�̍d�ρj�̎w�W�ɂȂ�܂��B�̑��̌����������Ȃ��āA�B���Ɍ��t�������ƌ���������܂��B |
|
�v���g�����r������ |
�v���g�����r���́A�̑��ō����`���ł��B���t���Ìł�������q�̋@�\��ł��܂��B�������̉����N���������̎w�W�ɂȂ�܂��B |
|
�摜�f�f |
�摜�Ŋ̋@�\�͉���ɂ����̂ł����A���b�̗̂L����A�̑��̎�ᇂ̌����A�̑��̑傫���̔��f�ɂ́A�G�R�[�ACT�AMRI�Ȃǂ̌������֗��ł��B |
�U�D�̑��a���ꂱ��i��\�I�Ȃ��́j�@
�E�C���X���̉��iC�^�AB�^�̉��Ȃǁj�A���ȖƉu���̉��i���R�ɔ��ǂ���a�C�B�����̖Ɖu�����Ŋ̑��ɉ��ǂ��N����j�A�̑����i�̍זE���A�]�ڐ��̊��Ȃǁj�A�̌��ǎ�i���ǂ̉�̂悤�Ȏ�ᇁj�A�̍d�ρA�������d�����_�lj��i�_�ǂ𒆐S�Ƃ��ĉ��ǂ��N����A�_�`�̗���Ȃǂɏ�Q���N����a�C�j�A�������_�`���̍d�ρi�����s���̉��ǂ̈��j�A�A���R�[�����̉��A��ܐ��̉��A���b�́A�̔^ᇁA��A���R�[�������b�̉��iNASH�j�Ȃ�
�V�D�̍d�ς̕a�ԁ@
�ɒ[�Ɋ̑��������Ȃ����ꍇ���l����ƁA�̋@�\�̗������[�܂�܂��B
�̍d�ς̎�Ȍ����́A�E�C���X���̉��ł��B��U����C�^�̉��ɂ��܂��B�ł��A���b�̂Ȃǂ�����̍d�ςɂȂ邱�Ƃ͂���܂��B�̍d�ςł͖{���̊̍זE�̑���ɑ@�ۍזE�Ŗ�������Ċ̑��Ƃ��Ă̋@�\�������܂��B�@�ۂ������邱�Ƃɂ���Ċ̑��̌������������A�h�{�f�̎�荞�݂��s������ƌ����Ă��܂��B�@�@�@
�܂��A��Ӌ@�\���������A�h�{�f�̕������x��܂��i�����l�̉����肪�x���Ȃ�j�B�����ۂ��ʼnh�{�̒����@�\���ቺ���A�G�l���M�[���ؓ��ō�낤�Ƃ��邽�߁A�ؓ������������@������܂��B�@
�W�D�̍d�ς̏Ǐ�ƕa�ԁ@
���ӊ��A���t�@�@�@�@
���ӊ��͉�ō�p�̒ቺ��A�`�������\�̒ቺ�A�h�{�����\�̒ቺ�Ȃǂ��W���ċN����Ǝv���܂��B�@���t�́A���t�̐F�f�ł���w���O���r�����甭������r�����r���̏������ł��Ȃ��Ƃ��ɋN����܂��B�@�@�@�@
�菶�g���i��̂Ђ炪�s���R�ɐԂ��Ȃ��ԁj�N���ǎ�i�N���̂悤�Ȗ͗l���畆�ɏo��j�@�@�@�@
�����z�������̕������x���Ȃ�ƁA�畆�̖э��ǂɊg������̂��o�Ă��܂��B���ꂪ�����ƌ����Ă��܂��B�肪�Ԃ�����̍d�ςƂ͌���܂���B�@�@�@
�����i�����̒��ɐ������܂�j���̕���i�ނ��݁j�@�@�@
��Ɍ��t���̃A���u�~���Ƃ����`�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��甭�����܂��B�A���u�~���͕��ʂSmg/dl���炢����܂����A�R���炢�ɂȂ�ƌ��ǂ���g�D�ɐ������R��o�čs���܂��B���̂��ߕ���݂₷���Ȃ�܂��B�@�@�@�@
�H�����
�H���̌��ǂ��ӂ����̂́A�̑��ɑ@�ۉ��̂��߂Ɍ��̒ʂ肪�����Ȃ��āA�喬�����オ��A���̒Ⴂ�H���̐Ö��Ɍ�������邽�߂ł��B���̏㏸�͕����ɂ��W���Ă��܂��B�Ö�ᎂ��j��ƁA��o�����N�����ċ}�����邱�Ƃ�����܂��B�@�@�@
�P�O�D�A���R�[���Ɗ̑��a�@
�A���R�[���ɂ��̑��a�@�@�@
�A���R�[����A�����ނƁA�X���ȏ�̐l�����b�̂ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B���b�̂́A�]�����h�{�����̑��ɗ��܂�����Ԃł��B����ɐ����̐l�́A�A���R�[�����̉��̏�ԂɂȂ�܂��B�����Đ��p�[�Z���g�͊̍d�ρA����Ɋ̊��ɂȂ�܂��B�����̗��R�̂ЂƂƂ��āA�A���R�[���̑�ӎY���ł���A�Z�g�A���f�q�h�̔�����p������ƌ����Ă��܂��B�@�@�@
�A���R�[���̍�p�@�@�@�@
�����l�̒��߂́A�A���R�[���̑�ӂƋ������܂��B�@�A���R�[���͍זE�̖���ʉ߂���͂������A�z������₷���ł��̂ŁA�̑��ł������ɕ�������A���̍ۂɑ�ʂɐ����镨�����������邽�߂ɁA���̑�ӂ͌�ɂȂ�ƍl�����Ă��܂��B�@�@�@�@
�A�~�m�_���瓜����锽���i���V���j�Ȃǂɂ���Ċ̑�������̗ʂɒ��߂��ďo��͂��̃u�h�E�����A�A���R�[���̕������D�悳���Ԃ͏o�Ȃ��Ȃ�A�ጌ���ɂȂ�X��������܂��B�@�@���A�a�̖���g���Ă���ꍇ�́A�A���R�[���Ɩ�̑��ݍ�p�i�����ۂ݁j�Ō������ጌ�����N�����̂Ŋ댯�ł��B�@�@
�A���R�[���̑�ӂ͓��̕����o�H�iTCA��H�j�Ƌ������܂��B���̂��߁A���Ɍ����������ăG�l���M�[���͂���Ƃ��Ă��A�g���Ȃ��悤�ȏ�ԂɂȂ�܂��B�@
�܂��A�A���R�[���̕����Y���͎��b�_���o�Ē������b�ɂȂ�܂��̂ŁA���ǂ͎��b����锽�����N�����Ă��܂��܂��B�@�@�܂�A���R�[���́A�������t���ɏo�čs���̂�}���铭���ƁA�������b����莉�b�𑝂₷��p������܂��B����������ƁA��ӂ��}�q������ŕ��ł��B�_�C�G�b�g�ⓜ�A�a���ÂƋt�̓����ł��B�@�@
����ɃA���R�[���́A���ڊ̍זE��j���p�����悤�ł��B�A�Z�g�A���f�q�h�̓ł��A�זE�̑�ӂɕ��ׂ�^���邽�߂����m��܂���B�@�@�@�@�@�@�@
�A���R�[���ƌ����l�@�@�@�@
�A���R�[���͌����l����ߐ��ɉ����܂��B�ڂ����͉����Ă��܂��A�̑����瓜���o��̂�}�����p�̂��߂Ǝv���܂��B���̂��ߐH�O�������ނƐH�~���o�܂��B�ł����̓������}�q�����邾���ŁA���������Č��炷�̂ł͂Ȃ��̂ŁA����Ό��������̌����~����p���ƌ����܂��B�@�@�@�@
�A���R�[���͎��b�ɕϊ�����܂��̂ŁA��ӂɕ��ׂ������A�����I�ɂ͌����l���グ���p������܂��B�@
�P�P�D�h�{�ߑ��Ɗ̑��@
��ӂ̐����}�ł����ɂȂ����悤�ɁA�]�����h�{�f�݂͌��ɕϊ�����Ȃ���A���b��O���R�[�Q���̌`�Œ�������܂��B���̔����͋Q��ɑς��邽�߂ɕK�v�Ȕ\�͂ł����A�O�H�𑱂���ꍇ�͑傫�Ȗ��ł��B�̍זE�̒��ɒ������b�Ȃǂ̎��������܂�܂��ƁA���b�̂ɂȂ�܂��B�@�@
��A���R�[�����ގ��b�̉��iNASH�j�Ƃ����a�C������܂��B�̑��Ɏ��b���������܂�����Ԃ̐l�̒��Ɋ̉����������āA�̍d�ςɂȂ�a�C�ł��B�ڂ����͉����Ă��܂��A�����I�ȉh�{�ߑ���Ԃł́A�̑��ɉ��ǂ��N�����čזE�����ł��锽�����N����₷���Ȃ�悤�ł��B�@�@�@
�얞��Ԃ��A�̍זE�ɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă���̂��ڂ������Ƃ͕s���ł����A�얞�ŃC���X�����̌��ʂ������邱�Ƃ͊m���ł��B���b�זE����A��ӂ̃W���}�����镨���i�T�C�g�J�C���j���o��ƌ����Ă��܂��B�@�@
�܂��A���b���[���ɂ����Ԃł͓��������ɕ������锽���͕K�v�Ȃ��Ȃ�܂�����A�]������������������X�����\�z����܂��B���������A�a�ł́A���������ɕ�������邱�Ƃ��K�v�ł��B�������Ȃ��ƁA�����������t���ɗ��܂荂�����ɂȂ��č����ǂ��N�����܂��B����ɗ]�v�ȑ�ӂ��N�����ėL�Q�����������邱�Ƃ��A����̐}�ɂ���܂����B�@�@�@
����̘b�́A�h�{�����̓��e�𗝉����鎞�̎Q�l�ɂȂ�܂��B�H���Ö@��^���Ö@�́A���ǂ̂Ƃ���A�����Ɋ̑��̑�ӂ߂��邩�A�ؓ��̊����ƘA�������邩��ڍ����Ă��܂��B�H����K���ɂ���ƃC���X�����̌��ʂ���������A�ؓ��ɃJ�����[���g�킹��Ɠ���ӂ��X���[�Y�ɂȂ�܂��B�@�@�@�@�@
�C���X�������˂́A�������זE�Ɏ�荞�܂��āA����ӂ�⏕����̂��_���ł��B�����ɓ���ӂ��N�������߂ɃC���X�����𒍎˂�����A�^���Ö@�����Ă���킯�ł��B�@�C���X�����������Ȃ���A�����l�͏オ��A�`���⎉�b�̑�ӂɂ����e�����\�z����܂����A�������オ��X��������܂��B
�^���Ö@�́A�����g���ē����̎��v�i�K�v���j�����߂āA����ӂ̗���𑁂�������ʂ�_���Ă��܂��B�@
�H���Ö@�́A��������鎉�b�̗ʂ����炷�̂��傫�ȖړI�ł��B�����ɕK�v���[���ȃG�l���M�[��₢�A�]�����J�����[�����܂�Ȃ��悤�Ƀo�����X�悭�h�{������邱�Ƃ���{�ł��B�@
�@�@�@�@�@