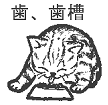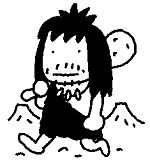糖尿病患者によく見られる感染症
平成18年4月20日 勉強会 橋本 泰嘉
糖尿病患者には病原体が感染しやすく、しかも重症化しやすい傾向があると言われています。本日は、感染症を予防するために勉強をしましょう。感染症の種類を言うときには、感染する場所からの分類と病原体の種類からの分類法があります。その両方からの理解を深めましょう。
代表的な感染症(感染する場所)
歯 歯肉炎、歯槽炎
副鼻腔 副鼻腔炎
肺 肺炎、肺結核
肝臓 肝膿瘍
胆嚢 胆嚢炎、胆道炎
尿路 腎周囲膿瘍、腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎
皮膚 皮膚真菌症、毛のう炎
軟部組織 壊死性筋膜炎、よう、せつ、糖尿病性壊疽
感染の場所は、上に書いた以外にも全身いたるところにあります。重症の場合は、菌が血液を介して体を回る「敗血症」という状態になります。
代表的な感染症(病原体)
今度は病原体からの分類をしてみましょう。細菌の名前にはなじみが少ないと思いますが、どのような菌がいるのかによって、同じ感染症も対処法が違ってきますので、知っておいて損はないと思います。
結核菌 肺結核、腎結核
肺炎球菌 肺炎の原因菌のひとつ
インフルエンザ桿菌 肺炎の原因菌のひとつ
緑膿菌 副鼻腔炎、外耳道炎など
溶連菌 咽頭炎、筋膜炎など
大腸菌 腸炎、胆道炎、尿路感染症
ブドウ球菌 皮膚感染症など
真菌 水虫、肺などほぼ全身
ウイルス各種 ほぼ全身
通常は上のふたつの分類法によって感染症を説明しています。例えば、肺炎球菌による肺炎、大腸菌による膀胱炎という具合です。同じ肺炎でも、例えば肺炎球菌による肺炎と、真菌(カビ)による肺炎では薬も違いますし、経過も相当違います。
感染症の予防方法
感染症は予防が可能です。予防のためには、私達が持つ免疫力が充分であること、大量の病原体に触れないこと、触れても速やかに排除する(洗う)ことが条件になります。
免疫力を維持するために
免疫とは、病原体から私達を守るために先祖から受け継がれた仕組みです。免疫力をたかめるという効能で、食品などを売り込もうとする業者がいますが、糖尿病患者の場合は、なによりも血糖のコントロールが効果的です。
栄養状態も大事です。免疫の働きには充分なエネルギーが必要ですから、例えば戦争などで飢餓状態になった時には、感染症が蔓延することは皆さんよくご存知だと思います。
でも糖尿病の場合は代謝機能に障害がありますので、栄養をたくさん取っても血糖値を上げるだけで免疫力に直結しません。かえって細菌の活動を助けてしまいかねません。充分な栄養と血糖コントロールを両立させることが大事です。感染症の時には一時的にインスリンを使うこともためらってはいけません。普段の治療が食事療法であっても、インスリンが必要な場合は稀ではありません。
休養も大事です。仕事をやりあげてしまうために短時間に集中して働いても、病気になってしまえば寝込まなければなりませんから、あせりは禁物です。運動療法も、度が過ぎれば風邪の原因になります。
大量の病原体に触れないために
かって北米の鉄道建設のためにヨーロッパや中国から労働者が集まった時に、手洗いの習慣を持たなかったヨーロッパ人より、手洗いをする中国人のほうが病気をしにくかったという話があります。手洗いには病原体を減らす効果があります。
病原体はそこらじゅうにいますので完全に除菌することは難しく、除菌をうたった商品にこだわっても無理があります。また、うがいのためにイソジンうがい液を慢性的に使っている人をみかけますが、甲状腺機能に影響がでることもありますので注意して下さい。
菌を排除するために
手洗いをした後に、タオルを家族といっしょに使うと、タオルを介して病気をもらうことがあります。タオルは一人一人別に使うのが正しい使い方だと思います。
学問的な裏づけのある話ではありませんが、痰をうまく出せる患者さんは肺炎になっても治りが早い印象があります。もともと体力があるから痰も出せるのかもしれませんが、病原体を排除するのが治療の原則ですから、痰や膿などはなるべく体内に止めないほうがいいと思います。肺炎になっても横向きやうつ伏せ寝の方が痰を出しやすくて治りがいいこともあります。鼻水もすすらないで出して、拭いたティッシュなどはゴミ袋に入れて、封をして2次感染を防いだほうがいいかも知れません。
代表的な感染症の予防法、対処法
歯肉、歯槽炎は血糖値が高いと起こしやすいし、歯槽炎があることで血糖コントロールが悪くなるという悪循環になりやすいので、虫歯の管理は糖尿病の管理のために一般の人よりも重要です。歯ブラシを上手に使って口の中を衛生的に保つように努力すべきです。お年寄りの場合は、口の中の衛生状態によって肺炎の起こす率が変ったりします。
最近流行した胃腸炎のうち、ノロウイルスという病原体が老健施設で死者を出したりして有名になりました。もともとはカキなどの海産物の中で繁殖しているウイルスですが、調理場のまな板や調理人の手を介して媒介されますので、何からもらうか分りません。学校に行っている子供さんがいる家庭では、学校からもらってきて、家のタオルを介して家族に拡がるかも知れません。
下水道管や排水路を扱う時には、特殊な菌に感染することがあります。例えば、破傷風菌による敗血症やレジオネラ菌による肺炎です。レジオネラ菌は、温泉施設の感染が有名です。湯の管理がおろそかな温泉施設には行かないことや、排水路用水路の工事の時にはマスクや手袋を忘れないことも大事です。
糖尿病性壊疽は、主に足の末端の感染から起こります。したがって、足を毎日観察し、傷がないか確認することで重症化を防ぐことができます。はやめに消毒すれば、ほとんどの病原菌は退治できます。特に神経障害のために足の感覚がにぶくなっている方は、かならず靴下を履いて傷を予防すること、靴も靴擦れしにくいものを選ぶことなども忘れてはいけません。やけどをしないために、ファンヒーター等の熱風は直接あびないこと、湯たんぽは使わないことなどの用心も必要です。
壊死性筋膜炎は、皮膚の小さな傷から始まりますが、筋肉の表面を伝わって急速に拡がり、命に関わることがあります。傷の消毒と観察を忘れないこと、また血糖値がコントロールできていればご自分の免疫力で細菌の勢いを弱められますから、血糖コントロールに努力することも予防の原則です。傷の周りに赤い発疹が出たり、それが拡がったりするときは炎症が拡がっていることを意味しますから、直ちに病院を受けたほうがいいと思います。
膀胱炎は、水分のとりかたで予防が可能です。心臓や腎臓に問題がなく、むくみがない糖尿病患者さんの場合は、一般に血糖の影響で脱水になっていると考えられますので、水分は多めに取っておくべきです。特に膀胱炎の場合は、尿が膀胱内にたまって出て行かないと膀胱の中で菌が増えてしまいますので、なるべく尿の量を増やすために水分を取るべきです。いったん膀胱炎になったら、面倒ですが菌の種類を調べてから治療したほうがいいと思います。特に膀胱炎を繰り返している人は、抗生物質が効きにくい菌が残っていることが多いので、効果を確認してからでないと簡単に治療できないことがあります。
肺結核は意外な人で発見されます。無症状と言ってよいくらい症状がないか、ご本人は風邪と思っていらっしゃる場合が多いようです。昔のように血を吐くような結核は多くありませんから、風邪症状が続く時など体調がおかしい時にはレントゲンと痰の検査を怠らないことが大事です。
インフルエンザはもともと感染力が強いウイルスですので、特に糖尿病患者が感染しやすいとは言えないかもしれませんが、感染すると血糖値も非常に変動しやすく、体力を消耗して別な感染を引き起こすこともありますから、予防できるなら予防すべきです。流行する前の予防接種と、流行時期の手洗いは欠かさないこと、病院を受ける時には待合でマスクをして待ち、何かを触ったらそのたびに手を洗うことなどで予防が可能です。