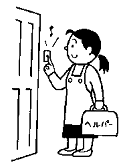介護保険の意義
介護保険に関する私見を述べます。介護保険制度は意義のある制度です。制度が始まってから、重い障害がある人は相当なサービスが受けられるようになり、家族の負担は減ったと思います。制度が始まる前は、家族の犠牲だけで成り立っていた部分がありました。そして、介護の職場は田舎で産業が少ない地域に仕事先を確保する効果もありました。以前なら都会の職場に流れていた若者が、介護の現場で仕事につける機会を得ました。
でも、私は導入の仕方に不満がありました。効率が悪いと感じたからです。素人目に見ても計画が行き当たりばったりの印象がありました。まず財源が足りるはずがないと思えました。高齢者の割合が多い自治体ほど財政が厳しいはずですが、さらに負担を強いるのは無理としか思えません。また、事務作業が多すぎて金銭と労力の両面で効率が悪いこと、新たな施設の建設費に保険料が費やされて無駄なことなどを感じていました。
導入の仕方
一般に、国が何かの事業を導入する時は、最初は破格の好条件を提示して多くの人に参入させないと成功しません。医療保険制度もそうでした。しかし、そのような手法は、財政が豊かな時には有効ですが、介護保険導入当時はもう最初から無理が見えていました。逆に、最初は最も緊急性の高い重度の障害者に限って資金を投入し、段階的に民間企業に委託して徐々に軽症者にもサービスを広げるような手法もあったように思います。国鉄やNTTなどが民営化されていた時代ですから、そのような(チマチマした)手法もやむをえないと受け入れられたはずです。最初の条件がみみっちいと業者の参入が進まないという欠点はありますが、少なくとも無駄は少なかったでしょう。
導入当時は医師会に対して、「介護は待ったなしです。とにかく導入してから問題は後で修正しましょう。」と説明されていましたが、みずから長期的に計画していませんと言っているようなものだと感じました。また、高級官僚の逮捕に代表されるように、利権がからんでいたようです。ビッグビジネスのチャンスとばかり、様々な業種が新しい施設の建設に群がりましたが、無駄はなかったのでしょうか。
そもそも介護保険は、介護現場を補助する本来の目的と、医療費を(見かけ上)減らす目的、民間の業者にビジネスを提供する、ついでに厚生官僚にも新しい職場を提供するという目的があったように感じました。できあがった制度を見ると、本来の目的以外のほうが中心になったかも知れません。制度がおかしいと言おうものなら、「では介護保険に反対するのか!」「厳重に管理しないと平等にサービスを提供できない」と反論されて、うまく目論見を隠されてしまったようです。
社会保障の維持
医療保険料だろうと介護保険料だろうと、払う金に違いはありません。本来、医療と介護を分ける必然性は全くありません。実際の対象者を見れば、すぐ分ることです。無理に分けて効率が良いはずがないと思います。結局は建設費や人件費も含めて社会保障予算の規模を大きくしただけで、旧来の老人ホームなどを充実させたほうが無駄は少なかったような気がします。
本来、社会保障は儲けをねらうものではなく、必要不可欠のレベルに止めるべきものですので、ビジネス感覚の事業を導入すると維持するのに無理します。厚生年金が良い例でした。数百億円の予算を使って各地にホテルなどを作りましたが、採算が取れなくなって閉鎖か、安い金額で売却されました。結果として保険料が消えてしまった格好になっています。後生(後から生まれる人)に負担をかけてしまう計画は、もっと慎重に考えるべきでした。
業者にとっては、新しい施設基準を義務付けて建設をしてもらえないと仕事が増えませんし、自分達が介護事業に進出するためにも、新たな保険制度を作って欲しかったのだと思います。確かに大きくて美しい施設ができて良かったし、建設業界は潤って景気にも寄与したと思いますが、施設を維持していくためには相当な保険料を要するはずです。保険料が介護ではなく建設費に使われるのは、ちょうど農業振興費が土木業に流れて農業には回ってこないのと似ています。財源が無限なら構わないのですが。
現状は?
金銭面を見れば、今日の状況は予測通りで、財政的な見通しが厳しいことから、審査を厳しくし保険料を上げざるをえないと言われます。本当の財政状態は分りません。建設費や事務費を除けば黒字のように思いますが、大勢の事務官が管理するシステムですから、効率を良くするということは最初から望めません。
何かの介護サービスを受けていた人が、「今後は受けられませんよ」と言われると、前の状況に合わせていた家族は生活の修正をせねばなりません。私は認定審査委員をしていましたが、見たこともない患者を事務的に判定するだけで、「この患者は動けないから、認定を重くしないといけない。」と訴えても、「今は軽く判定するように基準が変更されています。」と、事務的に却下されます。まさに官僚的な印象でした。
無慈悲に基準を決めるのは、平等という面では確かにいいことです。細かい事情など無視して機械的に判定しないと、ゴネる人が得するケースが増えます。ただし旧共産圏がそうだったように、平等を重視しすぎると管理者ばかりが偉くなって現場に自由度がなくなり、全体が沈滞する傾向があります。
また、細かく基準を修正して対応しようというのは立派な考え方ですが、長期にそれをやっていては小手先の対応に終始してしまいます。その結果、皆が懸命に努力しているはずなのに、なぜか別な要因に引っ張られて(例えば役人の縄張り争いなど)、問題が解消しないのが常です。定期的にドラスティックな路線変更をすべきです。少し前に、構造改革が必要だと皆が感じたのは、まさにそういう点に因ったのではないでしょうか。
根本的欠陥
役人に限らないかもしれませんが、我々は古来より抜本的、戦略的なことは嫌いで、修正が好きな傾向があります。修正することは業績になるでしょうが、制度を修正して介護報酬を減らせば、現場にとっては‘登った途端にはしごを外される’ようなことになります。少なくとも10年くらいは修正を要しない計画が作れないなら、そもそも計画する資格がないと思いますが‥‥。
これに対し、介護現場に携わっている人達は皆さん熱心で、夜遅くまで事務作業や会議をこなしていて感心します。ただし、事務作業は介護ではありませんから、一生懸命やっても患者のためには直接の恩恵がありません。事務は必要最小限に止めるべきで、現在のルールでは無駄な労力を強いている点で問題があると考えます。
また、保険料を納めるばかりで自分達の手で家族を介護している方達がたくさんおられますが、明らかに損しています。努力する人に何らかの負担軽減がされないと、努力がバカらしくなってくるはずです。ルールに様々な問題点がありますが、そもそもルールの作り方にも根本的問題があると考えます。「効率」「戦略性」「長期的視野」という観点があれば、違ったシステムができたと思います。今後は高齢者の人口が増えますから、ますます状況は悪化すると思いますが、会議を生業としている人達は無駄を気にしませんので、計画を丸投げしては後生に害を及ぼしかねません。
また、密室で決めると現場の状況と遊離した判断に陥る危険性があります。丸投げする政治家を支持してはいけないと私は当時思いましたが、一般の人の感覚は私とは違っていたようで、根拠が明示されないまま官僚的に方針が決定されています。最近は介護予防という考え方が導入されたようですが、確かに効果があるという根拠があるのか、疑問です。思いつきでやっているのではないかと疑います。実験精神が豊かなのは良いことかも知れませんが、大きな予算を動かすのですから、モラルがあるなら施策の根拠は明示すべきだと思います。
目標
私は少し先走る傾向がありますので、意見が一般常識となって認められるのには20年くらいかかります。あまりボヤいていても仕方ありませんので、何か案を提示したいと思いますが、財政に詳しくないので具体的なものは作れません。でも目標くらいは考えられます。
①サービスを利用しない人は、少しでも金銭的負担が軽減されるべき(健康に留意するよう利益誘導するため)
②基本的には希望するサービスは受けられるべき(本人が費用を負担するなら受けられる自由があったほうが良いから。問題は、その負担料を適切に設定できるかですが)
③判定基準、個人負担割合などの修正は、国会の委員会で審議する(密室で決めないことが原則だから)
④基準、規則は国政選挙前の一定期間に公開する(これも密室で決めさせないための原則)
⑤財源は国の一般会計から出す(そうすると自治体から法外な要求をされるのが問題ですが、財政が安定することは確実。消費税を福祉目的税にしようという意見もありましたが、本来は予算が肥大化しすぎているだけで、財源がないというのは欺瞞としか思えません。)
空論でしょうか?歴史の本を読む限り、複雑な制度を作り、コロコロ税率を変えた国はロクな結果を招いていないように思います。また、密室で決定した恣意的な判断がまかり通った国や企業も、人の期待を失って破綻している例が多いような気がします。
診療所便りより 平成19年4月
院長 橋本泰嘉