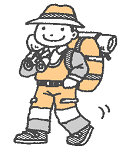御嶽山の噴火(爆発)は悲惨な結果をもたらしました。登山には最高の季節、ちょうど山頂に人が集まる時間に、しかも目立った前兆なく噴火していますので、悪い条件が重なっています。被災された方々は本当に不運で、お気の毒と言うしかありません。
阿蘇や金峰山でも同じことが起こるかもしれません。でも噴火は滅多にないことですし、前兆がないなら対処も難しいので、地震などの把握しうる指標で考えるしかないでしょう。
対策が必要ないわけではありませんが、山登りをいっさい止めたり、全ての山に厳重な監視体制を敷くような対応は現実的ではないように思います。
人工甘味料の問題点
(人工甘味料と腸内細菌)人工甘味料は、カロリーや糖分の制限が必要な方には有効ではないかと考えられてきました。血糖値を上げないはずだからです。栄養士にも積極的に使うように指導する人がいます。
ところが、今年発表された報告(Nature 514,181-186.2014)では、意外に代謝に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。理由は腸内細菌が変化し、糖の代謝能力が落ちるからと説明されています。腸内細菌を調べたり、取り出して他のネズミに投与したりすることで、確かに細菌のバランスが変化していること、糖の代謝能力が低下していることを確認できたようです。
この報告は主にネズミを使った研究ですから、人間にそのまま当てはまるとは言えませんが、人でも同様の現象はありえます。少なくとも多量の人工甘味料は控えるほうが無難でしょう。
(腸内細菌叢)最近はコマーシャルでも腸内細菌叢、善玉菌、悪玉菌などの文句がよく出てきます。今回の研究が問題視した細菌叢はCMの善玉悪玉といった観念とは違うはずですが、健康に良くない細菌のバランスを問題にしている点は同じです。我々が糖分を吸収する前の段階では、消化酵素や腸内細菌が働いて、食べた物を分解していくはずです。腸内の細菌が分解してくれないと体内に吸収されにくい栄養素も多いはずなので、できれば良い状態を維持したいものです。
ただし、腸内細菌叢を目に見える形で評価することは簡単ではありません。便を調べても、途中の小腸の状態は分かりません。細菌は腸管内の場所によって構成が全く違っており、その多くは培養が難しいこともあるので、わざわざ体から取り出して比較するのは非現実的です。評価が難しいものを論じる場合は、動物実験などを参考にするしかないように思います。
(甘味料の利点、欠点)人工甘味料の利点は、糖分の摂取を制限しても甘みを楽しめることです。私は今まで人工甘味料を勧める意見には懐疑的立場をとっていました。それは長期間摂取したことによる害が不明という理由によるもので、実際にどのような害があるか知っていたわけではありません。今回の研究も人間を使って直接証明されたものではないので、参考にすべき事象でしかないと思います。
ただし、害が分かっていないことも間違いないので、もし積極的に勧めるならば、モラルの観点から言えば、害より効果が優先されるという根拠を充分に説明できる必要があります。現時点で、それができる人は少ないはずです。
甘い物を制限すると、罰を受けているような情けない気持ちになります。何でも制限制限と強制的な言い方をされると、患者としては囚人になったかのような気持ちでしょう。そのため思いやりで人工甘味料を勧めていた栄養士もいたはずですが、安易すぎたかもしれません。害のことを知っておくこと、それを患者さんに充分理解していただく必要があります。
甘味料は腸内細菌に与える害の他、甘さに慣れてしまうことの害(本当の糖分も欲しくなってしまわないか)や、発癌性に関しても完全に否定できているとは言えません。 極度に砂糖に依存している特殊な患者さんを除き、人工甘味料を勧める指導は好ましくないと思います。量が少なければ腸内細菌叢が変化するまでには至らないかもしれませんので、うまく調整できれば禁止すべきではないのかもしれません。
診療所便り 平成26年11月分より・・・(2014.10.31up)