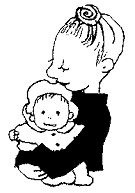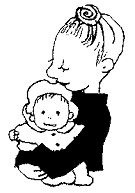
医療崩壊
医療崩壊という言葉をお聞きになったことはありますか? 市内にお住まいの方はピンと来ないかもしれませんが、地方の病院では小児科、産婦人科を中心に職員が勤務に耐えられなくなって運営が難しくなっています。内科、外科も同様です。麻酔科のスタッフがいっせいに退職したという話もいくつかありました。医学雑誌の分析をまとめますと、以下のような原因がありそうです。
理由その1
勤務医が耐えられなくなった最大の理由は、現在の医師研修制度だと思います。研修先が大都市の病院に集中したため地方大学の人員が不足して、医師を派遣するシステムが成立しなくなってしまったのです。
理由その2
その他にも理由があります。そのひとつは、医療紛争に関して法律が追いついていないことです。特に産婦人科は最も訴訟が多い科ですが、「これは最低限の義務だ」という明確な指標がありません。出産に関してはコンマ数%の事故は必ず起こるのですが、結果が悪いと医療ミスになります。
理由その3
また、アメリカ式の事務手続きを義務付けたことで、雑務が増えていくことも嫌気がさす理由です。秘書がいるからこそ成立するシステムを秘書なしで形だけまねています。加えて、さまざまな会議を義務付けたために、心ある医者ほど診療に専念したい思いと要求される作業とのギャップに嫌気がさします。会議を減らす会議をしたらという冗談もあるくらいです。
理由その4
医療費の抑制も関係しています。診療報酬は年々下げられて、良心的な治療をしても採算が取れなくなっています。下手すると、手術に使う材料費のほうが手術代より高いこともあります。病院の収入を確保するため在院日数を減らし、ベッドの回転を上げることを要求されるために、時間当たりの仕事量が増えてしまいました。
理由その5
説明義務も増えています。説明が詳しくなるのは良いことですが、稀にしかない副作用でも説明しないと義務違反と言われるので、「明日、隕石が落ちてくる可能性も否定できません。」式の説明が義務づけられています。常識的な説明では、裁判になったら終わりです。
理由その6
もともとの勤務条件も関係しています。当直あけで普段の勤務を続け、食事抜きで連続30〜40時間仕事できるのは道義的義務を感じるからですが、文書書きや会議への参加は道義的意義が高いとは限りません。
政府の危機管理は?
ルールを決めている人達と私達の認識レベルに大きな差があります。各々の規則には一定の根拠がありますが、全体にどのような影響があるのか分らないで決めてはいけません。 私達が何か医療行為をする時には、救急セットを準備してからでないと始めませんが、研修制度の導入には「もしこうなったら」という準備はなかったようです。「もし、医者の配置が変化したら」「一時的にせよ、麻酔科や産婦人科がいなくなったら」と考え、対処する危機管理能力が不足していたと思います。現場が混乱すること自体が失策ですが、誰も責任を追及されていません。実に変な話です。やり方が大本営の時代から変わってません。諮問会議の先生や官僚達は、昔の軍のエリートと同じレベルの過ちを犯しています。
研修制度改革の必要性は?
それに,そもそも旧来の医局制度は、そんなに悪かったのでしょうか? 制度を変えると田舎の病院が悲惨なことになるはずですから、都心部から段階的に制度を変えても良かったような気がします。私が田舎の病院に行ったのは貧乏クジのようなもので、誰かが行かないと医療が成立しないので、自分のキャリアを犠牲にしても仕方ないと思ったからです。耐えられなくなれば交代もいるのが救いでした。今の制度では地域のことより自分のキャリアを優先できますから、わざわざ犠牲になって地方の病院に行く医者はいなくなります。今になって地方勤務の義務化が論議されていますが、制度改革前によく考えておくべきでした。
ボランティア精神の限界
病院の現状は深刻ですが、まだまだ一般には認識されていないため、勤務に耐えられない医者が悪者になってしまいます。 根底に、医者の配置は自分が関与する問題ではないから知ったことじゃない、という感覚があるようです。私は予防医学が最も大事だと考えて専門を選びましたが、今日の状況なら最も不足している産婦人科を選ぶと思います。でも、そのようなボランティア精神に頼っていては、今後も問題は解決しないでしょう。 産婦人科に限らず、きつい科は学生から敬遠されています。社会の要求、規制がボランティア精神で耐えられるレベルを超えているからだと思います。 産婦人科医に限っての話で少し偏った内容ですが、現場の医師の意見が紹介されているブログがありますので、ご紹介します。
(http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/)
解決策は?
導入の仕方は良くなかったのですが、長期的には研修制度は今のような形になるべきだったと思います。 当面は医者のボランティア精神で耐えられる限りは耐えてもらって、病院間の調整(スタッフを集約するなど)で乗り切るしかないようです。数十年待てば調整できるはずです。
その間かなりの部分は諦めざるをえませんが、例えば、田舎の産婦人科医には国が数千万円を無償で提供する(金で釣る)のは速効性があって効率の良い解決策でしょう。医師数を増やすように論議されていますが、現実を見ていない考えだと思います。費用効率が悪く、効果が出るのに15年以上かかるはずです。
また、医療費の設定には無理があります。必要な医療を制限し、あまり命に関係ないものを優遇するような不透明な決定がまかり通ることがボランティア精神の意気をくじきます。
私個人としては、政策がどうであれ、状況がどうであれ、常にボランティア精神で診療するよう努めたいと思います。
診療所便りより 平成19年6月