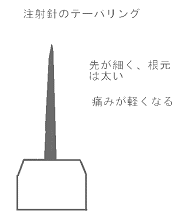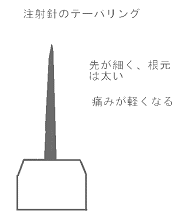
インスリン注射製剤について
糖尿病の治療の中心は、食事と運動療法です。これができなければ治療が成立しません。そして薬による治療の中心は、意外にも飲み薬ではなく、インスリンの注射です。
今まで数百人の患者さんにインスリンを指導しましたが、なかなか思う通りにはいきませんでした。本来なら医者や看護婦がやるべき注射を患者さんに自分でやってもらうのですから、「消毒とは?」「インスリンとは?」といった基本的なことからの学習と、相当な訓練が必要なはずです。間違えれば命に関わります。でも自己流の誤ったやり方で注射される方が少なくありません。実は医者でも充分に習得している人は、たぶん県内で20~30人しかいないと思います。残念ながら適当に指導し、処方されているのが現実で、人間を実験台にしているような感じがして怖く思います。
糖尿病の治療には複雑な要素が絡みますので、飲み薬では充分に効かないことが多いのが現状です。これに対し、インスリンの注射はより強力な効果があります。ご存知と思いますが、注射してまで血糖を下げる理由は、血糖が高い状態が続くと血管や神経、目、腎臓に害(合併症)が出るからです。コントロールがうまくいけば合併症を予防できますが、血糖を下げすぎれば低血糖による害が出ますので、厳密に血糖値を管理する必要があります。これが非常に面倒です。ご自宅や職場で、自分で血糖値を測っている人もおられます。
最近アメリカで、吸入により肺からインスリンを吸収させる器具が認可されました。注射は痛いので、注射以外の方法は患者さんにとっては大変な朗報です。日進月歩の医学の世界ですから、つい数十年前には考えられもしなかったような良い薬ができています。1日中安定した効果を示すものや、すぐ血糖値を下げるものなど、組み合わせれば一定の血糖値を維持できます。インスリンと似た作用を示す薬も開発中です。
インスリンはすい臓で作られるホルモンですが、現在使われている製品のほとんどは合成され加工されたもので、自然のものではありません。注射といっても器具は専用で、ほとんどは使い捨てで、いわゆる注射器の形はしていません。針も先が細くなり(テーパリング加工)、痛みは随分軽くなりました。
補足(平成20年12月)
注射薬を簡単に説明します。注射液をもらったら、箱の中に説明書があるはずです。そこには細かい文字で「半合成~ヒトインスリン~」などと書かれています。これはインスリンの作られ方を説明しています。インスリンの名前はたくさんありますが、長いものでは、例えば「ノボラピッド30ミックス注フレックスペン」という製品もあります。
注射薬の名前は非常に複雑ですが、決まりのようなものはあります。名前にノボ~という文字が入ってたら、ノボという会社の製品であることを意味します。~カート、ヒューマという文字が入っていたら、リリーという会社の製品です。別に意味がないのに、このため名前が長くなっています。統一してくれれば間違いが少なくなるはずです。イノレットとノボリンという言い方は、製品のシリーズで分けたようです。
Rという文字が入っていたら、速効性の成分を含むことを意味します。ラピッド(速い)の頭文字ではなく、レギュラーのRだそうです。30R、50R、ミックスなどの文字が入っていたら、中間型と何かを混ぜた製剤であることを意味します。30や50などの数字は、混合する割合を意味します。製剤ごとに色分けをしてあります。よく薬局でRと30Rを間違える事故があります。製剤の色が違うことに気がついたら、その場で確認しましょう。 Nの文字がついていたら、中間型である(長く効く)ことを意味します。
この中間型という言い方は製剤を作る側の分類で我々にはなじみがなく、しかもニュートラル(中性)の頭文字のNを記号にしてありますが、先程のRと同じく作り手のための区別にすぎず、一般の人には何の意味もない記号です。言い方を変えたほうが安全管理のためにはいいと個人的には思います。
フレックスペン、またはキットというのは、使い捨てでペン型をした注射器であることを意味しています。処方箋にはFPと略する先生もおられるかも知れません。
代表的なインスリン注射製剤(平成20年改定)
|
分類 |
名前 |
形状 |
|
超速攻型 |
ヒューマログ注100単位/ml |
ボトル |
|
ヒューマログ注キット |
ペン形式 |
|
|
ノボラピッド注ペンフィル |
カートリッジ型 |
|
|
ノボラピッド注フレックスペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
ヒューマログ注ミリオペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
速攻型 |
ヒューマリンR注100単位/ml |
ボトル |
|
ヒューマカートR注カート |
カートリッジ型 |
|
|
ヒューマカートR注キット |
使い捨てペン形式 |
|
|
ペンフィルR注 |
カートリッジ型 |
|
|
ノボリンR注100単位/ml |
ボトル |
|
|
ノボリンR注フレックスペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
イノレットR注 |
独特なダイヤル式 |
|
|
ヴェロスリン |
ボトル |
|
|
中間型 |
ヒューマリンN注100単位/ml |
ボトル |
|
ヒューマリンN注カート |
カートリッジ型 |
|
|
ヒューマリンN注キット |
使い捨てペン形式 |
|
|
ペンフィルN注 |
カートリッジ型 |
|
|
ノボリンN注100単位/ml |
ボトル |
|
|
ノボリンN注フレックスペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
イノレットN |
独特なダイヤル式 |
|
|
ヒューマログN注ミリオペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
混合型 |
ヒューマリン3/7注100単位/ml |
ボトル |
|
ヒューマカート3/7注カート |
カートリッジ |
|
|
ヒューマカート3/7注キット |
使い捨てペン形式 |
|
|
ノボリン30~50R注フレックスペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
イノレット30~50R |
独特なダイヤル式 |
|
|
ペンフィル30~50R |
カートリッジ |
|
|
ヒューマログミックス25注カート |
カートリッジ |
|
|
ヒューマログミックス25注キット |
使い捨てペン形式 |
|
|
ヒューマログミックス注25ミリオペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
ヒューマログミックス50注カート |
カートリッジ |
|
|
ヒューマログミックス50注キット |
使い捨てペン形式 |
|
|
ヒューマログミックス注50ミリオペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル |
カートリッジ |
|
|
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン |
使い捨てペン形式 |
|
|
持続型 |
ランタス注オプチクリック |
カートリッジ |
|
ランタス注ソロスター |
使い捨てペン形式 |
|
|
レベミル注フレックスペン |
使い捨てペン形式 |
実際に効果が出る時間は、注射の量や個人の体質によっても随分変りますので、「速効型だから2時間で血糖が下がらないのはおかしい。」とは言えません。
超速効型インスリンの特徴
(製品名ヒューマログ、ノボラピッド)
注射してから30分たたないうちに効果が出る。
そのため食事の直前もしくは 直後に注射する。
仕事の関係で、30分前に注射できない人の場合には便利。
食事の摂取量が分らない時には便利(食後に使えるので)。
効果が長引かない
次の食事前に低血糖を起こす可能性は低い。
逆に、食後に低血糖を起こすことがあります。
効果が続かないので、注射を忘れると血糖値が非常に上がる。 1日1回この注射を使っても、意味がありません。効果がすぐなくなるので、食事ごとに使わないといけません。
速攻型インスリンよりも若干弱いので、量が多めに必要。
値段が少し高めです。
合成されたインスリンなので、細胞増殖作用が本来のインスリンと違う。長期間使うとどのような作用が出るのか解っていない。(アメリカ衛生局でも安全性は認められていますが。)
点滴の中に混ぜる時に便利(結晶を作りにくい)
速攻型インスリン(製品名ノボリンR、イノレットR、ヒューマカートR、ヒューマリンRなど)の特徴
通常は食事の30分前に注射する。
(量が多くなると時間をずらさないといけない場合もある。30単位くらいが境いめになります。それより多いと、注入量が多くなる関係で吸収が遅れてきます。)
皮下注射では30分後くらいから効果が出ることが多い。
超速攻型ほど速く効かない
食後に低血糖を起こすことがある
効果が続かないので、注射を忘れると血糖値が非常に上がる。 半合成だが分子構造は生体と同じなので、比較的安全。
混合型インスリン(たくさんの製剤がありますが、~30R、ミックスなどと書かれています)の特徴
速攻型や超速攻型と、中間型インスリンを混ぜた薬。
混ぜる割合は1対9から5対5まである。
実際には速効性成分が明確に効果が出ないこともある。
注射の回数を減らせる可能性がある。
例えば、一日2回の注射をされている場合には、食後の血糖値もコントロールできる可能性があります。
沈殿している成分があるので、使用前に混和する必要がある。
中間型インスリン(製品名にNの文字が入ってます。ノボリンN、イノレットN、ヒューマカートNなど)の特徴
注射して1時間後~10時間後くらいまでゆっくり効く薬。
濁っている(ゆっくり溶けるように結晶を作らせているから)
使用前に混和する必要がある。混和を忘れると、上澄みだけを注射した場合は全く効果がなく、沈殿だけを注射した場合は激しく効く場合があります。
速攻型インスリンよりも効果としては強い。
注射後しばらくたって低血糖を起こす可能性がある。
低血糖は長く続く可能性がある。
持続型インスリン(製品名ランタス注、レベミル注フレックスペン)の特徴
注射してもすぐに効果が出ないが、一定した効果を示す。
通常は他の薬と併せて使う。
時には単独で使用して有効な場合もある。(導入時など)
寝る前に注射してもらうことが多い。
オプチクリックは特許の関係で、器具が使いにくい。
中間型よりも力としては強い。したがって、Nの文字が入った製剤から切り替えられた方の場合は、急激に血糖値が下がる可能性があり、少し量を減らしたほうが良いこともあります。
低血糖になったら、長く続く可能性がある。
インスリンに共通する副作用
どのインスリンも注射の量や注射時間を間違えれば、強い低血糖がおこることがあります。発疹が出たり、皮膚が厚くなったり、逆にへこんでしまったりすることもあります。
アレルギーが出た時はインスリンの種類を変えるか、減感作をしないといけないことがあります。
皮膚の厚さの変化を防ぐため、注射の場所は一箇所に集中しないようにしなければなりません。注射部が化膿してしまうこともありますので、消毒は念入りにしなければなりません。
インスリンの保管法
およそ醤油と同じと言って良いと思います。光に当たる場所は分解が早くなるので、ダメです。凍らせるのも分解につながります。冷蔵庫の冷気の噴出し口に置いていたら凍ってしまったという話を聞いたこともありますので用心してください。車の中など、高温になる場所も変性すると言われています。体温ではほとんど問題ないらしいと言われていますが、数ヶ月身に着けても大丈夫かどうかは分りません。
封を開ける前は冷蔵室(冷凍ではない)に入れるように勧められていますが、防腐剤の活性の関係で、開封後は室温の方が保存が効くと言われています。
よくある注射方法のミス
インスリン注射は慣れてくると自己流になってしまうことが多いようです。
① 消毒を忘れる
② 混ぜてから使うことを忘れる
③ 試し打ちを忘れる
④ 同じ場所に注射してしまう
⑤ 針をつけっぱなしにする
今後の展望
インスリンに似た作用を持つ物質や、食欲、肥満に直接作用する薬も研究中です。膵臓の中のインスリンを出す細胞を増やす薬が待たれます。結果もかなり出ていますが、評価が定まっていないので省略します。
インスリンと併用する飲み薬の種類は増えましたが、それによって患者全員のコントロールが劇的に改善したという話は聞きません。まだ夢のような薬はできていませんので、治療の基本である食事療法、特に食品の重さを量り食品交換表を参考書にして、カロリーを計算する地道な努力が必要です。
インスリンの器具は、さらに改善されると思います。もっと小さくなるのではないかと思います。不具合が生じている器具も、やがて改良されるでしょう。針は先が細く根元が太い形が出ていますので、ずいぶん痛みが軽くなりました。針なしの注入器具は、今のところ注射の主流にはなっていないようですが、今後は値段も下がって、よい選択肢になるかもしれません。
名称についても危険防止の意味から、もっと統一されるのではないかと期待しております。