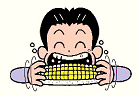低血糖の現状
(低血糖)・・・低血糖への準備が必要・・・
糖尿病のため血糖を下げる治療をされている方は、血糖値が下がり過ぎる「低血糖」への用心が必要です。
低血糖状態では細胞が活動するための栄養源が不足し、様々な生命活動に支障を来たします。低血糖の症状は、軽い動悸や冷汗ですむ場合もありますが、意識消失、呼吸不全、不整脈や心筋梗塞など、致命的な病態が付随することもあります。 神戸の救急病院が救急に訪れる低血糖患者の統計を発表しました(糖尿病55:11;857-865)。
この論文には、低血糖で意識を失った時間が8〜12時間を越えると後遺症を残す傾向があったと書かれています。でも8〜12時間は平均的な数字で、8時間を越えないなら大丈夫とは言えないはずです。後遺症を残す時間的閾値がいずれにせよ、短時間で対処できるように普段から心構えを持つべきです。
高齢者では特に注意が必要で、判断が遅れて重症化する傾向があり、血糖のコントロールの指標であるヘモグロビンA1c(HbA1c)の値で言えば、6%程度に下がった状態では注意が必要と書かれていました。
(HbA1cの目標値)・・・目標達成には能力と準備が必要・・・
血糖は変動が激しいので、食事や薬を上手く調整しないと直ぐ低血糖を起こします。普段の血糖が非常に高くても、コントロール不安定な方では低血糖を起こします。6%以上だから低血糖の心配がないと考えては危険です。
血糖コントロールの目標6%、7%といった値は、学会が推奨する治療上の目標値で、解りやすいようにと数値目標を立てたのですが、強制的に患者さんに求める意図で定めたものではありません。それなのに目標に達することを最優先に考えると、低血糖について充分に理解しているかどうか、対処する能力が充分か、仕事場や家庭の協力体制が充分かの評価を忘れやすくなります。状況の確認がないと、何ごとも危険を伴うものです。
頑張り屋で素直な方は、指導内容以上に食事を制限し、御自分の対処能力を越えて血糖を下げてしまいます。 実は低血糖に関する充分な知識を持っている人の割合は、教育熱心な病院に通院中の患者さんでも数割程度です。そもそも食事のカロリー計算ができなければ食事の調整は無理なはずですが、これもできない方が大半です。したがって、多くの方が危険性をはらみながら治療しており、目標値の示し方によっては低血糖に患者さんを追い込むことになりかねません。
(SU剤への注意)・・・SU剤は低血糖の危険あり・・・
飲み薬のうち、SU剤(オイグルコン、アマリールなど)と言われる薬の占める割合が高い傾向もありましたが、これはまずSU剤が最もよく使われていたせいと思います。作用が長時間続くことや、作用機序も低血糖につながりやすい性格があり、その点から考えても当然の結果でした。SU剤は歴史のある血糖降下剤です。ある程度は定量的に効果が期待できるので使いやすい反面、量が増えるほど低血糖を惹起しやすい欠点はあります。
近年発売されている他の飲み薬は作用機序が異なり、単独で血糖値を正常以下に下げることは稀で、SU剤やインスリンと併用しなければ低血糖を起こしにくいものがほとんどです。逆に言えば、併用の際には細心の注意をはらう必要があります。
このような結果は以前から言われていたことですが、改めて確認できたことになります。オイグルコン、アマリール、グリ〇〇〇ドといった名前の血糖降下剤を飲まれている方は、低血糖への準備を再確認されるべきです。
(低血糖と認知症)・・・低血糖は認知症の危険因子・・・
高齢の糖尿病患者にとって、低血糖は認知症と関連が深いという統計結果もあります(JAMA InternMed online On June10,2013)。 アメリカ人の統計ですが、重症低血糖を経験すると、その後34%ほどが認知症と診断されていた一方で、重症低血糖がなかった方は18%ほどしか認知症にならなかったそうです。これは大きな違いだと思います。さらに、認知症患者さんは低血糖を起こされる確率が14%であったのに対し、認知症でない方は6%程度と、こちらも相当な違いでした。
この統計は70歳以上の方を対象にしていますので、日本では厳格な血糖コントロールを目指すべき対象ではなく、そもそも統計が成立しないくらい低血糖は稀でないとおかしい気がします。8%近くの患者さんが低血糖を発症されていたそうですので、随分と乱暴な治療をされていますが、逆に言えば勇敢に血糖を下げようとしていたとも言えます。若い方でも低血糖が将来の認知症に関係するかは解りませんが、いずれにせよ重症の低血糖を避けたほうが良いことは間違いないはずです。
(血糖コントロールの意義)・・・意義の強調の仕方に注意が必要・・・
以前は治療薬が限られていましたし、低血糖を怖れて血糖値が高いまま放置し、病状が悪化する方が多数おられました。血糖値のコントロールは合併症を予防するために必要です。血糖値を高いままに放置しておくと、血管や神経、腎臓などに障害を起こし、失明、腎不全、末梢神経の痛みや麻痺などの困った状態(糖尿病性合併症)が発生します。 コントロールを厳重にできれば合併症をかなり防げることが証明され、可能なかぎり血糖値を下げましょうと啓蒙活動が行われています。
ところが強調の仕方というのは難しいもので、人の認識を変えるためにあまりにセンセーショナルな表現をとり、血糖値を下げることばかりに意識を集中させてしまうと、強迫観念に捉われたかのように過剰な治療をしてしまいます。その現象に対して啓蒙をした方が責任を持って事後指導をするわけではなく、やりっぱなしになる流れがあります。悪意はなくとも、結果的に患者さんが危険にさらされるのは困りますから、啓蒙の方法には改善が必要かもしれません。
血糖コントロールは重要(ただし重症低血糖を起こさないなら)といった括弧書きをもらさないこと、または「重症低血糖は合併症より危険」と必ずコメントを加えるほうが適切だったのかもしれません。
(薬の宣伝の影響) ・・・宣伝には用心を・・・
薬の使い方に関する警告は度々出ていますが、医者の間でも充分に認識されていません。新しい薬が発売されると、さかんに宣伝されて危険性に目が行かないことを繰り返します。
DPP−4阻害剤という系統の薬が発売された後は、SU剤との併用によって低血糖の発症が多発しました。薬が危険というより医者の処方内容がおかしいと私には思えましたが、相当数の発症があったことから、製薬会社の説明と医者の理解力の双方に問題があったようです。
一般に薬の発売においては発売記念講演などがさかんに開催され、権威のある有名な先生を呼んで効果が発表され、興味を持つ医者が薬を試したいと考えるようになります。DPP−4阻害剤についても宣伝が繰り返されたので、時流に遅れたくない意識は働いたと思います。でも本来は、新しい薬については慎重さが必要です。警告が出され、それ以降の低血糖は減っているようですが、それでも皆無ではありません{糖尿病56(5):277-284}。
(低血糖の意味への理解)
低血糖が怖いことは常識ですので、本来なら病院や患者は警戒し、滅多に重症の低血糖は発生しないはずです。誤解、不勉強、宣伝など様々な要因によって、残念ながら稀とは言えない発生があるのは残念です。
経口糖尿病薬の使い方には文章を読んだ知識だけでは把握しにくい、微妙なセンスが要求されます。専門医が極めて高名でも、責任感や危機意識、センスは別ものですので必ずしも信頼はできません。
飲まれる患者さんの側にも、知識と対策が必要です。血糖降下剤を飲まれている方、インスリン治療をされている方は、御自分の血糖コントロールが望ましい状況かどうかに注意するとともに、低血糖の危険性がどの程度あるかについて、たびたび主治医に確認すべきと思います。
診療所便りより (2013.08.31up)