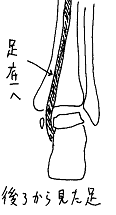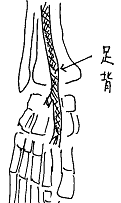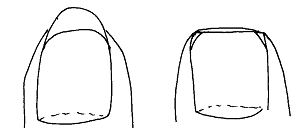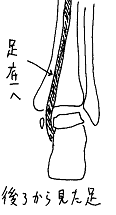
糖尿病性壊疽の予防 勉強会資料 平成22年3月31日
A 糖尿病壊疽とは
壊疽は、おおまかに言うとバイキンが付いて障害をきたした状態です。今までの勉強会では壊疽の写真をお見せしていましたが、何度見ても気持ちのよいものではありませんので、ここでは省略します。
感染や血行障害によって、皮膚や近くの組織に壊死(組織が死んでしまったような状態)、融解(肉が溶けたような状態)部分、潰瘍(穴が開いて窪みを作った状態)などを作った状態を差します。皮膚ばかりでなく、骨や筋肉などの組織もやられることがあります。
糖尿病以外の理由で壊疽ができることもあります。激しい外傷や血管が詰まってしまう病気(閉塞性動脈硬化症、バージャー病、血管炎)です。動脈塞栓でも同じような現象は起こりえます。
特に「糖尿病性」と断り書きがつくのは、糖尿病患者さんに独特の形で壊疽が起こりやすいからです。糖尿病患者さんの壊疽は、大きな血管が詰まっていなくても発生することや、治りにくく進行しやすく、再発しやすいことが特徴です。
B.壊疽の好発部位
壊疽が発生するのは足の先です。小指の外側、かかとなどが代表です。
理由
①通常、末梢神経障害は足のほうに進行が速い傾向がある。(単純に足の神経が長いことなどが関係しているかも知れません)
②足の血流を遮断してしまう危険が腕よりも多い。(足は姿勢によって直接血管を圧迫したり、加重がかかったりする)
③足は怪我の程度が強くなりがち(手は目で見て簡単によけられるが、足は視野の死角となりやすい)
理屈から言えば、手の先や腸などにも同じような病変を作りそうですが、私は手に発生させた患者さんを数人しか見たことはありません。これに対して足の壊疽の患者さんは数十人に上ります。足のほうが断然多いと思います。
血液の中には、虫歯などから細菌が紛れ込むと思われます。ほとんどは免疫で退治されるはずですが、中には敗血症(血液中に菌が残る状態)になる人もいます。その場合は、どこに壊疽~膿瘍などを作ってもおかしくありません。
壊疽という言い方は、表面に見える感染巣を差しますので、膿が溜まった状態を含めれば全身いたるところに発生しうると思います。
もしかすると「腸炎」などと診断された患者さんの中に、本当は腸の血管が詰まって壊死を起こしそうになっていたけれど、たまたま血流を維持できて、症状がはっきりしなかった患者さんがいるのかも知れません。
肝臓に膿瘍(膿が溜まった状態)を作った患者さんは、血管の閉塞が引き金になっていたのでは?と推測される場合があります。肺炎も同様です。膿瘍を作ってしまった後では、何が引き金だったか解らないからです。本当は足以外にも、結構別なところで壊疽のなりかけが発生しているのかも知れません。
でも、問題になるのは足です。場所が限られているので、予防のために観察するのも通常は足のみでよいことになります。
C.壊疽の危険因子 (壊疽を起こしやすくする原因)
バイキンが付くこと、血流が充分でないこと、免疫が充分に働かないことが壊疽を起こしやすくします。
①バイキンが付きやすい状況
足の傷、特に傷に気がつくのが遅れて感染巣が大きくなってしまった場合は、壊疽になりやすくなります。したがって、そもそも足を不潔にしていた場合、水虫を悪化させた場合、足の裏が極端に乾燥していてヒビ割れが起こりやすい場合も、壊疽を起こしやすくなります。
②血流が充分でない状況
お腹の中で大きな血管が足に向かって枝分かれします。この付近で血管が細くなると、歩いていると足が痛だるくなり、休むと楽になる症状(間歇性はこう)が出ます。そして進行すると、足の色が悪くなり、さわると冷たく感じるようになります。
足の近くになると、足底と足の甲に図のような血管が走りますが、細い血管なのでよく詰まります。若い人は、ここを押えると脈を触れますが、老人では触れない人が多くなります。ここが触れないということは、お腹からここまでのどこかで血管が細くなっていると考えられます。
血流が悪くなった場合、壊疽になる危険は通常より高いと言えると思いますが、すぐ薬を飲まなければならないということはありません。でも、他の人よりは用心が必要でしょう。
タバコは強力に動脈を傷めます。血圧などに何の問題もない人でも、タバコのために心筋梗塞を起こす率が増えますが、足の血管が詰まってしまうこともよくあります。この悪い影響は、糖尿病や高血圧よりも強力だと思われます。
動脈硬化のために血管が細くなることはよくあります。高齢者にはほとんど例外なく動脈硬化がありますが、糖尿病や高血圧などがあると、その進行が早くなります。血糖コントロールが悪い、血圧が高いなどによって動脈が細くなっているかもしれません。
足の動脈以外に、静脈やリンパ管の流れが悪化した人を見かけますが、蜂か織炎やリンパ管炎などという感染症を起こす例もありますので、動脈硬化ほど直接的原因ではないとしても、これも壊疽の原因になると思います。
③機械的な圧迫
脳卒中や骨折のために柔軟に足を動かせなくて一箇所に圧が加わってしまう場合、靴の形やサイズが合わなくて靴擦れを起こしやすい場合、そしてウオノメ、たこがあり、さらに自分でこれらを削ろうとして傷を入れてしまった場合は、危険は非常に高くなります。
④神経障害がある
感覚が鈍くなると、足の傷に気がつきにくくなります。
⑤視覚障害がある場合
視力も落ちている場合は、傷の判断が難しいため壊疽にも気がつきにくくなります。
⑥栄養状態が悪い
栄養不足の状態では免疫を担当する細胞の数が減り、おそらく機能も落ちると思われます。褥創を作った患者さんの治り具合は、栄養状態が良い人のほうが断然早いと言えます。ただし、糖尿病の患者さんの場合はカロリーを増やした場合には、それに見合う血糖コントロールの対策も必要です。
⑦血糖のコントロールが悪い
これも栄養状態が悪いのと同じように、免疫細胞の働きに関係すると思われます。非常に複雑な理由によるようですが、とにかく血糖値をコントロールしないと傷が良くならない傾向はあります。
D.壊疽の経過
壊疽を形成すると、中心部に溶けた組織と細菌と繊維細胞、炎症細胞などが混在した状態(膿)が溜まります。膿の周辺には細胞が防波堤の役割をして、菌が周りに拡がらないように壁を作るような反応が起こります。
壊疽の場合は、防波堤が壊れるような感じで、この膿が流れ出していきますが、体の中深くにできた場合は、周辺の組織を巻き込んで、大きく深く進展することもあります。その場合は、壊疽というより「膿瘍(のうよう)」という言い方をします。
指の先全体が壊疽になった場合は、指自体が脱落することもあります。
筋肉表面の膜にそって早いスピードで菌が拡散して、炎症が広範囲に拡がってしまうことがあります。「壊死性筋膜炎」と呼ばれています。半日くらいで足全体に菌が拡がった時は、急いで治療をしないと体全体に菌が回ってしまい命に関わります。
膿が流れ出した後、自分の免疫のほうが菌の勢いよりも強い場合は肉が周りから盛り上って、そのまま傷を塞いでしまいますが、菌の勢いが強い場合は膿が溜まっては流れ出し、カサブタができては破れるということを繰り返し、慢性化します。
E 壊疽の治療
壊疽になった場合、治療を病院にまかせたほうが良いと思います。下手な処置をして、足を切断するようなことになったら大変だからです。病院では、およそ以下のような手順で、治療の反応と傷の経過を見ながら対処しています。
①壊死性筋膜炎などで進行が早いと判断したら、除去が原則。
②膿が溜まっていたら、排膿して洗浄(菌を減らす)
③感染している菌を検査して、抗菌療法
④栄養状態、血糖コントロール状態を改善
⑤肉が盛り上ってきたら、肉の定着を促進
壊疽の治療法には進歩が予想されます。
再生医療と言われる技術が進歩してきました。文字通り組織を再生させる治療法です。おそらく再生医療が進歩すれば、まず血流を保つ技術が進むと思われます。すでに閉塞性動脈硬化症の患者さんに血管のもとになる細胞を注入してやると、新しい血管が発達することが解っています。壊疽の患者さんにも応用できそうです。おそらく治療に要する期間が短くなるでしょう。
壊疽で足を切断した患者さんは、その後長く後遺症で苦しみます。でも、せめて失った足の一部でも再生できれば、少しは歩きやすくなるのではないかと思います。形まで元通りにするのは無理だとしても、骨のもとになる細胞を使いながら徐々にもとの長さに近づけることは可能になると思います。
ただし、期待しすぎてもいけません。予防が第一です。
F 壊疽の予防のための原則
①血糖コントロールを保つこと
壊疽の場合には、血糖コントロールをつけるためにインスリン治療を始めることが多くなります。そのほうが代謝の状態が正常化し、免疫細胞が活発に活動して菌を殺す反応がよくなると考えられています。
②動脈硬化を予防する
もしタバコを吸っていたら、ぜひとも禁煙すべきです。タバコは、せっかくの糖尿病の治療を無駄にします。血圧やコレステロールの治療も厳格にしておくと、血管が傷むのを抑えてくれると期待できます。
③怪我しないように注意すること
ケガは壊疽の引き金になりますから、可能な限り予防したほうが良いと思われます。もしケガをしても、速やかに治療できれば壊疽までには至らないで済ませることは可能です。そのための注意点としては、
☆★毎日足を観察する☆★
自分で観察するのが難しい人の場合は、家族に観察してもらうこと
傷を早く見つければ、早く対処することが可能
☆★素足で歩かない☆★
室内でも靴下~スリッパなどを履いて傷を予防する
靴は足にあったものを選ぶ(靴擦れ予防)
指の部分が横に広い「幅広設計」を選ぶ、格好にこだわらない
☆★外出の際には靴下、靴が原則☆★
サンダルや下駄では、ちょっとした擦り傷を作る可能性がある。
☆★巻き爪を予防する爪の切り方を心がける
ストレートカットと言われるやり方(図示)が推奨されています。実際に爪を真横に切ることはできないので、若干の修正が必要。
☆★かかとを乾燥させすぎない☆★
乾燥させすぎると、足の底の皮にヒビが入って、そこからバイキンが付くことがあります。予防のためにクリーム類が必要な場合もあります。
☆★水虫の治療をする☆★
水虫を作るのは真菌ですが、その菌がそのまま壊疽をきたすことは多くはありません。通常は水虫でただれた部分からバイキンが侵入してしまうことがほとんどです。足を濡れたままにしないこと、指の間にただれたような部分を作らないように早めに治療することなどがお勧めです。
爪の水虫の場合は、なかなか治療が厄介ですが、腎臓や肝臓の機能に問題がなければ飲み薬で完全に治療することも可能です。
☆★やけどを起さないように注意する☆★
①やけどと壊疽の関係を理解する
やけどを起した部分の表面の皮膚は水泡を作り、ただれてしまいます。正常な皮膚からは簡単に病原体が侵入することはできませんが、ただれてしまうと病原体がついてしまい、そのまま壊疽を形成していきます。
②低温熱傷(ていおんねっしょう)に注意する
やけどは熱湯を浴びるか火遊びの火が燃え移ることで発生することが多そうな気がしますが、実際に壊疽になるのはアンカやファンヒーターの風など、比較的温度が低いものが原因であることが多いようです。「熱いもの」ではなく、「暖かいもの」です。暖かい程度なら安全であるかのような気がして、ついつい注意が不足してしまうのかも知れません。暖かいものでも、長い時間触れていると耐え切れないほど熱くなります。ところが感覚がしびれてしまった場合には、この「耐え切れない」という限界が当てになりません。
③アンカを使わないこと
長い時間熱せられると、アンカでも充分にヤケドします。「あなたは神経障害があります」「あなたは血糖コントロールが良くありません」「病気を発症して10年くらい経った」という方は、もうアンカは使わないほうが良いでしょう。
④ファンヒーターの熱風を浴びない
熱風を直接浴びないことも大事です。神経障害がある方の場合は、熱いと感じるのが遅れてしまいがちです。ファンヒーターを使われてもいいのですが、離して使うことは大事です。おそらくハロゲンヒーターもファンヒーターと同じような注意が必要で、あまり近づけすぎてはいけないと思います。
⑤風呂の温度に注意
温水器の湯温を上げたままでいることに気づかないで湯を出してしまうことがあります。また、追い炊きのスイッチを切り忘れて熱湯になっている可能性もありますから、手で確認してから入る等、細かい注意が必要です。「タイマーを入れているから大丈夫」と、思っていたらタイマーが故障していたということもありえます。
⑥その他
岩が太陽の熱で高温になっている場合があります。プールで子供達の世話をしている時に、周りのコンクリートや金属製の部分でやけどをする例もありますので、状況を考えて利用しましょう。美しい女性の水着姿に見とれていると、壊疽を作るかも知れません。