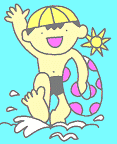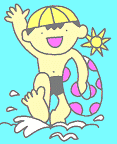脱水と注射
気温が上がっていく時期は、体が慣れてしまう前は簡単に脱水状態になりますが、連日暑い日が続くと、なぜか慣れる傾向を感じます。同じ動作、同じ飲食をしても、我々の適応力が変化するからのようです。
適応力が何によってもたらさせるのか詳しくは知りません。血圧や利尿に関係するホルモン、ミネラルの出入りを調節するチャネルと言われる細胞膜上の蛋白構造、水分の摂取量と摂取のタイミングなどかと想像しますが、元気なスポーツ選手が突然倒れるのまで予測するのは難しいことです。眼に見える指標はそれほどありませんし、自覚症状もはっきりしないことがあるようです。倒れた人に後でお聞きしても、いつもと同じように感じていたとおっしゃいます。
アフリカで激しい脱水症状を起こした子を対象に、生理食塩水などを注射した場合の効果を調べた報告が発表されました(N Engl J Med2011;364:2483-95)が、意外にも注射をした子の方が死亡率が高いという結果でした。
アフリカと日本とは状況が全く違いますので一概には言えませんが、一般に血管の中に何かを入れる場合は、慎重さが望まれます。内容、量、投与の早さとタイミングなどに注意しないと、心不全などの害が生じます。 そもそも近年は「注射」という行為自体が少なくなっています。急激な反応を少しでも避けるために、ゆっくり注射する「点滴」で観察するのが原則です。点滴も百パーセント安全ではありませんが、反応が少し穏やかになれば対処する時間をかせげる点で有利です。
この試験では、注射をされた子のほうに肺水腫という副作用が増える傾向がありました。肺水腫は肺の水分をスムーズに回収して全身に送り出せない状況で、ほとんどの場合は心不全と同じ意味です。おそらく注射のスピードが速すぎたか、注射した内容が濃すぎて心臓の負担になり、循環機能の余力を超えてしまったようです。
人の循環動態は繊細で、ただのポンプとパイプでできた回路とはわけが違います。反射やホルモン、腎臓の機能などで調節されています。 良い内容の液であっても、急速な注射は危険です。少量の注入に対して起こる反応を確認し、適応を待ってまた注入して・・・という確認、観察の繰り返しは必須です。「水分が足りないんだから、さっさと注射しろ!」といった短絡的な考え方はよくありません。
短絡的といえば、”浸透圧利尿”という理屈に基づく治療薬も害が散見されます。浸透圧利尿は血液の濃度を上げて浮腫みを取ろうという治療です。脳卒中では脳の浮腫みを取る標準薬として使われます。海外の報告では今回の発表と同じような害が目立つので、使用を制限する考え方も拡がりつつありますが、国内では脳浮腫の場合に多用され、致命的な害を生じたと疑われる例もあるのが現状です。
おそらく、年齢やGFR(腎機能)によって最初から薬の量を調節する、短時間に反応する心不全の指標(ホルモン値や心臓の拡張の具合)などに従って、速やかに対処すれば害を防げるのではと思いますが、運任せで投与されています。今回の試験と同じような誤りだと個人的には考えています。
平成23年8月診療所便りより(2011.08.31up)