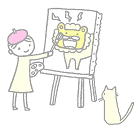特定健診の結果は国に送られ、医療費削減や健康増進のために使われる計画でした。ところが、データの8割は使えないままであることが明らかになりました。
理由は、データの文字の違いに対応していなかったからのようです。私もよくやるような、初歩的なミスと思われます。問題は3年前から明白だったのに、対策はとられていなかったそうです。
おそらくデータは工夫次第で、まだ使えるはずです。入力データの形式を調整するソフトなど、作れないとは思えません。税金を使っているのですから、予算を無駄にして欲しくありません。健診の効果を確認し、是正すべき点を明らかにすべきです。まさか、問題点が明らかになるのが怖いから放置したということはないはずです。
活発な研究者
糖尿病関係の論文を活発に発表する研究者は、製薬会社に雇用されていたり、密接な関係を持つ傾向がある、そんな内容の統計が出ました(BMJ2015;351:h2638)。
医療に限らず、どの分野でも、選ばれた専門家は業界に都合のよい内容を話す傾向があります。 政府主催の委員会には、なぜか政府関係者と仲の良い学者や、利益に関係しそうな業界団体の人が入って、反対意見の人が最初から少数派になっている印象があります。どんな基準で、誰が専門家を選らんだの?と気になりますが、選ぶ時点で紛糾するので、まともな手続きができないのかも知れません。
選ばれた人間は箔がついて有名になり、いろいろな場所に呼ばれ、評論活動などを通じて実利を獲得する傾向もあります。ただし、国立競技場やオリンピックのロゴの騒動を見るように、よろしくない判断を下す専門家はいるようです。選ばれたから偉い、優秀で間違わないとは限りません。強引な議事運営、不誠実な利益誘導を疑われる事例は少なくありません。
糖尿病の薬の場合、薬が血糖値を下げる効果を強調した論文が発表されると、製薬会社はそれを宣伝に使います。結果をパンフレットに写し、薬の有効性を強調して処方してもらおうと、宣伝員が活動をしています。雑誌にも広告がたくさん掲載され、テレビや新聞でも派手な表現で解説されますので、薬を使わないと遅れてしまうような感覚が生じ、結果として売り上げにつながります。
発表した研究者は会社と良好な関係を築き、薬の評価に関わる機会が増えます。様々な開発研究に名を連ねるので論文も多数になり、際だって活動的な印象につながります。会社からの寄付も得られやすくなり、資金的に豊かになって仕事も増やせる好循環にもつながります。この論文を見ると、そんな仕組みが数字にも出ているようです。
発表内容に誇張や嘘がないなら、研究者達の利益を気にする必要はありません。ただ、誇張が巧妙になされると、簡単には見抜けません。 宣伝方法に関して有名になったのは、血圧の薬ブロプレス錠とディオバン錠です。会社の関係者がグラフの線を微妙にいじって差を大きく表現しようとしたのではないか、研究の集計を担当し、都合の良い結果が出るようにデータをいじったのではといった疑いがもたれています。会社は何でもやると考えたほうが良さそうです。
そのような不正、あるいは怪しい行為に荷担することがないよう、研究者や学会関係者、雑誌関係者には高い倫理面の意識が必要と思います。 でも、この論文を読む限り、それは難しいことなのかも知れません。こちら側としては、せめて話上手な発表者やセールスマンに騙されないように、よく勉強しておく必要があると思います。
診療所便り 平成27年11月分より・・・(2015.11.30up)
少し誇張