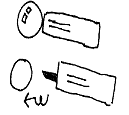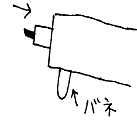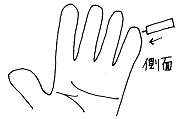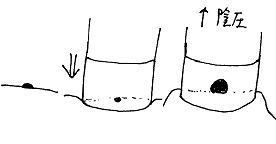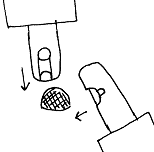血糖自己測定について 勉強会 平成19年10月18日
講師 橋本 泰嘉
血糖自己測定とは
文字通り、血糖値を自分(または家族)で測定することです。英語ではSMBGと略します。
測定する機械の性能が上がったことから、病院に行かなくても簡単に測定することができるようになりました。ただし、健康保険を使えるのは、インスリン注射をしている方だけに限定されています。食事療法や飲み薬だけで治療している方の場合は、もし測定するなら全額自分で購入しないといけません。その点が問題ですが、もし自己測定ができれば自分の病状を把握することができますので、治療のレベルが上がります。
血糖値は変動が激しいので、一回測った値によって一喜一憂しても意味がありません。繰り返し測定して変化を知って始めて意味が出ます。また、値を速やかに調べないと低血糖などの緊急の場合などは非常に困ることになります。このような意味から、自己測定をお勧めします。
血糖の検査法いろいろ
血糖コントロールを知る方法には、
①
血糖値を病院で測定してもらうこと、
②
ヘモグロビンA1cなどを検査してもらうこと、
③
尿糖を調べること、
④
そして血糖値を自分で測定すること(SMBG)
の4通りの方法があります。病院で測定した血糖値は、その時々の食事内容で変化しますので参考程度の意味しかありません。ヘモグロビンA1Cの場合は1ヶ月くらいの血糖値の平均的な状況を知るのには便利ですが、測定した時が低血糖か高血糖かの判断には役立ちません。尿糖検査は血糖値が非常に高い時には陽性になりますが、低血糖の判断には役立ちません。繰り返し実際の生活の中で測定できれば、それが最も血糖値を把握するのに役立つ方法です。
尿糖と血糖値の関係
自分で血糖の状況を検査する方法に、尿糖の測定があります。以前は多くの患者さんが尿の検査紙を薬局で買って検査していました。尿検査は、今でも意味があります。トイレに検査器具が備え付けてあるものもあったくらいです。検査する際に痛くないのがなんと言っても良い点です。ただし、血糖値が160~170くらいまでは尿糖が出ないことも多いので、空腹の時間が長かった後の尿を検査しても意味がないことも多いのが問題です。また、血液から尿に糖が出て膀胱にたまるのには時間がかかるので、今の血糖値と尿糖とが食い違う結果になることも少なくありません。尿糖が出るようでは基本的に血糖値が良いはずはないので、要するに自分が非常に悪い状態であるかを確認することしかできないというのが、尿糖検査の限界でしょうか。
血糖自己測定の意味(効果)
血糖値が変る様子を実感し、病気への理解が深まる
血糖値の管理のレベルが上がる
血糖値の目標を下げることが可能になる
合併症を減らすことが可能
妊娠や出産を可能にする
低血糖や高血糖を確認できる
確認することで不安感を減らすことができる
入院の回数を減らすことができる
血糖自己測定のやり方
機械によって使用法は随分異なりますので、詳しくは各々の説明書を読んで確認して下さい。ここでは各製品にほぼ共通することを述べます。
①
まず手を洗います。少しでもバイ菌から身を守るためです。洗った後は、濡れたままではいけません。水分が血液と混ざって、低めの結果がでることがあるからです。
②
測定の器具を調整します。まずは針と穿刺器具ですが、一般に図のように針をねじ切るタイプが多いようです。針を器具に取り付けた後で頭部をねじると、中から針が出てきます。一体型の器具の場合は、ねじ切る必要はありません。
③
穿刺器具の多くは、バネ仕掛けで針を打ち出します。レバーなどを使って、バネをかけてください。キャップをかぶせて、針が飛び出しすぎない様にします。
④
針の刺さる深さを調節できる器具がほとんどです。針の根元にダイアルがあれば、それを回して自分の皮膚の状況、穿刺する場所に応じて深さを調節しましょう。通常、指より腕のほうが深く刺さないと出にくい傾向があります。
⑤
穿刺する場所を決めます。手の指なら側面がお勧めです。物に当たる場所より、当たりにくい場所を選びましょう。人によっては爪の間や、指の腹を選ぶ人もおられるようですが、なるべく痛くなくて汚れにくい場所を選んで下さい。
⑥
手掌や腕を選ぶ場合も、なるべく汚れにくい場所を選び、血管を避けるように注意して下さい。器用な人は、耳たぶなどからも採取できます。
⑦
センサーを測定器具にセットします。セットの仕方はいろいろですが、普通はセンサーを袋から出して、強く圧迫しすぎないように注意しながら機械に入れます。強く持ちすぎると、自動的に測定を始めることがあります。また、センサー挿入部にゴミが溜まったり電極がすり減っている場合にも自動的に測定を始めることがあります。掃除などで調整できない場合には、機械を交換するしかありません.
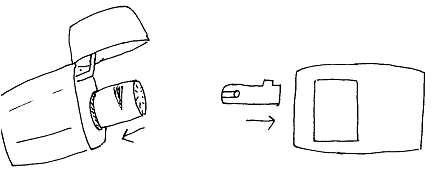
センサーを入れると自動的に「血液を付けなさい」などの表示がされると思います。音も出るでしょう。
⑧
アルコール綿などで消毒します。この時も、消毒液が充分に乾いた後で血液を採取するようにしてください。
⑨
穿刺器具を当てて、穿刺してください。しわの多い場所は、しわに沿って血液が拡がって採取しにくいことがありますので注意して下さい。
⑩
血液量が少ないか、しぼり過ぎた場合は値が低くなる傾向があります。腕などのしぼりにくい場所で血液が充分に出ない場合は、吸引する器具を使う手もあります。自動で吸引してくれる器具もあります。
⑪
指から採取する場合は、心臓より低い位置に指を下げることが原則です。その位置で、穿刺した場所に向かって他の指を使って血を集めると、たいていは充血します。その状態で、さらに穿刺した指を曲げると充分な血液が出てきます。これでも出ない場合は、正確に測るために穿刺をやり直したほうが良いでしょう。
⑫
センサーを測定器につけた状態で、センサーの吸引部に血液を触れさせます。センサーが自動的に血液を吸引して測定を始めるでしょう。
⑬
値を確認したら、血液を消毒綿でふき取り、センサーは廃棄、結果は何らかの形で記録しましょう。穿刺針は、一般のゴミといっしょにしないようにして、できれば病院に持ってきて下さい。病院で捨てます。
⑭
センサーを抜き取ると、自動的に機械の電源が消えるものがほとんどです。値を自動的に記憶してくれる機械もありますが、病院が解りやすいように、手帳などに書いていただけると助かります。
血糖自己測定の回数、測定する時間
測定する回数や時間に決まりはありません。その人の時間の許す時に、最小限の回数で測定していただいて良いと思います。可能ならば、病院に入院して検査してもらう時のように、一日の食事前後と寝る前の測定をして欲しいのですが、毎日それを繰り返すのは時間に余裕のある方でないと無理でしょう。
通常は、外来に来ていただいた時に、「今度は朝食前を中心に測って下さい。」「今度は寝る前を中心に測って下さい。」などと勧めます。患者さんによって、また治療法によってポイントが異なりますので、最小限の検査でポイントを押えるように工夫しております。測定していただいた結果と、病院での血糖値、HbA1cなどの値を総合して次回の測定を決めていくのが通常のやり方です。
血糖自己測定の費用
インスリン注射をされている患者さんは、血糖自己測定の際の測定紙(センサー)に保険が効きます。注射をされていない患者さんは保険が適応されませんので、センサー1枚100円くらいの実費を払って購入しないといけません。
さらに測定器自体は治療法に関係なく全額自費の負担が必要です。以前は検査機械の会社の方針で機械については無料で分けてもらっていましたが、厚生省の方針で有料になってしまいました。厚生省にも言い分はあるでしょうが、結果として患者さんのためにはなっていないように思います。
測定器は値段が1万~3万円くらいです。高いものが特に正確だとは言えません。
血液を採取する器具にも保険が効きませんので、これも自費で購入する必要があります。これは故障が少ないので、新しい機械を買ったからと、わざわざセットで購入する必要はありません。多くの場合は、故障した時に病院から分けてもらえるかも知れません。(病院の方針にもよります)採取する時に使う針は保険が効きませんが、多くの場合は病院がサービスで提供してくれます。院外薬局からもらっている場合は購入しないといけないかも知れません。
血糖自己測定器
測定器にはたくさんの種類があります。性能に多少の差がありますが、日常の使用にはほとんど困らないレベルになっています。下の図に現在宣伝されている商品をまとめましたが、この他にも使用可能な製品はたくさんあります。
|
名前 |
測定時間 |
場所 |
センサー名 |
特徴 |
|
フリースタイル(フラッシュ) |
7~15秒 |
手のひら、腕、指 |
ニプロフリースタイルセンサー |
検体量が少ない |
|
メディセーフミニ |
? |
指 |
メディセーフチップ |
|
|
アキュチェックアビバ |
5秒間 |
手のひら、腕、指 |
アキュチェックアビバストリップス |
貧血、低温の際も測定可能 |
|
アキュチェックコンパクトプラス |
5秒間 |
指? |
アキュチェックコンパクトドラム |
17回分の試験紙を収納 |
|
プレシジョンエクシード |
5秒間 |
手掌、腕、指 |
スマートブルー |
液晶画面が見やすい |
|
グルテストエースR |
15秒間 |
指 |
グルテストセンサー |
温度センサー付き |
|
グルテストNeo |
15秒間 |
指、腕、手掌 |
グルテストネオセンサー |
採血量が少ない |
|
アセンシアブリオ |
10秒間 |
指 |
アセンシアイージーフィルセンサー |
見やすい |
|
アセンシアブリーズ |
10秒間 |
指 |
オートディスクセンサー |
10回分の試験紙を収納 |
|
ワンタッチウルトラ |
5秒間 |
手掌、腕、指 |
LFSクイックセンサー |
|
検査時間は気にしなくてよいと思います。採血量が少ない機械は、指よりも痛くない手掌や腕からの採血を可能にしましたが、誰でも採血できるとは限りません。皮膚の血流の状況によっては、吸引しても採血できない人もいます。
血糖値の記憶機能がついた機械も多いのですが、通常は手帳に値を記録して見せてもらうことが多いので、必ずしも記憶機能は必要ありません。
センサーを10個~17個内蔵できるタイプの製品もあります。持ち運びには多少便利です。血液が機械や指につく危険性も少し減ります。
皮膚の穿刺器具
血液を採取する器具もたくさんあります。こちらは壊れにくいので、測定器の会社の製品をわざわざ購入する必要はありません。大きく分けると、指専用のものと、腕や手掌にも使えるものがあります。皮膚を針で刺した後に、陰圧をかけて血液を吸引するための補助具もありますし、それが最初から一体化した器具もあります。個人の皮膚の状態によって、向き不向き(値が出ない人もいます)があるようですので、病院で試してから購入したほうが良いでしょう。
測定誤差の問題
血糖測定器は年々性能が良くなっていますので、一般家庭で測定する場合に性能の点で困ることは少なくなりました。しかし、時に誤差が問題になります。それにはいくつかのパターンがあります。
A)血液の採取量が少ないと値が小さくなりやすい。
血液量が少なくても機械は自動的に作動して測定を始めますので、値が出たから常に正しいとは限りません。血液の出が悪い時には、無理にしぼると血液以外の成分が入ってきますが、この時も値が低く出る傾向があります。
B)気温の問題
機械を低温の場所に置いていた場合は、値が不正確になる可能性があります。温度補正をしてくれる機械もありますが、それでも冷たいところから出してすぐ測定したのでは補正しきれません。気温が零下になるような場合には、ある程度暖めないと信頼できる値が出せないかもしれません。
C)センサーの問題
点滴をしている最中には値が不正確になる可能性があります。点滴中の糖分の中には、ブドウ糖以外の糖が含まれている可能性がありますが、時に測定器に反応して値が高めに出ます。また、血液中の酸素濃度が極端に高い場合は、値が狂うこともあります。御家庭で問題になることは少ないと思いますが、病院で動脈から測定した場合は狂います。農薬中毒の治療薬などの薬剤で値が狂うこともあります。
D)経年的変化など
もともと機械は通常の血糖値を測ることを目標にしていますので、値が100くらいの血糖値は正確に測れますが、極端に高いか低い値では正確に測れません。さらに、機械ですから年々狂いは生じていきます。2~3年でほとんど使い物にならないくらい狂うこともあります。定期的に補正用のチップで確認し、あやしいものは交換するようにした方が良いと思います。