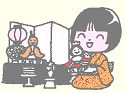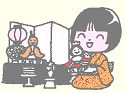花粉症の治療は、抗アレルギー薬の内服が基本です。でも最近、外用薬の性能が良くなり、内服薬を必要としない方も増えてきました。
抗アレルギー剤は、眠気や倦怠感の副作用と治療効果との調節が難しい場合もあり、副作用が気になって薬が充分に効かない印象を持たれる方も多かったはずです。
外用薬にも欠点はありますが、体内に吸収される薬物量が少ないので、基本的に飲み薬より体への負担が軽いと考えます。個人的な意見で一般的なコンセンサスを得た考えではありませんが、外用薬を中心とする方向に指針を改めるべきではないかと思います。
リウマチ因子
人間ドックの検査項目の中に‘リウマチ因子〜リウマトイド因子〜RF定量’などと呼ばれる検査が入っていることがあります。高い値が出る人は多く、結果を持って来院される方も珍しくありません。 リウマチ因子が高いとリウマチではなかろうかと気になるでしょうが、必ずしもそうではなく、参考資料のひとつと考えるべきです。
リウマチ因子は免疫反応の中で形成され、測定方法が以前から決まっているので比較的簡単に検査できます。高齢者の数十人に一人は陽性です。逆に早期の関節リウマチの場合、半分くらいの方は正常値(陰性)だそうです。したがって、診断に使う場合に当てにならないことがあると言えますが、リウマチの病状と数値がよく連動することもありますので、全く意味がないとは言えません。
リウマチの診断基準の項目にも入っています。 ただし、リウマチは診断の仕方が単純ではなく、リウマチ因子が陽性となることは必須の条件ではありません。
健診でリウマチ因子を測定する根拠は、私には判りません。健診だから自由でいいのですが、意味を受診者が理解できている必要はあります。 一般的には関節炎の症状がある方にしか検査する意義はないように思いますが、複数の健診施設で検査項目に加えてあり、自動的に判定されます。稀には検査をきっかけに何かの病気を発見できる可能性はありますので、全然意味がないとは言えないでしょうが、誤解を生みやすいので止めて欲しいと個人的には思います。
本当に微妙な症状の場合は、健康保険を使って他の検査をします。代表的なのは抗Ccp〜環状シトルリン化ペプチド抗体と呼ばれる検査です。こちらは特異度(精度)の高い検査ですが、値段の関係か健康保険組合から認められない場合もあるようです。繰り返しの検査も、原則として認められていません。
平成25年診療所便りより (2013.03.31up)