「国家の品格」
最近、医師会の先生の勧めで、「国家の品格」(新潮新書 藤原正彦著)を読みました。タイトルを聞いた時は国粋主義の本かと思いましたが、教育についての本でした。
弱い者いじめは良くない、人の迷惑になることはしないなど、基本になる情緒的な面を大事にしないと良い社会にはならないというのが主題です。理屈ばかり立派でも根本にこのような情緒がないと、理屈で正当化して変なことをやってしまう事例があることは確かに感じます。少し偏りのある内容ですが、一読の価値はあります。
塾通いを教育のように思いがちですが、根本にしっかりした情緒がないと変な理屈がまかり通ってしまうと思います。
耐性菌について
最近の感染症の原因菌は抗生物質に耐性の菌が多くなっていますので、昔からの飲み薬では効果があがりません。耐性菌が多いのは、おそらく抗生物質の使い方や、病院での待合の仕方、塾や学校での手洗い不足に原因があると思います。待合が幾部屋かに分かれていない病院は、それだけで注意が足りないと思います。
たくさん薬をもらうと安心しますし楽にはなりますから、早く楽になることを優先すると、薬が強い病院ほど患者さんが集まり、そこで耐性菌をもらう可能性も高くなり、結果として患者さんが耐性菌を作って拡げます。病院で耐性菌をもらったなら病院の管理が良くないからだと思われるかもしれませんが、患者さんが持ってこられる耐性菌を全て除菌することなど出来るわけがありません。皆さんを良くする代わりに、どこかで弱った方を死なせているというのは決して言いすぎではありませんので、薬の適正な使用を皆さんにも考えていただきたいと思います。
耐性菌を作らないための原則は、①必要な時以外は抗生物質をもらわないこと。②抗生物質が必要な時は充分量を計画的に使うこと、③抗生物質は勝手に減量したり中断したりしないこと、④必要な場合は菌の確認を怠らないこと、⑤痰、鼻汁をこまめに取り、ティッシュなどに付着したものに他の人が触れないように袋を密封する、⑥感染した可能性がある時は、何かに触るたびに手洗いをする、⑦手洗いの後のタオルは家族と共有しない、⑧咳が出る時はマスク着用、などです。
大きな病院はどこでも感染症対策委員会を作って管理はしていますが、菌を完全に排除するのは無理です。除菌、抗菌の製品を使っても宣伝ほどの効果はありません。菌を洗い落とすことが感染コントロールの原則です。当院も待合の椅子や手すりを頻繁に拭くようにしています。手洗いはセンサー式ですが、これも対策のひとつです。
有名な耐性菌は、耐性緑膿菌、MRSA、PRSPなどです。病棟ではこれらの菌にどう対処するか神経を使いますが、病院の対策だけでは効果が上がりません。皆さんにも耐性菌を作らないための常識を持つようにお願いしたいと思います。
MRSA
MRSAは耐性菌の代表選手です。子供さんが‘とびひ’にかかったことはありますか? これもMRSAによる場合が多くなっています。院内感染の原因菌として有名ですが、特殊な菌ではなく、幼稚園や学校、塾などにもたくさんいます。菌自体の力は弱いので、ほとんどの場合は付着しても治療は要りませんが、体力が落ちた時には致命的感染になりえます。
感染症の治療のために抗生物質を長期間飲んでもらうと、目的の菌以外の菌が耐性化します。肺炎、前立腺炎、咽頭炎、副鼻腔炎などでは必ずです。抗生物質は、他の菌に与える影響が少ないものを計画的に使うことが望まれますが、実際は野放しと言って良い状態です。
慢性の気管支病変や副鼻腔炎のためにエリスロマイシンを飲む方はたくさんおられます。これは年中飲んでいただきます。また、溶連菌の治療のために2週間くらいアモキシシリンを飲んでもらう子供も多くいます。溶連菌自体は今のところ耐性化しないようですが、他の菌が耐性化するはずです。したがって、その方には耐性化したMRSAなどがたくさん付いていて、その方が触る所にも当然その菌が付いていきます。もちろん眼には見えませんし、ついても症状はありません。でも、その菌で感染症を起こすと、抗生物質は簡単には効きません。
病院では抗生物質の管理のしかた、排泄物の捨て方などに神経を使っています。でも病院ばかりでなく、ご家庭でも手洗いやタオルの交換の仕方に注意すべきです。手で触れる所には全て眼に見えない病原体がついているかもしれないと考えるべきです(神経質にならない程度に)。瞬間殺菌をうたった消毒薬もありますが、効果の検証が不充分で害も予想されますので、私はお勧めしません。
診療所便りより 平成18年11月
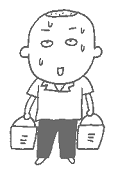

弱いものいじめはしません.
廊下は走りません.
談合はしません。