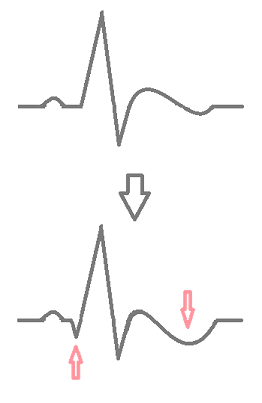
心電図検査の目的
(目的)心電図検査の目的は、不整脈や狭心症、心筋梗塞、心臓肥大などを探ることです。典型的な例としては心筋梗塞の最初の検査、頻脈や除脈で救急を受けた時に診断をつけようとして使います。
大きく変化している場合は、そこでかなり診断できることもあります。微妙な変化の場合、過去の記録と比べて病状を推測するのですが、通常の診察日に検査する場合は、検査しても直ぐ治療に結びつかないので、その意義を理解しにくいことになります。無駄に思えるはずです。
(記録の意味)当院では毎年数例の急性心筋梗塞や頻拍発作を診療しますが、比較できる過去の記録がなくて困ることがあります。全員に心電図検査をすれば良かろうと思われるかも知れませんが、保険診療のルールでは狭心症や不整脈が疑われる方以外は、例えば高血圧や糖尿病があっても厳密には検査は認められていませんから、無理に検査しない傾向はあります。
また、私が検査を勧めても、今は症状がないから、あるいは健診で受けるから病院での検査は無駄と考えて拒否される傾向があるのも理由のようです。 無理強いはできませんから記録がないままになり、後で困った事態になっているのが現状です。
心電図の所見は言葉で表現しにくいので、目で比較する必要があります。 血糖値やコレステロールは数値で表されますから比較は容易ですが、心電図は表現が単純ではありません。
図に示した例で言えば、赤の矢印の部分は上と下で変化が見られます。これを言葉で表現すると、「小さな尖った波形が下向きに少し発生し、後ろの波が少しくぼんで・・・」といった表現になり、情報データとして曖昧です。 よほど大きな所見がない限り、実物を見て比べないと誤認を生じます。
健診機関側にも、この認識が足りていないようです。心電図の結果はP〜Uのアルファベットを使った記号や何ミリ上昇といった表現がされますが、言葉には限界があるので実物のコピーを渡すべきでしょう。言葉で済むはずがないことを認識すべきです。
(‘正常’の意味)今の健診のほとんどで、心電図は機械が自動判定します。前回と多少形が変っても、基準を満たしていれば‘正常’と判断してくるはずです。でも所見の変化は何か起こったことを意味しますので、結果が正常かどうかが病状を意味せず、病気の見逃しにつながります。微妙に変化していても、自覚症状はないのが普通です。人間ドックで見逃されていた心臓病の例は珍しくありません。
心臓に何か起こす危険度が高い方、具体的には高血圧、脂質代謝異常、糖尿病、喫煙者は必ず定期的に検査をして、過去の結果と比べる必要があります。それによって緊急時の対処を間違わないようにしたいものです。
診療所便り 平成27年1月分より・・・(2015.01.31up)