���A�a�̖�̒��ӓ_�@�@������Q�P�N�P�Q���P�V���@���{�@�Á@
���N�̓~�ɐV�������A�a�̖�������܂����B�����̕���ł́A���̖�ɂ��ďЉ�܂��B����ɁA��ʓI�Ȗ�̒��ӓ_�K���܂�
�W���k�r�A�A�O���N�e�B��
���̖�́A���ǂ��番�傳���z�������̓������������ł��B���܂ł̓��A�a�̖�Ƃ͓������Ⴄ�V������ł��B�@
���ǂ��番�傳���z�������̖��O�̓C���N���`���ƌ����܂��B�C���N���`�����X���ɓ����܂��B���������H����������ɑ��₩�ɃC���X���������傳���̂́A�H�ו�����������ɃC���N���`���������ăC���X�����̕�����h�����Ă��邩��ł��B���ɁA�C���N���`�����X�����������p������܂��B�H�~�ɂ��W���Ă��܂��B�@
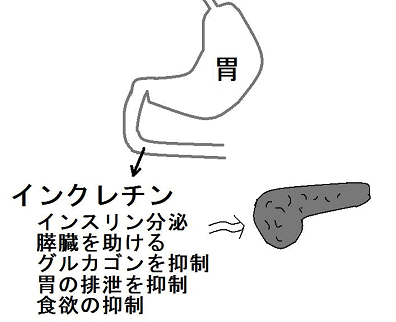
����̐V������́A���̃C���N���`�������������̂�x�点�邱�ƂŁA�C���N���`���̓��������߂���ʂ�����܂��B�C���N���`��������y�f���c�o�o�S�Ɨ�����̂ŁA�c�o�o�S�j�Q�܂ƌĂ�܂��B�@�����œ��̐����̂��߂ɁA���A�a�̈��ݖ�̎�ނ��܂Ƃ߂Ă݂܂��B��ԉ����������ꂽ��̂��Ƃł��B
|
��� |
���i�� |
���ʁ@���� |
���_ |
|
�r�t�� |
�I�C�O���R���A�}���[�� |
�C���X����������h�� |
�ጌ�������� |
|
�O���R�V�_�[�[�j�Q�� |
�x�C�X���A�O���R�o�C |
���̋z���}�� |
�����̏Ǐo�₷�� |
|
�r�O�A�i�C�h�� |
�����r���A���f�b�g |
�C���X�����̌��ʂ������� |
���_�A�V�h�[�V�X�̉\�� |
|
�`�A�]���W�� |
�A�N�g�X |
�C���X�����̌��ʂ������� |
����̉\�� |
|
�O���j�h |
�t�@�X�e�B�b�N�A�X�^�[�V�X |
�����ɃC���X����������h�� |
��� |
|
�c�o�o�S�j�Q�� |
�W���k�r�A�A�O���N�e�B�� |
���܂��� |
��� |
�����̐V�������ݖD��Ă���_
�P�@�ጌ�����N�����ɂ����@
�Q�@�X���ɕ��S�������ɂ����@
�R�@�얞���ɂ����@
�S�@���̖�ƕ��p�ł���@
�T�@����P���̓����ł悢
�V�������ݖ�̌��_�@
�P�@����߁@
�Q�@�ݒ��Ǐo��\���@
�R�@�l�i�������@
�S�@���̃z�������ɍ�p����\��������
�T�@�V�����ĕ]�����m�肵�Ă��Ȃ��@
�U�@������������
���A�a��̈�ʓI�ȕ���p
|
����p |
�Ǐ�A���� |
�Ώ��@�A���ӂȂ� |
|
�ጌ�� |
���܂��܂ȁe�ጌ���Ǐ�f�@�ጌ���̕���ŏq�ׂ��ʂ� |
�u�h�E���̐ێ�A�O���J�S���̒��� |
|
�����A���ɁA�֔�A�H�~�s�U�A�q�f |
�e������Ǐ�f�Ƃ܂Ƃ߂��邱�Ƃ�����܂� |
�ǂ̖�ł���������\��������܂��B |
|
���Ǘl�Ǐ�A���Ȃ�A���� |
�������ɂ��A�������Ђǂ����� |
������X�ɑ��₵�Ċ��炷�B�ݒ�����ŏ��ɕ��p����B |
|
�̋@�\��Q |
�ǏȂ����Ƃ�����܂��@�ʏ�͌��t�����ł̂`�r�s�A�`�k�s�ُ���Ӗ����܂��B�@ |
�ǂ̖�ł���������\��������܂��B��̒��~�A�܂��͌��� |
|
���NJ̉� |
�̋@�\��Q�̌��������́@�����ɂ�������� |
���@�A�W������ |
|
���A�����j�A���� |
�ӎ���Q���o�邱�Ƃ����� |
���z���}���܂ŏo�邱�Ƃ�����@�@��̒��~�A�A�~�m�_���܂̎g�p |
|
�畆�Ǐ�A���] |
�~�y���]�A�y�� �������ꍇ�̓V���b�N��� |
��̒��~�A�A�����M�[�̎��� |
|
�����ߕq�� |
���ɓ��������������Ԃ��Ȃ�Ȃ� |
��L |
|
�n�� |
�ǏȂ��ꍇ�������@���x�ɂȂ�Α���⌑�ӊ��Ȃǁ@ |
��̒��~�A |
|
������������(�n���̈��̂悤�Ȃ���) |
���M�����邱�Ƃ�����B �������͖Ɖu�ɕK�v�ł� |
��̒��~�A���ʓ��@���K�v�Ȃ��Ƃ�����܂� |
|
�������� |
���x�ɂȂ�Ώo�� |
���ߖ�̒��~�A���� |
|
�������A���o�ُ� |
���̒��̒ɂ݁A��������Ȃ��Ȃ� |
|
|
�d�����ُ� |
�ǏȂ����Ƃ������A�ӎ�������邱�Ƃ�����@ |
��̒��~�A���� |
|
���A�~���[�[���� |
�ǏȂ����Ƃ����� |
�H�ɔ����A�֎� |
|
�A���R�[���ϐ��ቺ�@ |
�A���^�r���[�X�Ə�����Ă��邱�Ƃ� |
�֎� |
���A�a��̒��ӏ�
�@���Œ�߂�ꂽ���ӏ����͔��ɓ���ȕ��͂ł����A�v��ƈȉ��̂悤�ȓ��e�ł��B���ׂ鎞�̂��߂ɏ����Ă����܂����A�o����K�v�͂���܂���B���͂͌����Ȃ��ӔC��j�����邽�߂ɍ��X��������A�Ȋw�I�Ɍ�������Ă��炸�A����̖�ł������������炱�̖���������낤�Ƃ��������ō���Ă��܂��̂ŁA�{���̕���p��������Ă���킯�ł͂���܂���B���ۂɕ��͂̒ʂ�Ɏg���Ă���ƕa�������邱�Ƃ�����܂��B
�D�w�ɂ͓��^�֎~�@���̖�ɉߕq�ǂ�����l�ɂ͓��^�֎~�@�d�ǂ̊����ǁA��p�O��A�d�ĂȊO���̊��҂ɂ͓��^�֎~�@�����A�q�f�Ȃǂ̈ݒ��Ǐ���l�͓��^�֎~�@���A�a�������܂��͑O�����A�d�ǃP�g�[�V�X�ɂ͓��^�֎~�@�̑���t�������Ɉ����l�ɂ͎g�p�֎~�@�]�����́A���t�@�\���ቺ�����l�͒ጌ���ɒ��ӂ��K�v�@�H���̐ێ悪�s�K���Ȏ��͒ጌ�����N�����₷���@�������ؓ��^���̎��ɂ͒ጌ�����N�����₷���@�A���R�[�����ʂɈ��ސl�ł͒ጌ���̌����ɂȂ�₷���@����҂ł͐T�d�ɑ��ʂ��Ă����@���A�a�̐f�f���s�m���Ȑl�ɂ͓K�����Ȃ��@�H���Ö@��^���Ö@�Ō��ʕs�[���Ȏ��Ɏg�p���l����@���ʂ���J�n���A���ʕs�[���Ȏ��͕ʂȎ��Â��l����@��ɓ��^�p���̉ہA�ʂ̒��߁A��܂̑I���ɒ��ӂ��邱�Ɓ@�ጌ�����N�������Ƃ�����̂ŁA������ƁA�^�]�ɂ͒��ӂ��K�v�@�t����̑��������Ȃ��Ă��ʂ̒��������Ȃ��ł������ƒv���I�Ȓጌ�����邱�Ƃ�����B�t�s�S�̊��҂���́A���ɗp�S����K�v������B
���N���瓜�A�a��̂ЂƂu�{�O���{�[�X�v�A�a�̔��Ǘ\�h�Ɏg���Ă��ǂ����ƂɂȂ�܂������A����͗�O�Œʏ�͖��m�ȓ��A�a�łȂ����������g���ׂ��ł͂���܂���B�t�@�\��̑��̋@�\�́A���ɂ͋}�Ɉ������܂��B���̏ꍇ�A���A�a�̖�߂��Ȃ��Ɗ댯�ł��B�ł����ۂɂ͌䎩���̐t�@�\��������邱�ƂȂǓ���̂ŁA���҂��p�S���Ă��������͂���܂���B��������������Εa�@�ɍs������Ȃ��̂�����ł��B��������ǂ�ł��Ӗ�������Ȃ��l�͑����̂ŁA���̓_��������ӏ��i�Y�t���j�̌��ʂ͌���I�ł��B
��ʓI�ȑ��ݍ�p�i�������݁j
����͑厖�ł��B��҂��t�����S�ɗ������Ă��Ȃ��l�������̂ŁA�ڂ�ʂ��ĉ������B�����A�����̖����鎞�ɂ́A�������݂ɂȂ��Ă��Ȃ����m�F���ĉ������B���ɍ܂ł̒ጌ���A�X�e���C�h�ł̍���������\�I�ł��B
���A�a��̌��ʂ��������A�ጌ�����N�����₷���X��������
|
�C���X���� |
���̓��A�a�̖� |
|
|
���[�t�@�����i���t���T���T���ɂ����j |
�v���x�l�V�h�i�A�_�̖�j |
�������ɍ܁i�ɂݎ~�߁A��M�܁j |
|
���u���b�J�[�i�����A�S���̖�j |
�T���t�@�܁i�R�ۍ܁j |
�e�g���T�C�N�����i�R�������̂ЂƂj |
|
�t�B�u���[�g�i�������b�̖�j |
�A�]�[���n��i�i�����̖�j |
|
�����~����p����߂�\�����������
|
�G�s�l�t�����i�b����V���b�N�̖�j |
�X�e���C�h�i�A�����M�[�Ȃǂ̖�j |
���A�� |
|
�b��B�z������ |
���E�z�������i�����z�������j |
�|�_�u�Z�������i�z�������܁j |
|
�C�m�j�A�W�h�i���j�̖�j |
���t�@���s�V���i���j�̖�j |
�s���W�i�~�h�i���j�̖�j |
|
�t�F�m�`�A�W���n��܁i�����_��j |
�t�F�j�g�C���i�������̖�j |
�j�R�`���_�i�r�^�~���j |
���A�a�̈��ݖ�̈Ӗ�
�����ň��ݖ�̈Ӗ�������������Ǝv���܂��B�@
���A�a�̖�̗��z�@
�@ �����l��H�O�A�H��Ƃ�����߂��܂ŗ}����
�A ��ɂ���Ĕ얞���������Ȃ�
�B �ጌ�����N�����Ȃ�
�C �̑���t���A���ǂɊQ���y�ڂ��Ȃ�
�D �X���ɕ��S�������Ȃ�
�E �R���X�e���[���ȂǂɈ��e�����y�ڂ��Ȃ�
�F ��`�┭�����̖�肪�Ȃ�
�G �����ǂ����������Ȃ�
�H �l�i�������@���̓���Ŏ��Â��I������B
���ۂɏ�̏���������͂���܂���B��ɂ͉������猇�_������܂��B�܂��A���A�a�̖�̎g�����͔��ɓ���A���E���T���Ă������Ɏg����l�͂��Ȃ��ł��傤�B�ł́A����Ȃɂ�₱�����Ȃ��͎g��Ȃ������ǂ����ƌ����ƁA�����ł͂Ȃ��悤�ł��B�@�l�X�Ȍ����̌��ʂ�����ƁA�K�v�ȏꍇ�͑��߂ɖ������ł������ق�������ƍl�����܂��B
�^����H���Ö@�͕K�{�ł����A�������������ƁA�����ɂ͖K�v�Ȃ��̂��Ɗ��Ⴂ�����l�������āA���ʓI�ɕa������������邱�Ƃ������Ȃ�A�Q��ڂɎ�f���ꂽ���ɂ͎������Ă���l�����܂��B�K�v�Ɣ��f���ꂽ��A��̎��Â�x�点�߂��Ă͂����܂���B���Ȃ��Ƃ����������߂ɂȂ����i�K�ŁA�����m���ɉh�{�m���҂Ƒ��k���ł���悤�ɂ��Ă����ׂ��ł��B
��̈Ӗ��ɂ��āA�^��ɂ���������`�Ő������܂��B
�@ ���A�a�Ȃ�A����������ق����ǂ����H
������₷�����ł����A�ԈႢ�Ƃ͌����܂���B�������́A�u�������Â��n�߁A�a�@�ɒʉ@�A�܂��͘A������荇���K�v������B�v�ł��B
���ݖ�ɂ͗l�X�Ȗ��_������܂����A���ق����o�߂��ǂ����Ƃ������A�Q��S�z�������Ĉ��܂Ȃ��̂͐���������܂���B���ׂ́A��{�I�ɖ�ɗ���߂��Ȃ��ق����悢�a�C�ł��B�ł����A�a�ł́A�u��͂Ȃ�ׂ����܂Ȃ��ŁA�Ђǂ��Ȃ��Ă�����ށB�v�Ƃ����l�����ł́A�o�߂��������܂��B�a�C�̐��i���Ⴂ�܂��B
�u�H���Ö@�����Â̊�{�Ȃ̂ŁA���Ղɖ���������Ȃ����Ɓv�Ƃ����̂͗��_�I�ɂ͐������̂ł����A���̌��t�̂��߂ɖȂ��Ȃ玩���͌y���̂��Ɗ��Ⴂ���Ēʉ@�����Ȃ����҂������A���̂��߂ɕa��͈������܂��B�����I�ɂ͖�����l�̂ق����o�߂��ǂ��̂͊ԈႢ����܂���B
�A�@��͂P����ݏo������~�߂��Ȃ��̂��H�@
���̂悤�Ɏ��₳��邱�Ƃ͑����̂ł����A���̕��͂ɑ��铚���́A�u���̎���ɂ͈Ӗ�������܂���v�Ƃ������������̂ɂȂ�܂��B�����C�̓������ӂ�o�������ɁA�u��x�����~�߂�ƁA���ӂꂽ���ɂ܂��~�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ�����A���̂܂܂��ӂꂳ���Ă����B�v�ƍl����l�͂��Ȃ��͂��ł��B�K�v�Ȏ��ɂ͕K�v�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��B
���A�a�͕a�C�̐��i����l���āA�����ǎ��Â���Εa�C�������Ă��܂��Ɗ��҂ł��܂���̂ŁA���Â��Ĕ������݂邵������܂���B���Ŏ��Â��I��邱�Ƃ����҂���͎̂~�߂āA������ɂ���ʉ@����K�v������A����Ȃ��ł�����ł�낤���ƍl�����ق����A�ނ��낢���Ǝv���܂��B
���͖v��Ȃ��Ȃ�l�͂��܂��B�H���Ö@��^���Ö@��M�S�ɂ��ꂽ���́A��𒆎~�����܂܂ł�����ꍇ������܂��B�������A�����l��������Ȃ��̂ɁA�u�������A���̐l�B��ڕW�ɖ�����܂Ȃ��ŗl�q���������B�v�ƍl������ƁA�a�������Ă��܂����Ƃ������̂ŁA��̎��Â�x�点�邱�ƂɌŎ����Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B���炩�ɖK�v�ł��鎞�ɁA�~�߂��邩�ǂ������C�ɂ��Ă��Ӗ�������܂���B
�B�@���A�a�̖�ŁA�X���������Ȃ�̂��H�@
����X���ɕ��S��������\���́A��̎�ނɂ���Ă��قȂ�܂����A�m���ɂ���܂��B���ɃC���X�����̕�����h�������́A�X���ɕ��S��������Ǝv���܂��B�X�����J��Ԃ��h�������ƁA�C���X���������זE�������Ă��܂��āA�e�X������ꂽ�f�悤�ȏ�ԂɂȂ�܂��B��������ƁA�C���X�������o���͂͗����Ă��܂��܂��B����Ȃ���܂Ȃ��ق��������̂ł́H�ƍl����l�������܂����A���ۂɖ���g��Ȃ��ł���Ɩҗ�Ɍ����������Ȃ��č����ǂ��o���オ���Ă��܂��܂����A��͂蓯�l�ɃC���X�����̕����Q���o�Ă��܂��B�@�����ǂ�h�����߂ɁA�����̃R���g���[����D�悵�čl�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�C�����l���������́A�����ɂ����̂��@
�����l�������Ɓu���Ő��v�Ƃ����s�v�c�Ȍ��ۂ������܂��B���Ő��́A���������l�ɑ̂�����������Ȃ��Đ���ȑ�ӂ��ł��Ȃ��Ȃ�����Ԃ��Ӗ����A���ɃC���X�����̌��ʂ������邱�Ƃ�A�C���X�����̕�����ێ��ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�����l���������ƁA���ꎩ�̂��a������������܂��B
���̂悤�ȏꍇ�̑Ώ��@�́A�����l���܂������邱�Ƃł��B����������A�{���̑�ӂ����߂��ĐH���Ö@��^���Ö@�ŃR���g���[���ł���\�����o�Ă��܂��B�����A�������ώ@���Ă��đ�ӂ����퉻���Ȃ��܂ܒ����ԉ߂����ƁA���̊Ԃɍ����ǂ�����I�ɂȂ�A�܂��X���̕���\�ɂ����e�������邩���m��܂���B���̂��߂ɖ�̎��Â�K�v�Ƃ���A�܂�H���Ö@�Ŋώ@���Ă���ł͌o�߂��ǂ��Ȃ����Ƃ�����܂��B
��\�I�Ȗ��@�@
��\�I�Ȗ�ɂ��ĊȒP�ɐ������܂��B�@
�@�I�C�O���R���Ȃ�
|
��i���i���i���j |
�I�C�O���R���A�_�I�j�[���A�p�~���R���Ȃ� |
|
��ʖ��i�������j |
�O���x���N���~�h |
|
�����A���� |
1.25
�~����2.5�~���̐��܂�����B2.5�~���̂��̂͌`�������^�B�@��Ƃ����X������C���X�������o�������p�������A���Ȃ苭�͂Ɍ����l����������ʂ����҂ł���B���j�̂����B�����͒��������������ƁB |
|
���_�A���ӓ_�A |
����Ɍ��ʂ��Ȃ��Ȃ邱�ƁA�X����敾�����₷�����ƁA�ጌ�����N�����Əd�ǂɂȂ�₷�����ƁA�얞�������₷�����ƂȂǁB�Q�������i�ŏ��͌����Ă����̂ɁA����Ɍ��ʂ��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����錾�t�j�B |
|
����p |
�ጌ���i�H�Ȃ͂��ł����Q�D�T������ƋL�ڂ���Ă��܂��j�A�̋@�\��Q�i�O�D�V���j�A���]�i�O�D�P���j�ȂǁB |
|
���킹���݁A���ݍ�p |
�����̖���M�܂ƕ����ۂ݂ɂȂ�܂��̂ŁA���X�\���s�\�̌��ʂ̕ω�������܂��B���̖���g���Ă���l�́A���ׂ̂Ƃ��Ȃǂׂ͍��������l�𑪂�Ȃ��Ɗ댯�ł��B��p�Ȃǂ̂��߂ɃC���X�������Âɐ�ւ��鎞�Ɍ��ʂ��ω����邱�Ƃ��悭����܂��B�C���X�����Ō����l��������ƁA�u���Ő��v���������āA���̖�̌��ʂ��}�ɍ����Ȃ邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���̂悤�Ȏ��ɈȑO�Ɠ����ʂň��ނƂЂǂ��ጌ�����N�����A��p��Ɏ��̂��N�����댯��������܂��B |
|
���̑� |
�P���R����ނƂ�������������Ă���l���������܂����A��p���Ԃ��������Ƃ��l����ƂP���P�`�Q�������Ǝv���܂��B |
�A�O���~�N����
|
��i���i���i���j |
�O���~�N���� |
|
��ʖ��i�������j |
�O���O���W�h |
|
�����A���� |
20�~����40�~���̐��܂�����B���悻�I�C�O���R���������キ�������̂ƌ�����B���t���T���T���ɂ�����ʂ����邻���ł����A�����ł��邱�Ƃ͂܂�����܂���B |
|
���_�A���ӓ_ |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
|
����p |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
|
���킹���݁A���ݍ�p |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
|
���̑� |
��͂�1���P�`�Q����ޖ�ł��B |
�B�A�}���[��
|
��ܖ��A���i�� |
�A�}���[�� |
|
��ʖ��i�������j |
�O�����s���h |
|
�����A���� |
�P�~���ƂR�~���̐��܂�����B���悻�̋@�\�̓O���x���N���~�h��O���N���W�h�Ɠ����B�X������C���X�������o������ȊO�ɁA�C���X�����̌��ʂ����߂�悤�ȍ�p�����������߂ɁA�����X���ɂ����镉�S���y�����낤�ƌ����Ă��܂��B�������A���̌��ʂ����҂���䎩�g�͎����ł��܂���B |
|
���_�A���ӓ_ |
���̂Ƃ������ȕ���p�͏��Ȃ��A�����A�Z�������悻�I�C�O���R���A�_�I�j�[���Ɠ����ł��B |
|
����p |
�ጌ���i�o������܂��A�S�`�T�����肤�邻���ł��j�A���\�f�s�o�㏸�i�P�D�W�U���j�A�k�c�g�㏸�i�P�D�W�Q���j�A�`�k�s�㏸�i�P�D�V�X���j�A�`�r�s�㏸�i�P�D�P�U���j�A�`�k�o�㏸�i�P�D�O�U���j�A�a�t�m�㏸�i�O�D�W�T���j�A�J���E���㏸�i�O�D�V�W���j�A�q�C�i�O�D�V�R���j�A�����������i�O�D�U�T���j�A�����i�O�D�U�R���j�A�ݕs�����i�O�D�U�R���j |
|
���킹���݁A���ݍ�p |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
|
���̑� |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
�C�O���j�h
|
��i���i���i���j |
�t�@�X�e�B�b�N�A�X�^�[�V�X�A�O���t�@�X�g |
|
��ʖ��i�������j |
�t�@�X�e�B�b�N�A�X�^�[�V�X�i�i�e�O���j�h�j�A�O���t�@�X�g�i�~�`�O���j�h�j |
|
�����A���� |
�Z���ԍ�p���ăC���X�������X�����番�傳���A�H��̌����l����������ʂ�����܂��B���̒��ł́A�O���t�@�X�g���ł����ʂ�����悤�ł��B���ʂ��������Ƃ����_�ł��B����������ƁA�H��̃C���X��������𑣂����ƂŁA�H��̉ߌ����������炷���Ǐ�Q��\�h������ʂ����ɂ���̂����m��܂���B |
|
���_�A���ӓ_ |
��r�I�V������Ȃ̂ŁA���\�N���Ƃ��ɌÂ���Ɨ�R���鍷������̂��܂ł͕�����Ȃ��B���͂�������߂ŁA�Ⴆ�I�C�O���R�����g���Ă��[���ȃR���g���[���������Ȃ��l�̏ꍇ�́A�����̖�ł̓R���g���[�������҂��ɂ����B�l�i�������B |
|
����p |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
|
���킹���݁A���ݍ�p |
��̕\�̃O���x���N���~�h�Ɠ����Ǝv���܂��B |
|
���̑� |
�y�ǂ̊��҂���ɂ͗ǂ���B�����R���g���[���ǍD�Ȃ瑱�s�A�������l�ȂǂɈ����̒�������������]���̖�ɖ߂����C���X����������Ƃ������j�ŁA����I�Ɏg���ׂ��ƍl���Ă��܂��B |
�D���|�O���R�V�_�[�[�j�Q��
|
��i���i���i���j |
�x�C�X���A�O���R�o�C�A�Z�C�u�� |
|
��ʖ��i�������j |
�x�C�X���i�{�O���{�[�X�j�A�O���R�o�C�i�A�J���{�[�X�j�A�Z�C�u���i�~�O���g�[���j |
|
�����A���� |
�O���R�V�_�[�[�j�Q�܁A�u�h�E���z���}���܂ȂǂƌĂ�܂��B�����͒��ǂ��瓜�����z�������̂�j�Q���āA�����l�̏㏸��}�����ł��B��������P�Ƃł͒ጌ�����قƂ�Ǘ��Ȃ����Ƃ��ǂ��_�ł����A�C���X�����⑼�̈��ݖ�ƕ��p����ƌ��ʂ����Ă���܂��B |
|
���_�A���ӓ_ |
�܂�Ɋ̋@�\��Q���N�������Ƃ�����B�̒��œ��������y���āA���Ȃ�≺���A���ɂ̕���p���A���Ȃ�̗��Ŕ������邱�ƁA�l�i���������ƁB���Ȃ��̕���p�͂��炭����Ǝ��邱�Ƃ������B�n�߂͂悭�����āA���炭����ƌ��ʂ��Ȃ��Ȃ�l�����܂��B�܂��A�����̖�͈��̓����ł��̂ŁA�����Ԉ��ݑ�������ő�ӂɍ�p�����邩������܂���B |
|
����p |
�x�C�X���̂O�D�R�~����A�O���R�o�C�̂P�O�O�~�����ŏ�����R����ނƕ���p���o�₷���̂ŁA���ꂼ��O�D�Q�~���ƂT�O�~���Ɍ��炷���A���މ��P��ɂ����ق������S�ł��B |
|
���ݍ�p |
���̓��A�a��i���p�͉\�ł��j |
|
���̑� |
�H���̒��O�Ɉ���ł��炢�܂��B���܂̎�ނ͂��������āA���̒��ő����n���鐻�i����������Ă��܂��B |
�E�`�A�]���W���n
|
��i���i���i���j |
�A�N�g�X |
|
��ʖ��i�������j |
�s�I�O���^�]�� |
|
�����A���� |
�C���X�����̌��ʂ����߂Ă�����B����������A���̖�Ō��ʂ��o�Ȃ����Ɏg���ƗL���Ȃ��Ƃ�����B�����炭���A�a���������Ă����̂�}����悤�Ȍ��ʂ�����A���̖�����X���ɗD�����ƌ����邾�낤�Ǝv���܂� |
|
���_�A���ӓ_ |
�ނ��݂̕���p���o��l�����\�����܂��B�S���̋@�\�ɖ�肪����l�i�����̐S�s�S�j�A���Ƃ��Ɛt���a�Ȃǂ̂��߂ɕ���݂�����l�ɂ͌����܂���B�l�i��������ł��B |
|
����p |
�ގ���Ŋ̑����Ђǂ��������镛��p���o�܂����̂ŁA���̖�����X�̑��Ɋւ���̌������Ă����ׂ��ł��B |
|
���킹���݁A���ݍ�p |
���̓��A�a��i���p�͉\�ł��j |
|
���̑� |
�ŏ��͂P�T�~�����܂��g���Ď������@���ǂ��Ǝv���܂��B���ʂ��S���o�Ȃ��l�����\���āA�L�����������ꂢ�ɕ������͕̂s�v�c�ł��B |
�E�r�O�A�i�C�h�n
|
��i���i���i���j |
�����r���A���f�b�g�A�O���R���� |
|
��ʖ��i�������j |
���g�t�H���~�� |
|
�����A���� |
�C���X�����̌��ʂ����߂Ă�����B�͂Ƃ��Ă͎ア��ŁA�P�Ƃł͂قƂ�ǒጌ�����N�����܂���B���A�a�̗\���R�̕������A�a�ɂȂ�̂𑊓��\�h�ł���B���̖�ƕ��p���邱�ƂŁA���ʂ�₤���Ƃ����҂ł���BHbA1c���P�`�Q�������邱�Ƃ��悭����܂��B |
|
���_�A���ӓ_ |
���_�A�V�h�[�V�X�Ƃ�����ӈُ킪��������댯��������B�������A���̓��_�A�V�h�[�V�X�̔������͕s���ł��B�قƂ�ǔ������Ă��Ȃ�����ł��B |
|
����p |
���ɋH�ɓ��_�A�V�h�[�V�X�Ƃ�����ӎ������N�����\��������B��p�̑O�A�t���������Ȃ����肵�āA�̂��_���ɌX���₷�����͒��~���K�v�B���_�A�V�h�[�V�X�̊���������l�A�t�@�\��Q�A�̋@�\��Q�̂���l�A��_�f���ǂ��₷���l�A�A���R�[���ێ������l�A�E���ǂ̐l�A�����A�q�f�Ȃǂ̈ݒ���Q�̐l�A����ҁA�d�ǂ̊����ǁA�O�����p�O��A�Q���ԁA�]�����̋@�\�s�S�A���t�@�\�s�S�̐l�A�D�w�A���̖�ɉߕq�ǂ�����l�Ȃǂɂ͎g�p�֎~ |
|
���킹���݁A���ݍ�p |
�A�V�h�[�V�X�i���t���_���ɂ��邱�Ɓj�̊댯�����߂���̂͑S�ĕ��p���ӂł��B�������ɍ܁i�ɂݎ~�߁j�A���[�h���e�܁i�b�s�̎��ɓ_�H������j�A�Q���^�}�C�V���Ȃǐt�Ő��̋������� |
|
���̑� |
����������܂Ȃ��ƌ��ʂ��o�ɂ����B |
��ʓI�Ȗ�̎g����
���A�a�̖�͌����Ƃ��ď��ʂ���J�n���܂��B�@�Ⴆ�A�I�C�O���R���i2.5�j�S�`�T���͕ی����F�߂�ő�ʂł����A�����Ɍ����l�������Ă��A�ŏ����炱�̗ʂŎg���̂͊댯�ł��B�ʏ�͏��ʂ���J�n���āA�ጌ���̗L���A����p�̗L�����m�F���Ȃ��璲�߂��Ă����܂��B
�������A����͊O���ŏ�������ꍇ��z�肵�Ă��܂��B���@���͕p��Ɍ����𑪒肵�ĊǗ��ł���̂ŕK�����������ɂ������K�v�͂���܂���B��̗ʂ��ނɉ����Ċ댯�x��z��ł���A�ŏ����炠����x�̗ʂ��g�����Ƃ��s�\�ł͂���܂���B
�ł����A��̌��ʂ����肷��̂Ɏ��Ԃ�������܂��̂ŁA���@���ɃR���g���[�����ǂ������ʂŁA�މ@����ɒጌ�����N�����\���͂���܂��B�Ǘ��ł��邩�ǂ������d�v�ł��B
�x�C�X���A�{�O���{�[�X�A�O���R�o�C�Ȃǂ̖�܂́A�����Ȃ�P���R��J�n����ƕ��̏Ǐo�܂��B�P���P��A�������͓K���Ɉ�����܂Ȃ������肵�Ȃ���A���X�Ɋ��炵�Ă����K�v������܂��B���X�ɂƌ����Ă��A���܂薟�R�ƌ������R���g���[������Ȃ��܂܊ώ@����̂͗ǂ�����܂���B�R���g���[���̌����݂������Ȃ���A�C���X�����ւ̐�ւ����l����ׂ��ł��B�@
��̎��Â��n�߂Ă��H����^���Ö@���K�ɂ���Ă��Ȃ��ƁA��̌��ʂ��s����ɂȂ�₷���X��������A�����ɗ���̂͊ԈႢ�ł��B