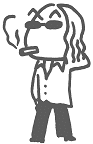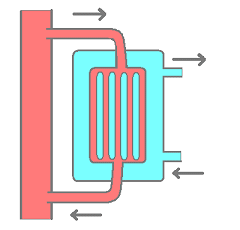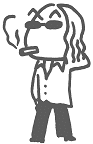
糖尿病性腎症と慢性腎臓病(勉強会資料)
この勉強会の目標
①慢性腎臓病の意味を理解する
②塩分制限の具体例を知る
③血圧管理の意義を知る
④尿検査の意味を知る
慢性腎臓病とは
読んで字のごとく、慢性の腎臓病のことですが、「腎機能の悪化が予想される腎臓の病気」といった意味です。糖尿病性腎症も慢性腎臓病に含まれます。
慢性腎臓病の定義
以下のいずれかを満たす場合を慢性腎臓病とする
1 腎障害が3ヶ月以上続く
この場合の障害の判断は、組織検査、血液、尿検査、
レントゲンなどの画像いずれでも構わない
2 糸球体濾過率(GFR)60未満が3ヶ月以上続く
例えば、3ヶ月以上にわたって蛋白尿かアルブミン尿が一定量以上出続けたら慢性腎臓病です。
糸球体濾過率GFRは、腎機能を表わす数字です。
実際は、
①尿蛋白が出るかどうか
②GFRが60あるかどうかが大事になっています。
さらに糖尿病患者さんの場合は特に腎臓の障害の意味合いが大きいので、
③尿アルブミンがどれくらい出るかが大きな注目点です。
慢性腎臓病の社会的意味
①血管の病気を意味する
②血液透析患者を生む
③経済的、精神的、身体的に損失が大きい
腎臓は血管の塊のようなものなので、慢性腎臓病があると、同時に心臓や血管の病気も持つと考えられます。
したがって、腎臓病を予防すれば心臓病の予防も期待できます。たくさんの人が腎不全のために血液透析を受けておられますが、腎不全になる患者さんを減らさないと不幸な人を減らせません。
そこで、慢性腎臓病という考え方を広めて、腎不全を予防しようとしているわけです。
早い段階で治療を開始し、腎不全を防ぐための病名です。
腎臓の働きの復習
腎臓は尿を作ります。血液をこしわけて老廃物を尿の中に出し、必要な物は血液の中に残す仕事をしています。
さらに、血液の濃さを調節するホルモン、血圧の調節をするホルモンを分泌し、骨の調節をするビタミンDの活性化にも関わっています。
したがって腎臓を悪くすると、次のようなことが起こりやすくなります。
①尿検査で蛋白か血液が出る
②血液の中に老廃物が溜まる
③貧血になる
④血圧が上がる むくむ
⑤骨がもろくなる
⑥ミネラルの調節が効かなくなる
血液透析の仕組み
血液透析は、透析膜の内と外で物質を交換して、血液中の不要な老廃物を外に出してしまおうという治療法です。腎不全が悪化した場合は、体の老廃物を出すため透析をするしかありません。
右の図のように、血管から血を取りながら、洗った血液を戻す作業をしますので、血管を機械につなぐ必要があります。およそ週に3日はベッドに寝ないといけません。
そうやっても、機械には腎臓の全ての機能は備わっていませんので、だんだん体が弱ってしまいます。透析は腎臓の代役としては役不足です。なんとか腎臓を守りたいものです。
慢性腎臓病の治療方針
要約すると、腎臓の負担を軽くし、腎臓の害になるものは排除するということです。
塩分の制限
蛋白質の制限(摂り過ぎない)
激しい運動の制限、脱水にならない
血圧、コレステロール、血糖値のコントロール
禁煙
肥満の是正、必要なカロリーは確保する
不要なミネラルの制限
塩分、蛋白質を制限する理由は、いずれも腎臓に負担をかけるからです。ただし、肉を食べないという極端な制限は意味がありません。
激しい運動、急激な脱水も腎に負担をかけます。
血圧、コレステロール、血糖値をコントロールすると、腎機能が保たれる傾向があります。
タバコは強力に動脈硬化を進めるために、タバコによって腎機能が悪化する傾向があります。
肥満は血圧や血糖値、コレステロールのコントロールを悪化させ、動脈硬化に悪影響があります。
いっぽうで、腎機能を維持するためには必要なカロリーを保つ必要があります。
慢性腎臓病が進行して腎不全になったら、カリウムとリンが血液中に溜まる傾向があります。カリウムは体にとって必要なミネラルですが、溜まりすぎると害が出ますので、時には制限が必要になります。
塩分制限の具体例
塩分を1日6グラム以内の摂取に止めると、腎機能を維持するのに有効だと言われています。でも、1日6グラムは、ちょっと辛いかも知れません。
①漬け物について
「漬け物を食べても腎臓がそんなに悪くなるはずはない。禁止するなんて極端だ。少しくらいはいいはず。」と、思われるかもしれませんが、慢性腎臓病になったら、漬け物は禁止すべきです。
塩分摂取量の目標は1日6グラム以下ですが、味噌汁1杯、煮物一皿にも各々1~2グラムの塩分が含まれていますから、よほど制限しないとすぐ越えます。今のご自分の感覚では異常と思えるほどの制限が必要かも知れません。
食品を制限すると、カロリー、ビタミン、タンパク不足になりますので、制限しても害がないものを考えないといけません。漬け物は人間の体に必須とは思えません。好きな人は多いですが、腎臓と交換できるほど好きでしょうか?
塩分の処理能力には年齢差と個人差があります。年齢が上がるにつれて塩分の処理能力が落ち、ちょっとの漬け物、煮物が、すぐ血圧や浮腫みに影響するようになってきます。慢性腎臓病の患者さんに、その害は計り知れません。
②醤油類
病院によっては、ダシ汁を刺身や揚げ物料理のタレとして出されるところがあります。
弁当に付いてくる一般の醤油のほうが、おそらく美味しいと思いますが、それでは治療にならないので、わざわざ手間をかけて作っているのです。
ダシ汁にも多少の塩分は含まれますが、醤油やソースに比べれば制限できますし、慣れれば充分に美味しく食べられます。たくさん作って、冷蔵庫に分けて入れておけば便利です。
私の家の食卓には醤油はありません。なくても慣れれば不自由しません。酢やみりん、カボスなどをフルに使えば、きっと醤油に頼らなくても済みます。
③スポーツ飲料
夏の暑い日の野球観戦、庭の木の剪定など、考えただけでも脱水になりそうです。こんな時には塩分が不足する場合がありますが、一時的です。
慢性腎臓病において、脱水状態は病気をいっぺんに悪化させます。激しい労働も命取りになりかねません。したがって、スポーツ飲料を必要とする労働や運動は、そもそも望ましくありません。
学生時代には暑い日の部活動では塩をなめながら練習をするように指導されたかもしれませんが、休憩を入れるほうが利口です。慢性腎臓病の人にスポーツ飲料は必ずしも必要ありません。
登山の時にも早い段階で水分を充分に摂っておけば、脱水にならないで休憩時間まで間に合うこともあります。休憩の間に血管内の脱水が補正されれば、その後の体内での水分の流れが順調にいき無理がかからないので、動きが楽です。その際、塩分は必要ありません。いっきに激しい仕事をしないのがコツです。
通常の体に良い運動の場合、特に塩分を補わなくても食事からの塩分で充分に調節されることがほとんどです。
④メニューの工夫
保存が効く食品の類は全般に塩分が多いので、考えて使わないといけません。「今の時代に保存食品がないと、食べるものがないじゃないか。」などと諦めないで工夫すれば、合成保存料を口にする機会を減らす意味もあります。
下の表の塩分量を見てください。これを摂りながら、1日6グラム以内に収めるのは簡単ではありません。
|
食品名 |
量 |
塩分含有量 |
|
メザシ |
1匹 |
1.5g |
|
アジのひらき |
1匹 |
1g |
|
しらす干し |
大さじ2杯 |
2g |
|
ハム |
1枚 |
1g |
|
たらこ |
1本 |
1.5g |
|
サンドイッチ |
1パック |
2.5g |
|
幕の内弁当 |
一人分 |
4.5g |
腎臓病のための血圧の薬
慢性腎臓病の患者さんには軽いうちから、早いうちから血圧を下げる治療をしたほうが、腎機能を維持する効果があります。
使う血圧の薬は、ACE阻害剤、ARBと略される薬が中心になります。この薬を使ったほうが、腎機能が悪化しにくい傾向があるからです。 ただし、これらの薬には欠点もあります。
・ 咳が出やすい(喘息がある人は飲めないこともあります)
・ 血圧を下げる力が弱め
・ 脈が速くなりやすい
・ 血清カリウムが高くなりやすい
・ 発疹が出ることもある
・ 値段が高め
血圧が非常に高いか、むくみが強くなると利尿剤が必要な場合もあります。ただし、これにも欠点があります。
・ 使いすぎると腎機能を悪化させる要因にもなりかねない
・ 痛風の引き金になる
・ ミネラルバランスを壊す
・ 血糖値を上げる
・ 脱水状態にする
腎機能が悪化した場合は、薬も腎臓から出なくなりますので、体の中に溜まって副作用が出るため、腎臓で分解される薬を減らさないと危ないこともあります。したがって、腎不全の方では、薬を腎不全向きの内容に変更することもあります。
血糖コントロールと腎症
血糖コントロールが良いと、腎症の進行は遅くなると考えられています。今までの勉強会で何度も学習した通りです。そして、血糖とともに血圧をコントロールできた患者さんが、腎機能を維持できる確率が高くなります。
GFRについて
もう一度、慢性腎臓病の定義を見直してください。2番目の項目にGFRという数字が出ていました。
GFRは腎臓の機能、働き具合、能力を表わします。血清クレアチニンと年齢、性別から概算して表にしてあります。
|
男性 |
年齢 |
|||||
|
|
|
20歳 |
40歳 |
60歳 |
70歳 |
80歳 |
|
0.7 |
121 |
99 |
88 |
84 |
81 |
|
|
0.8 |
104 |
85 |
76 |
73 |
70 |
|
|
0.9 |
92 |
75 |
67 |
64 |
61 |
|
|
1.0 |
82 |
67 |
59 |
57 |
55 |
|
|
1.1 |
74 |
60 |
54 |
51 |
49 |
|
|
1.2 |
67 |
55 |
49 |
46 |
45 |
|
|
1.3 |
61 |
50 |
45 |
43 |
41 |
|
|
1.4 |
56 |
46 |
41 |
39 |
38 |
|
表を見てください。例えば、年齢が70歳の男性で血清クレアチニンの値が1.2の人は、以前なら「血圧は高いけれど、問題ないでしょう。」と言われていましたが、この表を見るとGFRは46しかありません。今後は「あなたはGFRは46しかありません。慢性腎臓病です。血圧の治療は考え直さないといけません。」と言われます。
GFRが90以上あれば、腎機能は正常と考えられます。60に近づけば、機能はかなり落ちつつあると考えられます。60未満は完全に慢性腎臓病です。腎機能の悪化を防がないといけません。
ただし、このGFRの値は平均的な体格に基づいて想像された値ですので、正確ではありません。自分の腎機能が悪くなったからと将来を悲観する必要もありません。ちゃんと治療すれば、どのような段階でも病状の進行を遅らせることが可能です。
検尿について
蛋白尿が続くのは慢性腎臓病と、ほぼ同じ意味です。
尿蛋白がある場合は、治療が原則です。以前の健康診断では、ただ「要注意、観察」と書かれていたかも知れませんが、安静状態で続けて蛋白尿が出ていれば、それはもう慢性腎臓病と思われます。観察ではなくて、治療が必要です。
特に糖尿病の患者さんについては、蛋白尿が出る段階では非常に腎臓がやられてしまったと考えられます。
運動した後、自然に蛋白尿が出る人もいます。はっきりしない場合には、朝一番の尿を検査すると解ります。また、尿中のクレアチニンといっしょに計算するとよく解ります。
潜血が出る時も安心はできません。
腎炎の時にも尿潜血が出ます。慢性腎炎は、当然ながら慢性腎臓病で腎機能の悪化の可能性があります。
目で見てはっきり解るような血尿は、ほとんどが尿管結石や感染症によりますので、ただちに腎機能が悪化するわけではないのですが、「たぶん血尿は結石のせいだろう。」と考えているうちに、腎炎が悪化することもありえます。
尿潜血が腎臓~尿路の癌によって起こる場合もあります。やはり早めの診断が必要です。
尿アルブミンは腎症の指標です。
特に糖尿病患者さんの場合は、ご自分の尿にアルブミンがどれくらい出ているかを気にする必要があります。
下の表を見て下さい。健康な人でも、わずかながら尿蛋白が出ています。主にアルブミンと言われる蛋白です。腎臓が障害されてくると、少しずつアルブミンの量も増えてきます。一定の量(30mg?)になったら、腎臓病の段階に入ったと考えられます。
さらにアルブミン量が増えてくると、今度は検尿テープで判定できるようになり、尿蛋白が陽性となります。つまり、蛋白が出るのは腎症がかなり進行したことを意味します。もっと早く、微量アルブミン尿の段階から、慢性腎臓病として治療すべきです。
腎症の段階
1 腎症前期 正常アルブミン量
2 早期腎症 微量アルブミン尿 (30~300mg)
3 顕性腎症 アルブミン300mg以上(蛋白陽性)
尿蛋白1日3.5g以上=ネフローゼ症候群
4 腎不全期 血清クレアチニン上昇(≧2?)
5 透析療法期
糖尿病性腎症は早期治療の意味が大きいので、蛋白が出る前から治療すべきです。 「尿蛋白が陰性だから、腎臓は大丈夫。」「健康診断で何も言われなかったから、腎臓には問題ない。」というのは間違いです。
残念ながら、健診施設でこれまで正しい判定をしてきたところはないと言ってよいほどです。加えて、特定健診では腎機能を測らない場合があります。ご自分で注意するしかありません。
(今回の勉強会の資料は、日本腎臓病学会編「CKDの診療ガイド」より引用改変しました。)
平成20年8月21日