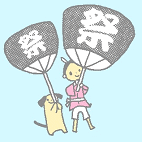手術前後の血糖コントロール
手術の前後には、インスリンを使いながら厳格に血糖をコントロールしたほうが良いと昔から言われています。でも、その根拠に関しては少し曖昧でした。血糖を下げたら本当に手術成績が伸びるのか、もしくは意外に結果が良くないのか、証拠のようなものには欠けていました。
一般に感染症や手術など、何かの侵襲が体に加わる時は血糖値が乱れ、その結果として代謝全体が悪化する傾向があります。理屈で考えると、それを抑えれば治療成績の向上が期待できます。実際の影響を調べた統計が発表されました(DiabetesCare2014;37:1516-1524)。
その結果、やはり血糖のコントロールが良いと手術合併症の発生率が下がる傾向が明らかでした。感染症の発生率、ろう孔の発生率、入院日数などに差が出ています。手術の腕さえ良ければ血糖は適当で良かろうと考えてはいけません。メスが切れるだけでは、手術成績は良くないのです。
もちろん手術成績が血糖値だけで決まるはずはありません。侵襲の少ない術式、手術の手際の良さなどは大事で、手術成績のかなりの部分は外科医の腕によると思います。ただし、その腕に加えて、代謝の管理の必要性も忘れてはなりません。
この研究の対象は肝臓や膵臓などの手術に限定されていましたが、経験的に他の手術、怪我、肺炎などの感染症の際にも血糖値の管理が治療成績に直結するのを感じます。普段は治療の必要がない程度の糖尿病でも、感染症がある場合はインスリンを用いることを考え、代謝の状態を保つのが原則です。血糖値が少し高いけど、飲み薬で様子を見よう、あるいは強い抗生物質を選んだから治療成績も良かろうと考えていると、想像以上に感染症が悪化することがあります。
考えてみれば当然かも知れません。手術も感染症も体にとっては侵襲であることは同じで、代謝には両方とも悪影響を及ぼします。充分な栄養、水分、酸素などが補充され、代謝経路が順調に運営されないと細胞の機能が維持されません。抗生物質を使えば病原菌は退治できるとは限らず、結局は免疫細胞の活動によって病原体を排除する必要があり、その際に細胞の代謝が順調にいかないと、免疫や傷の修復に関わる機能も維持が難しくなるはずです。
ただし、実際の血糖コントロールには難渋します。血糖値の下げすぎは命に関わりますし、普段のコントロールが悪い人の血糖を急に下げると、合併症に影響することがあります。下手すると、手術は成功したが網膜の出血で失明することさえあります。つまり、手術前後の血糖さえコントロールすれば良く、普段の血糖値は気にしなくて良いなどとは言えません。
できれば急激なコントロールを必要としないように、また合併症悪化の危険度を減らすために、普段からのコントロールを目指すべきと思います。いつ手術が必要になるか分からないからです。
診療所便り 平成26年9月分より・・・(2014.09.30up)