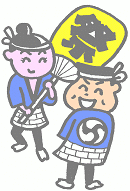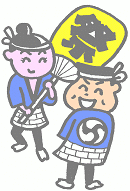
血糖値の変動の意味
インスリン注射をしながら血糖値を自分で測定しておられる人にとっては、血糖の高さとともに変動の幅が非常に気になります。
何を食べ、どれくらい動くかによって血糖値は著しく上下します。実際に測ってみて、いかに血糖値が変動するものか驚きます。どう食事し、どう運動したらよいのか、さっぱり解りませんと訴える患者さんもたくさんいらっしゃいます。血圧と同じように血糖値を変動させる要因は多く、予測するのは非常に難しいので不安になります。ところが医者達は血糖の平均値しか気にしてくれない傾向がありました。
その理由は、
①患者さんの食事療法の能力の限界(食事が一定しない)
②食品交換表の限界(糖分吸収の早さの違いに対応していない)
③変動に対応できる薬がない
④変動の意味が不明確(平均値で検討した文献しかない)
⑤インスリン抗体の作用や消化機能の問題
などと思われます。患者さんから質問されても、医者も対策を取れなかったというのが実情でした。
激しい低血糖発作は非常に危険です。変動の幅が大きい人は、300-500くらいあった血糖値が、1-2時間後には50くらいまで一気に下がります。対応を間違えると意識を失う可能性もあります。血糖値が高いまま放置するのも間違いですが、低血糖で危険な目に遭わせるのは最悪ですので、医者は低血糖を恐れて血糖値を高めにするしかありません。でも、それでは糖尿病性の合併症は防げません。
食後に血糖値が急激に上昇する人の血管には、動脈硬化の所見が直ぐ出るらしいという実験結果も発表されています。実験ですので実際の人間に全て置き換えてよい話かどうかは解りませんが、可能なら変動しないほうが良かろうとは思えます。
さて、最近はインスリン製剤が進歩し、注射の効き方が一定してきました。 例えば、ある製品は体内で薬が固まらないように加工してあり、吸収が早く効果も一定しています。また、別のインスリンは逆に薬が体内で安定して固まった状態を保ち、そのために1日を通じてゆっくり効果が発現されます。
飲み薬も様々なものがあります。作用時間が長いもの、短いものを組み合わせることで、その方の血糖値の変動をやわらげ、一定の値を保てる可能性が高まりました。その関係で、低血糖の危険性が低いままコントロールすることも可能になりつつあり、今までは対処法がなかった医者達も、処方の工夫ができるようになっています。
食事や運動量を一定させる必要がなくなったというわけではありません。食欲の趣くまま食べて寝転がっていたら、結果は明らかです。 生活習慣を正しくすることの意味は変わりません。ただ、昔と比べて食事内容にインスリン量を合わせやすくなったし、治療法に幅が出たので血糖値の変動を減らせるということです。 変動さえ小さくなれば、かなり血糖値を下げることが可能になります。そうなれば、合併症を予防できて寿命も延びると思います。
平成22年9月 診療所便りより