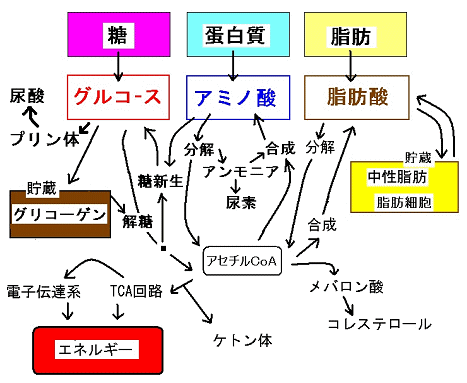1型糖尿病の療養経過
1型糖尿病は免疫系の反応によって発症する糖尿病で、当院にも患者さんがおられます。子供でも罹りますし、男も女も高齢者でも、生活習慣に問題がない人でも発症する可能性があります。
北欧には非常にたくさんの1型糖尿病の患者さんがいます。若い時に病気になるので成長期にも治療も続ける必要があり、悩みの多い時期を乗り越えるのは簡単なことではありません。最近、フィンランドの統計が発表されました(BMJ2011;343:d5364)。
治療法は年々進歩していますが、30年間の死亡率の推移を見ると必ずしも全ての世代で改善していたわけではありませんでした。 死因に関係するものとして、15歳以上で発症した患者さんにおいてはアルコール等の薬物が多いと書かれています。日本でもそうかもしれません。 日本では麻薬に相当する薬物の使用者は少ないと思いますが、アルコールは糖尿病患者でも飲まれる人がたくさんいます。飲まない人のほうが少ないかも知れません。
アルコールの影響は、糖尿病全般にかかってきます。アルコールは代謝失調を急に起こすので、対処が間に合わないと生死に関わります。
アルコールの代謝に関しては誤解が色々あると思います。栄養士や大学の栄養学の専門家も誤解、曲解があったように思います。下のような意見を聞かれたことはないでしょうか?
①アルコールは代謝されて身につかない、全て呼吸で排泄される。
②アルコールよりつまみが問題。つまみを何も摂らなければ良い。
③蒸留酒ならカロリーゼロとして考える。焼酎やウイスキーを勧める。
④80キロカロリーまでなら許可する。
いずれも誤解を生みやすい意見でした。
アルコールは粘膜をよく通過します。空腹時に飲むと直ぐ酔いますから、その速さを実感できます。 糖分やミネラルの吸収にも影響するので、例えば一過性に血糖を下げたり逆に上げたりします。
下の図は栄養素の代謝経路の概略を示しています。
アルコールはアセトアルデヒド→酢酸→アセチルコエンザイムAといった物質に分解されますが、アセチルコエンザイムA(アセチルCoA)は図の真ん中にあるように、栄養素に共通する代謝物質で、これから脂肪などが合成されます。炭酸ガスなどに分解されるまでには熱を発生します。したがってアルコールは、カロリーゼロとは言えません。
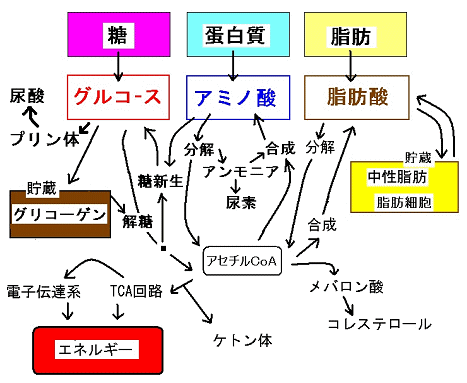
吸収されやすい性質から代謝経路を独占し、他の物質の吸収分解を全般的に阻害するのかも知れません。 糖尿病の薬と併せ飲みで低血糖を起こす、アルコール単独での急性中毒など、意識を消失する危険性は高まります。普段は血糖値が高いから大丈夫だろうと思っていると、思っていたより急速に吸収されたアルコールのせいで倒れる・・・そんな例は珍しくありません。
80キロカロリーまで許可するというのは、薬を使う必要がないほど状態の良い人に限定の話だったのですが、都合よく解釈して飲酒を続ける人も多いようです。薬を使っている人は禁酒するのが治療の原則です。
診療所便り 平成23年11月分より(2011.11.30up)