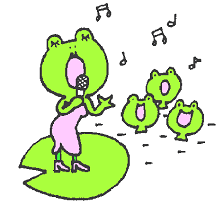AEDの効果
AEDとは
最近は公共施設を中心にAED(自動体外式除細動器)を設置する所が増えてきました。AEDは電気ショックを与えることで「心室細動」という不整脈を治療する機械です。人が突然倒れた時には、この心室細動が原因のことがあります。その場合は有効です。
AEDの実力
日本でAEDが使われた事例をまとめた報告が出ました(N Engl J Med 2010; 362:994-1004)。数年間の統計で、30万人の心停止者の中で1万人くらいが心室細動を伴っていたそうですが、その場で直ぐ対処できた人に限れば3割を救うことができたそうです。とても有効な機械だと言えます。
AEDの限界
この結果は、倒れた人全体の3割を救うと言う意味ではありません。心室細動によって倒れた人に直ぐ対処できた場合に限定してという意味で、直ぐに処置を始められなければ、いかに正しい方法で蘇生を試みても回復は期待できません。
また、不整脈以外の原因による場合、例えばクモ膜下出血などの病気には、心室細動を伴わないかぎり、効きません。
さらに、蘇生に成功しても回復後に後遺症を残さない人の割合は、人口100万人あたり年間1人以下とも書かれています。残念ながら、命は取り留めたが意識がはっきりしないといった症状が残る方がおられることは事実です。ドラマのように簡単に意識を回復し、話ができるとは限らないようです。
心室細動
私は蘇生が得意で、一般の医者より救命率が高く自慢していましたが、関わった患者さんは完全に心電図モニターが反応なし(フラットな直線状)のことが多く、心室細動は少ないという印象を持っています。モニターがフラットの時に、AEDは作動しません。
倒れてからの時間が長くなると心電図モニターは直線状になりますが、もっと早い時間なら「心室頻拍」という状態があります。この心室頻拍にもAEDの機械が反応しない場合があります。その場合はあわてず、心臓マッサージを再開して、搬送や連絡を急ぎ、しばらくすると心室細動に移行することが多いので、そのタイミングで再びAEDの機械を作動させてみることになります。
そのタイミングが実は問題で、持続的なモニターなしで心室細動にタイミングを合わせて作動させるのは、相当に慣れた勘の良い人でないと難しいはずで、救急隊員や一般の方では無理と思います。
蘇生の要領に関する私見
救急外来で私が不満に感じていたのは、蘇生措置を救急隊員がやると、病院への到着が遅れることです。気胸、出血性ショックなどは現場で蘇生処置をしても状態を悪化させるだけです。救急隊員は、いかに処置に慣れようとも診断能力や投薬に限界があるので、現場で粘られると病院でしか救命できない人の処置を遅らせます。統計上の理由で、そんな人のことは諦めよう、そのほうが成績が良いという理屈で救急体制が構築されているのですが、この理屈には誤謬があります。いわば統計を出すために限定した状況を、救急の指標と勘違いするように、学者や役人が犯しやすい誤りをやっているのかも知れません。
その場でAEDなどに反応した人を除けば、心臓マッサージをしながら速やかな移送開始を原則にすべきです。100万人に一人の成功を狙って、もっと多い人達を見殺しにしていたら愚かです。
人を救う行為に関して
AEDの使い方の講習会が時々開かれています。何も知らないでは使えませんから、受けてみられてはいかがでしょうか。救える命を救うという意識は大事だと思います。
ただし法律が追いついていない面はあります。蘇生を試みて命を取り留めた場合、普通なら感謝されて良いところですが、後遺症を残したために恨まれる、下手すると方法が良くなかったと訴訟を起こされることも覚悟する必要があります。
「そんなバカな、善意の行為を訴えるなんて」と、思われるかも知れませんが、救急外来では似たようなことをよく経験します。医者の場合は覚悟がありますが、一般の人はどうでしょうか?
平成22年6月30日 診療所便りより・・・・(2015.09.20up)