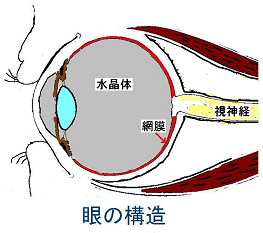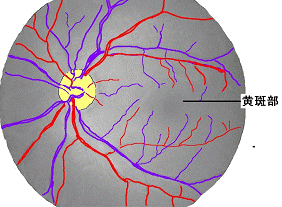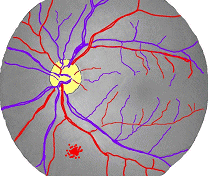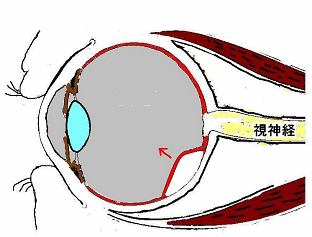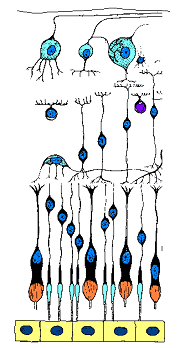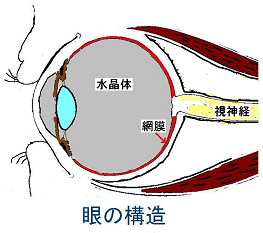
糖尿病性網膜症の話 勉強会資料 平成20年6月
糖尿病の合併症である網膜症についてまとめます。
網膜とは
網膜は、図のように眼の奥にある膜です。矢印をつけています。便宜上、水晶体や網膜にも色付けしております。
図の左側の毛が生えているところがマブタです。
網膜には血管がたくさんありますが、網膜を見れば外から観察できます。
網膜症の症状
① 症状がない場合が多い
② 色覚異常
③ 暗闇への順応力障害
④ 分解識別能(視力)の低下
糖尿病性網膜症は、進行しないと症状はないと言われています。詳しく検査すると、色覚異常が出現、あるいは暗闇への順応力が落ちる傾向があると教科書には書かれていますが、実際に患者さんから強く訴えられたことはありません。
光凝固の治療を網膜の広い範囲に受けた(汎網膜光凝固)ことのある人は、治療により暗闇での視力が落ちたと自覚されることが多いようです。これは、網膜の周辺部が明るさを感じるのに必要であるためのようです。
症状を感じるかどうかは、病変の場所にもよります。もし網膜の大事な部分に病変が出ると直ぐに感じられますが、同じ網膜でも周辺部に異常が生じた場合は症状がないこともあります。
網膜症が起こる理由
もちろん糖尿病であることが網膜症の原因ですが、糖尿病が原因になって網膜症が起こるには、いくつかの機序が考えられています。
#1 異常な物質がたまる
高血糖の状態にあると通常の代謝で生じにくい物質が産生されると言われています。このような物質は細胞から出て行きにくいので、どんどん貯まって細胞が機能しなくなるという現象が起こります。それが目や神経に害を及ぼしているのではないかというのが、ひとつの考え方です。
#2 異常な血管が誘導される
また、大きな出血が網膜に起こるのは新しくできた異常な血管(新生血管)が破れるからですが、新生血管ができる理由は、おそらく血管を作る細胞を誘導するような物質が眼の中に増えるからだろうと考えられています。本来の血管と違う成長をするので、破れやすい血管になります。
#3 血流、圧、炎症
眼の手術をしたとたんに網膜症が急激に悪化することがあります。また、片方の目だけひどく網膜症が進行していることもあります。これらは、単に細胞の中に何かの物質がたまるだけではない原因があることを想像させます。もしかすると、眼圧や血流、炎症も関係しているかも知れません。
#4 微妙なバランス
血糖値を急に下げた時に眼底出血が起こりやすいということは広く知られています。単に物質が何かたまるのがいけないなら、どんどん血糖値を下げればいいような気がしますが、そうでないのは網膜が微妙なバランスで成りたっていて、血糖値や血流、圧、いろんな物質の濃度が変化すると、病気が進行するのだろうと思われます。
眼底所見
眼科に行くと眼の検査をされますが、いったい何を見ているのだろう?と、思われたことはないでしょうか。
検眼鏡で目を外からのぞくと、眼底(網膜)が見えます。眼底検査の場合、検査する側からは右の画のように見えています。
右の図の真ん中やや左よりの白く丸い部分から血管(図の中の線)が放射線状に出ています。この白い部分は視神経の断面で、これが脳とつながっていて、視神経乳頭と呼ばれています。もし、この付近に炎症などが起こると、脳に情報が伝わりにくくなりますから、見えにくいという症状が出ます。
色や形を敏感に感じ取っているのは一部分です。図の矢印の部分で、ここを黄斑部と言います。黄斑部は敏感になっています。ここに出血やむくみ(浮腫)が起こると、小さな病変でも症状が出ます。ほとんど失明してしまう場合もあります。
逆に右図のように周辺部(右図)に出血が起これば、かなり大きな出血でも何の症状もないことがありえます。
このような出血のほかに白斑、浮腫などが網膜症の所見です。白斑とは、染み出したりした物質のうち、吸収されにくいものが網膜の近くに溜まった状態を指します。浮腫とは、炎症を起こしてむくんだ状態のことです。
網膜は薄い膜なので、剥がれてしまうこともあります。網膜剥離という言葉を聞くことがないでしょうか?若い人でも網膜剥離は起こりますが、糖尿病で出血した後にも剥離が起こります。出血して傷んだ部分を治そうとする反応が、周りの組織をひっぱる関係です。
剥離してしまうと、図のように網膜が前に引っ張られたように移動し、網膜に光が集まらなくなり、光の情報が視神経に伝わりにくくなりますので、失明の危険が高くなります。
網膜症の経過
#1 単純性網膜症と増殖性網膜症
単純性は、病気が初期の段階である~今は重症とは言えない状態を表す。
増殖性とは、病気が進行した~または重症と考えるべき(新生血管があって出血が予想される)状態を表す。
網膜症の経過を表す方法は、時代によっても結構変ります。
#2 単純性だから安心してよいか?
単純性網膜症だから軽症で、安心して良いとは限らない。
今の時点で視力に影響がある病変が少ないというだけで、次の瞬間に大出血が起こって失明する可能性はある。
この後どうなるかを表す分類法ではない。
#3 網膜症の進行具合は予想できない。
経過の個人差が大きい。
小さな出血→大きな出血→白斑→再出血→網膜剥離のように順番を追ってくるわけではない。
1年目はこれくらい、2年目は・・という法則もない。
血糖値がこうだから網膜症もこうという一貫性もない。
#4 一般的な傾向として、
初期の点状出血は、吸収されることが多い。
増殖性網膜症の段階で出てくる「新生血管」からの出血は、網膜以外の部分に影響を及ぼして視力障害を起こす可能性が高い。
網膜症の治療
網膜は、顕微鏡で見ると右の図のようにいくつかの層が重なっています。(上が硝子体側、下が眼の外側です)
光凝固
#1 光凝固の原理
網膜には特定の色の光を吸収する場所がある(主に細胞が多い層)
レーザー光を当てると、その部分がヤケドを起こす
ヤケドの部分は周囲とくっついて固まる
固まった部分は病状進行の防波堤になる
血管はヤケドを起こしにくいので、詰まりにくい
レーザー光は一種類ではなく、何種類もありますが、それぞれ効果を起こす場所が決まっています。光の種類や出力を選べば、害が少ないように調節できます。
#2 光凝固の効果
光凝固は有効ですが、全員の視力が改善するわけではありません。光凝固をした場合としなかった場合を比較すると・・・(早期網膜症治療研究ETDRSより)
黄斑部に浮腫みがあって視力が0.5以下の人の場合、直接病巣を凝固すると3年後に40%が視力改善、光凝固しないと20%しか改善していない。(つまり、光凝固は有効)
黄斑部に浮腫みがない人の場合または、黄斑部に浮腫みがあっても視力が1.2以上ある人は、光凝固する~しないで、視力に差がなかった。(つまり光凝固で全員の視力が改善するわけではない)
#3 光凝固の問題点
(多くは自然に回復することが多い)
光凝固療法をしても失明を予防できないことはある。
広範囲に施行すると、視力は落ちる(3割くらいの人) 暗点(見えない部分)が生じることがある
角膜を傷めることがある
瞳孔が散大することがある
水晶体が濁ることがある
網膜前や水晶体に出血することがある
網膜はく離の引き金になることもある
色覚異常、視野が狭くなる、暗闇で見えにくいなど
レーザー光の波長や力を調節して、徐々に成績は良くなっているようですが、思ったほど凝固の深さを調節できない傾向がありますので、計画ほど効果を実感できない可能性はあります。
硝子体手術
硝子体手術とは、濁った硝子体の除去を中心とした手術のことです。網膜の前、レンズの後のガラス球みたいな部分を取り除きます。
どのような場合に手術をするかについては、年々技術が進んでいますので今後も変っていくでしょうが、例えば以前は、硝子体に出血した血液が吸収されずに長く残った場合
黄斑部の網膜が剥離してしまって、他の治療に反応しない場合でしたが、近年はこれに加えて、
新生血管が多く、出血が予想される進行性の増殖性網膜症の場合などです。
網膜の大事な部分の出血や炎症が強い場合、剥離した部分が機能を失ってしまった場合は、せっかく硝子体を入れ替えても失明を防げない場合がありますので、硝子体手術は万能ではありません。網膜症が進行しないように努力しないといけません。
血糖コントロールと網膜症の関係
血糖コントロールと網膜症の進行具合については、今までの勉強会でも繰り返し説明してきました。血糖をコントロールすることで、網膜症の進行を遅らせ、視力を守ることができます。
1型糖尿病患者の網膜症に対する血糖の影響(DCCTより)
|
HbA1c 7% |
HbA1c 9% |
|
|
新たに発症 |
7% |
24% |
|
さらに進展 |
21% |
41% |
この表の見方
新たに発症とは、網膜症がない状態から新たに網膜症を発症することを意味します。
この割合が、HBA1cが7%だった人達では7%に止まっていたのに、HbA1cが9%の人達では24%もあったということです。
さらに進展とは、すでに網膜症があった方達が、さらに進行した割合を意味します。
HBA1c7%の方達の中で、すでに網膜症があった人の21%は治療にもかかわらず網膜症が悪化したが、HbA1c9%の人達では、この割合がさらに高く、41%も悪化していたということを意味します。
DCCT研究は、1型糖尿病患者さんをたくさん集めて、いっぽうの群には6年間強力なインスリン治療を行い、HbA1cを7%にまで下げ、HbA1cが9%の人達との差を比べました。6年間というのは病気になってからの年数ではありません。研究を始めてからという意味です。病気になってからの年数は、もっと長くなりますので、「自分は糖尿病と言われて6年経つから、もう網膜症になったのか・・」と、決めつける必要はありません。
表のように、血糖コントロールを保った人達は、コントロールが悪かった人達と比べて網膜症の進行具合が遅くなっています。
HbA1cがどれくらいなら網膜症の進行を止められますか?と、質問を受けますが、これについて決まりはないと思います。
いったん始まった網膜症は、簡単には治まらないこともあるからです。眼科で検査しても解らないくらいの程度で、ゆっくり病気が出来上がっていくことも考えられます。
ずっとHbA1c6~7%を維持できたら安心かというと、やはり網膜症が出てくる人はいます。表を見ても解るように、せっかくHbA1cを7%に保っても、6年間経つと7%の割合で網膜症が発生していました。
いっぽうで、HbA1cが9%であっても、多数の人が網膜症を発症しないでおられることも確かです。この表から見ると、研究開始時に網膜症がなかった人達の76%(100%-24%)が網膜症を起こしていませんでした。コントロールが悪いと、皆がどんどん悪化するわけではありません。運良く、何事も起こらない人もいるわけです。
でも、長期的に見ると血糖値をなるべく正常に近づけたほうが網膜は安定すると考えられますので、急激な変動がなく、しかも正常に近いくらい、そして低血糖が起こらないくらいに良好なコントロールを目差すべきだと考えます。
また、詳しい理由は解りませんが、血圧を厳密に治療した場合は、網膜症が悪化しにくいというヨーロッパの統計もありますので、血圧の治療もおろそかにはできません。血圧の目標は110~120くらいの、かなり低い値になります。