インスリンを守るとは、どのような意味か? 勉強会資料
平成19年6月14日
インスリンはどのような物質か?
インスリンは、膵臓などから分泌されるホルモンです。血糖(ブドウ糖)を細胞の中に取り込む際に、その効率を良くする力を持っています。これが働くと血糖値は下がり、血糖からエネルギーが作られます。

図のような簡単な構造をしていて、とても分解しやすく、光にあてると壊れてしまいます。このため、インスリン注射液は直射日光が当たらない場所に保管しないといけませんし、凍らせても壊れますので注意が必要です。
人の血液の中には一定の量のインスリンが流れています。食事をすると、食事に見合ったタイミングで膵臓からインスリンが分泌されます。これが肝臓を経由して全身にまわり、肝臓や筋肉の細胞の表面につきます(図の左上の方)。
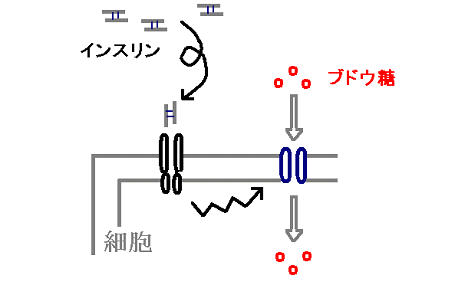
すると、細胞にはインスリンを受け止める受け皿があって、周りの細胞膜に働き、活発にブドウ糖を血液から細胞の中に取り込み始めます(図の右側)。結果として血糖値は下がり、細胞内では代謝が進んでエネルギーが作られます。
インスリンが多すぎるとどうなるか
インスリンによって血糖値が下がりすぎます。典型的なのは、インスリンを注射している人が食事を遅らせた時の低血糖発作です。また、稀に膵臓でたくさんのインスリンが作られた時(インスリノーマなど)にも低血糖発作が起こることがあります。低血糖の症状については今までの勉強会で学習した通りです。
実際には、インスリン量が多いのに血糖値も高いことのほうが多いようです。‘インスリン抵抗性’がある場合などです。もちろん、このような時に低血糖の症状はありません。
多すぎるインスリンによって皮膚に独特な所見が出る、血液中のミネラルの異常が出る場合もあります。動脈硬化も進みやすくなります。ただし、これはインスリン注射によって起こる副作用という意味ではありません。
どのような時にインスリンが多くなりすぎるか
インスリンが多くなるのには、血糖値が高いために必要があって多くなる場合と、不釣合いに多くて低血糖になる場合とがありますが、ほとんどの人はインスリンの効果が悪くなったために、たくさんないと効果が発揮できないから多くなるほうです。自覚症状は全くといってよいほどありません。
症状が出る時は、インスリンの注射に関係した場合が多いようです。インスリンの注射が食事や運動とうまく調整されない時は、インスリンが血糖値に対して多すぎることになります。注射量が正しくても、食事の時間が遅れる、仕事が忙しすぎるなどの場合には低血糖を起こします。逆に食事と運動内容が正しくても、インスリンの注射量を間違って多く射った場合も同様です。バランスが大事です。
インスリノーマは、インスリンを作る腫瘍(できもの)です。私達のインスリンは食事に合わせて量が調節されていますが、インスリノーマでは食事と関係なくインスリンが作られるため、低血糖になります。また、肺癌などに多いのですが、インスリンのような物質を作る腫瘍ができた時も急激に血糖値が下がります。ただし、これらは非常に稀ですので、一般には注射以外でインスリンが多すぎて困ることはありません。
インスリンが不足するとどうなるか
インスリンを使わずに血糖を下げる仕組みもありますが、インスリンほど効率の良いホルモンは今のところありません。
インスリンが少ない状態では、血糖を細胞に取り込む能力が低下します。血糖値が高くなり、腎臓の調節機能によって多くの場合は脱水になります。長期間このような状態が続けば元気がなくなり、合併症が起こりやすく、糖尿病性昏睡に陥る可能性も出てきます。
また、インスリン量があっても肥満や運動不足などの理由で効果が出にくい状況では、やはりインスリン不足と同じように血糖値が上がりやすい状態になります。
どのような時にインスリンは不足するか
1型糖尿病では、インスリンを作る細胞が少なくなります。
この病気は、インスリンを作る細胞を自分の免疫反応で壊してしまう不思議な病気です。よく子供で糖尿病になった方を見かけますが、多くはこの型です。
同じように、膵炎などの膵臓の機能が落ちる病気の場合もインスリンを作る機能が落ちます。
普通の糖尿病は2型糖尿病と言われ、インスリンを作る細胞はちゃんとあります。さきほど述べたように、量が充分あっても、効果が出にくい場合もあります。「インスリン作用の不足」「インスリン抵抗性」などと表現される場合です。
インスリン作用不足とは、どういうことか
インスリンがあっても、充分に効果を発揮できない場合があります。肥満がある糖尿病の方の血液中インスリン濃度は、軽く100マイクロ/mlを超えていることがありますが、これは健康な人より多いくらいです。でも血糖値は下がりきれません。
インスリンが効果を発揮するためには、運動や食事療法などの条件が整っていることが必要です。
血液中のインスリンを検査して、もし非常に多い量が出ている時には、もしかするとインスリンの効き具合が悪くなって、たくさんのインスリンがないと血糖値を維持できない状態になっているのかも知れません。分泌が多いから膵臓が丈夫だとは言えないわけです。
インスリン抵抗性が強い状態が続くと、血圧が高くなり動脈硬化が進むなどの悪影響があります。
インスリンの分泌はどのように調節されているか
インスリン分泌の調節機構は、まだ完全には解っていません。食事が胃腸の中に入ると、腸管が反応してインスリンを出させる物質を分泌し、これが膵臓に働く機序があると思われます。
その他に血糖値が上がると、インスリンを分泌する細胞が独自に血糖値を感知して反応性に分泌するとも言われています。
糖尿病の飲み薬には、インスリンを出す細胞にはたらいて、分泌される量やスピードを調節するものがあります。しかし、長期に刺激を繰り返すことになるので、やがて分泌量が減ってくる傾向があります。インスリンを分泌する細胞を増やし、分泌の力を強める薬の研究が行われています。
インスリンと血圧、動脈硬化
インスリンは血圧に影響すると言われています。
インスリンがたくさん血液中にあるのに充分に効果を発揮できない状態(先ほど述べたインスリン抵抗性が強い状態)では、動脈硬化は進み、血圧が上がり、中性脂肪やコレステロールも高くなる傾向があるらしいと言われています。
ではインスリン注射をするとインスリンが増えるから、動脈硬化が進むのか?と思われるかも知れませんが、注射で血糖値がコントロールされれば、そちらの効果のほうが強いので動脈硬化が抑えられることが証明されています。
つまり、血糖値がコントロールされることが、高血圧や動脈硬化の予防のためにはまず大事です。インスリン抵抗性の問題と注射によるインスリン量の増加の問題は別と考えるべきだと思います。
ブドウ糖負荷試験とインスリン
ブドウ糖負荷試験を受けたことがありますか?
糖尿病の診断をする時に検査します。この検査で、血糖といっしょに血液中のインスリン量を測定すると、下のグラフのようになります(正常は黒色)。
インスリンの量には個人差、年齢差があるので、あくまで傾向としての話ですが、糖尿病の人もちゃんとインスリン分泌はあり、始めは多すぎるくらいですが、徐々にインスリンの分泌が遅くなり(青の線)、やがて少なくなります(茶色)。したがって、インスリン分泌が多いから、自分の膵臓が丈夫なのだと考えないようにしないといけません。
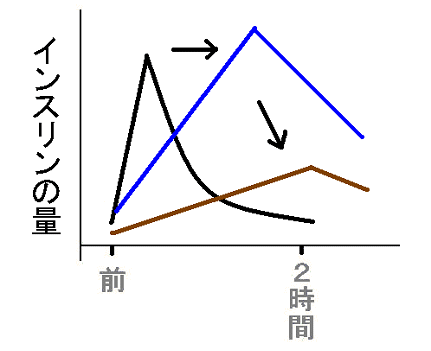
インスリンを守る会
「インスリンを守る会」が活動していました。
変な名前の会だなと思われたかもしれませんが、分泌されるインスリンが少なくならないようにしようという考え方からできた運動です。
活動の内容は、ご自分のインスリンの分泌ぐあいを調べて、運動や食事療法に精を出して反応を見るというものでした。
食事療法をせず、何にも運動をしないでおくと、インスリンをたくさん必要とするため、インスリンを出す膵臓が疲れてしまって、やがてインスリンの分泌も減ってしまう傾向があります。そのような時には、多くの場合、糖尿病になっていることが多いようです。会は、それを予防する運動です。
どうすればインスリンの分泌を保てるのか
実はこの話は推定にすぎません。確実な統計がないからです。
膵臓に負担をかけているとインスリンを出す細胞が活動できなくなるらしいことが学者の研究で分っていますので、膵臓に負担をかけることを避けるべきだろうと考えられています。
具体的にどうすれば負担がかからないかというと、まず食事のカロリーを取り過ぎないことが必要だと思います。運動をたくさんやっても、食事のカロリーがあまりに多いと消化吸収に負担がかかると思えるからです。
ただし、昔の日本人と今の日本人とで食事のカロリーが倍も違うわけではありませんので、カロリーだけの問題ではないはずです。食べる速さも関係しているかも知れません。いっきに甘いものを食べると、代謝するためにはたくさんのインスリンを早く出さないといけませんが、これは負担になるだろうと思われます。
食べる内容も関係しているかも知れません。例えば、昔の日本人はカロリーのほとんどをお米などの炭水化物から摂っていましたが、今は脂肪分の多い食品が増えて、そのため代謝に負荷がかかっていると思われますので、脂肪分を減らせば良いかも知れません。
食物繊維が多いと同じカロリーを食べても血糖値の上昇が軽くなりますが、膵臓への負担も軽くすむことが期待できます。したがって、野菜を増やせば膵臓を守ることにつながるかも知れません。
皆さんご存知の糖尿病食は、このような考え方から勧められている健康食です。糖尿病になったら糖尿病食が必要になるのではなく、予防のために有効な食事だと私は考えます。インスリンは血糖値以外にも、高血圧、コレステロール、動脈硬化に関与しますので、糖尿病食を食べることで、代謝全般に効果があると思われます。
薬の中にはインスリンの効果を高めるものや、糖の吸収を遅らせる効果があるものもあります。これらの薬では糖尿病を予防する効果も証明されています。インスリンの分泌を保つ効果もあるかも知れません。
過去の研究結果から今のところ考えられる方策を述べましたが、ここで述べたことが正しいかどうかは、今後の本格的な統計の結果を待たないと何とも言えません。
飲み薬とインスリン分泌
糖尿病の飲み薬の中で、インスリンの分泌を増やして血糖値を下げるものがあります。代表的なのはオイグルコン、グリミクロンです。これらの薬を長期間飲んでいると、インスリンを出す細胞が疲れてしまうのではないかという考え方があります。
実際のところ、長期間飲んでいた患者さんのインスリン分泌量は極端に少なくなっていることがありますので、その可能性はあると思いますが、糖尿病の病気の自然経過からも、また年齢からもインスリンの分泌は減りますので、薬の影響だけの問題ではないと思います。
ただし、「薬を飲んでいれば血糖値が下がるから、精一杯食べても大丈夫。パクパク食べよう!」という考え方は確実に間違いだと思われます。膵臓に鞭打つようなことをすることになるからです。
糖尿病の薬でも、別な系統ならば膵臓への負担が軽くてすむかもしれません。ベイスン、グルコバイ、メデット、アクトスなどが代表です。これらの薬は、インスリンを分泌させるのではなく、糖の吸収を遅らせるかインスリンの効果を助ける効果があります。しかし、これらの薬だけでは効果に限界がありますので、結局オイグルコンなどを併用しないといけない場合が多いようです。
糖尿病の薬を飲むと膵臓に良くないなら、血糖が高くても薬を飲まないほうが良いのではないかと質問されることがあります。統計の結果では、血糖を高いままにしておくことが最悪の結果を招いていますので、膵臓の保護について考えるより、まず血糖値のコントロールのほうを優先されたほうが良いと思います。血糖値が低いなら、薬の種類を考えて膵臓の負担が少ないものにすべきでしょう。